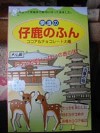柳生街道
 日帰りバスの旅にすっかりはまっている。何せ時間さえ守れば座っていても目的地に連れて行ってくれる。
時間的な制約はあるものの、ちょっとどんなところかなぁという下調べ的なものには実に便利ということである。
日帰りバスの旅にすっかりはまっている。何せ時間さえ守れば座っていても目的地に連れて行ってくれる。
時間的な制約はあるものの、ちょっとどんなところかなぁという下調べ的なものには実に便利ということである。
そこで今回、近畿日本ツーリストの「歩くクラブ」が企画している「柳生街道と春日大社万灯篭を巡る」というのに参加した。
柳生街道は以前、三重県側から奈良県境まで歩いた。車で行っていたので駐車場まで戻らなければならなかったのだ。
歩き残した部分を丁度歩けるのが参加した大きな理由。「歩くクラブ」というのはハイキングが目的である。初級から上級までクラス分けされている。歩くことはそんなに苦ではないがどのくらいが初級なのかが分からない。ということでまぁ中級でというところ。7キロを3時間というので楽でもある。
街道入口まで、トイレ休憩を入れて3時間のバスの旅。

歩き始めるに当たってガイドから注意がある。なんと山岳ガイドが付くのである。そして準備体操をやらされる。
高低差200M、距離7キロ、3時間の予定である。時間はたっぷりあるしゆっくり写真でも撮りながら行こう……と歩き出して驚いた。かのガイド氏先頭で飛ぶがごときスピードである。同行の中高年諸氏もかなりの速さである。皆さんトレッキングシューズと杖?としっかり山行きの装備である。私たちはカメラを手に提げのんびりムード。しかたがない、「しんがりを行きマース」と断って歩き始めた。

はるか昔、柳生一族がこの道を駆け抜けたんだなぁ…なんてことを考えながら、あっちを見たりこっちを写したり。大きな岩に彫られている観音像、高い崖に刻まれた仏様に昔人が、何を願い何を思ったのであろうか。
初めは私たち二人だったのがいつの間にか増えている。曰く「時間がたっぷりあるんだからもっと楽しんで歩きたい」 そうでしょうとも、どうぞご一緒に…とにんまり。
 荒木又ヱ門が試し斬りをしたと伝えられる首切り地蔵のところで40分の昼休み。
荒木又ヱ門が試し斬りをしたと伝えられる首切り地蔵のところで40分の昼休み。
何日か前に降った雪が残っているようなところで、風も冷たく瞬く間に体が冷えてくる。若いうちはたっぷりの休息は体力を回復する。中高年は、途中での長い休憩は却って歩けなくなるのだ。たまりかねた一人が「もう出発してください」と言い出す。
速く歩きすぎて予定の時間が余ったとかで「こちらにまわりましょう」と春日山石仏群へ。そこで道を間違える。何なのだ。このガイドは!
折り返しは、世界遺産登録の「春日山原始林」の中の平坦な道。集合時間の調整からか今度はいやにゆっくりである。変わらぬ速度で歩いている私たちは「速く行かないように」と注意される始末。「質問は何でもどうぞ」というふれこみだったので尋ねる。「人口の手が加わってないのを原生林といいますけど、原生林といわずに原始林というのはなぜ?」答え一発「分かりません!」なぜなら「僕は大台ケ原の案内人であってここはよくしらない」 。何なのだ。このガイドは!
想いのかなたに心弾ませながら……のはずであった。
今も静寂の中にあって、苔むした足下の土の息ずかいに耳を済ませたいとも思っていた。
それなのに、何がなんだか分からない消化不良な状態のうちに終わってしまった。
ガイド氏と別れてなにやらほっとした柳生街道でした。
近ツーさん、ガイドを付けるのは結構だけど今回はちょっとなぁ…でござんしたよ!
春日大社万灯篭
 温泉で、消化不良のハイキングの疲れをとり、夕食も済ませ、節分の行事「万灯会」見物にと繰り出す。
温泉で、消化不良のハイキングの疲れをとり、夕食も済ませ、節分の行事「万灯会」見物にと繰り出す。
帰りの集合時間だけ守れば後はフリーというのは助かった。明るい時間に通った時は、神官も巫女さんも警備の方々も準備に追われ忙しげに行きかっており、 まーるい目をした鹿がのんびりと迎えてくれていた。
まーるい目をした鹿がのんびりと迎えてくれていた。
すっかり日が落ちた境内は昼とはまったく違う顔を見せている。明かりは灯篭にともされたろうそくの灯のみ。かなりの数があるけれど足元が見えない。
節分というと家族でわいわい言いながらの
豆まき、有名寺の華やかな豆まきを想いうかべる。

万灯会は節分と夏の旧盆に行われるとのこと。豆まきの喧騒はなく寒い頃ゆえ人出も少なく、「寒いですけどいらっしゃるなら節分の方がいいですよ」と言われるのにも納得であった。
ほの暗い中を足元に気をつけながら歩いて行くと、ひときわ明るい灯をつけているところがある。 緋の袴をつけた巫女さんが可愛い提灯を売っている。一灯ずつ丁寧に蝋燭を燈して渡している。懐中電灯を持ってくれば良かったかなぁと思っていたところでもあり提灯のかわいらしさに惹かれて手が出る。500円であった。Maxは「またぁ…、邪魔になるよ」と言う顔をするが
提灯も巫女さんも可愛いいから……ネ。
緋の袴をつけた巫女さんが可愛い提灯を売っている。一灯ずつ丁寧に蝋燭を燈して渡している。懐中電灯を持ってくれば良かったかなぁと思っていたところでもあり提灯のかわいらしさに惹かれて手が出る。500円であった。Maxは「またぁ…、邪魔になるよ」と言う顔をするが
提灯も巫女さんも可愛いいから……ネ。

高台から下を見ると長い参道を灯篭の灯が縁取っている。行きかう人の波は闇の中に沈んでいる。社殿からは神官たちのささげる祈りの声が聞こえてくる。寒い冬から暖かな春への季節の移ろいを待ちわびる人々の心が伝わってくるようであった。
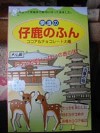
帰り道のお土産屋さんで、面白いものを見つけた。奈良といえば鹿に纏わるものは多いが、これはなんと「鹿のふん」というのだ。なんと言うネーミングかと二人で大笑いした。もちろん買った。小さなお饅頭のようなものが入っていた。美味しいと言えるものではなかったが、話題にはなった。「どこに行ってもくだらないものを見つけるねぇ」と変な株は上がったようだ。
2004年2月
 日帰りバスの旅にすっかりはまっている。何せ時間さえ守れば座っていても目的地に連れて行ってくれる。
時間的な制約はあるものの、ちょっとどんなところかなぁという下調べ的なものには実に便利ということである。
日帰りバスの旅にすっかりはまっている。何せ時間さえ守れば座っていても目的地に連れて行ってくれる。
時間的な制約はあるものの、ちょっとどんなところかなぁという下調べ的なものには実に便利ということである。

 荒木又ヱ門が試し斬りをしたと伝えられる首切り地蔵のところで40分の昼休み。
荒木又ヱ門が試し斬りをしたと伝えられる首切り地蔵のところで40分の昼休み。 温泉で、消化不良のハイキングの疲れをとり、夕食も済ませ、節分の行事「万灯会」見物にと繰り出す。
温泉で、消化不良のハイキングの疲れをとり、夕食も済ませ、節分の行事「万灯会」見物にと繰り出す。 まーるい目をした鹿がのんびりと迎えてくれていた。
まーるい目をした鹿がのんびりと迎えてくれていた。
 緋の袴をつけた巫女さんが可愛い提灯を売っている。一灯ずつ丁寧に蝋燭を燈して渡している。懐中電灯を持ってくれば良かったかなぁと思っていたところでもあり提灯のかわいらしさに惹かれて手が出る。500円であった。Maxは「またぁ…、邪魔になるよ」と言う顔をするが
提灯も巫女さんも可愛いいから……ネ。
緋の袴をつけた巫女さんが可愛い提灯を売っている。一灯ずつ丁寧に蝋燭を燈して渡している。懐中電灯を持ってくれば良かったかなぁと思っていたところでもあり提灯のかわいらしさに惹かれて手が出る。500円であった。Maxは「またぁ…、邪魔になるよ」と言う顔をするが
提灯も巫女さんも可愛いいから……ネ。