『 中山道を歩く - 美濃路(7)伏見宿 』
伏見宿は、江戸開府と同時に設けられた宿駅ではなく、土田宿の廃止に伴って新設された代わりの宿場である。
北西の木曽川畔にあった新村湊は、瑞浪や大井など、中山道の荷物積み出し港 として大いに賑わい、伏見宿の発展を陰から支えた。 明治に入り、人の移動
手段が鉄道に代わり、中央線もここを通らなかったこと、 川を利用した船運輸送が無くなったことで、すっかり寂れてしまった。
御嵩宿~伏見宿
喫茶店で一服したので、伏見宿に向かって歩き始める。
 御嵩駅前まで戻り、旧中山道を京方面に歩く。 右手に願興寺の駐車場、その対面の左手には 秋葉神社 などを合祀した一角があった。
二百メートルくらい先で左へと、枡形に曲がり、更に五百メートルくらいで右へ曲がる。 旧中山道を歩いても、これといった古いものはなかった。
間もなく国道
21号線にぶつかった。 時間にゆとりがあったので、願興寺の仏像を救った僧侶達がいたという 愚渓寺 に足を伸ばすことにした。 国道を横切り、
五百メートルほど坂道を登ると、右手に 御嵩小学校 がある。 その奥に愚渓寺があった (右写真)
御嵩駅前まで戻り、旧中山道を京方面に歩く。 右手に願興寺の駐車場、その対面の左手には 秋葉神社 などを合祀した一角があった。
二百メートルくらい先で左へと、枡形に曲がり、更に五百メートルくらいで右へ曲がる。 旧中山道を歩いても、これといった古いものはなかった。
間もなく国道
21号線にぶつかった。 時間にゆとりがあったので、願興寺の仏像を救った僧侶達がいたという 愚渓寺 に足を伸ばすことにした。 国道を横切り、
五百メートルほど坂道を登ると、右手に 御嵩小学校 がある。 その奥に愚渓寺があった (右写真)
駐車場から入口に入る前に、大きな石灯籠があるのにビックリした。
 「 大智山愚渓寺といい、臨済宗妙心寺派の寺院で,妙心寺第五世義天玄承禅師(ぎしょうげんしょうぜんじ)が
応永三十四年(1427)、当地鈴ヶ洞に創建した寺である。
「 大智山愚渓寺といい、臨済宗妙心寺派の寺院で,妙心寺第五世義天玄承禅師(ぎしょうげんしょうぜんじ)が
応永三十四年(1427)、当地鈴ヶ洞に創建した寺である。
義天禅師は 臥竜 と名付けた石庭を作庭し、禅の世界を表現するともに、修行の道場としての位置付けを与えた。
天保十年(1840)、現在地に移築され、二重塔を含めて伽藍が整えられるとともに、石庭も再現されて、今日に至る。 」 と、案内にあった。
これから推察すると、願興寺が兵火を受けた時代には、願興寺に近いところにあったのだろう。 山門から入ると、予想した以上に建物がしっかりして
おり、庭の手入れもきちんとされ
 ていた。 山額には、 古禅林 と書かれているが、 朝鮮国花庵 の筆で、将軍就任の慶賀使として来日した際に揮毫したものである。
大方丈の前にある石庭は、京都・竜安寺石庭の原形ともいわれるものである。 真白な砂に波紋と直線が織りなす造形、岩をさりげなく配する絶妙なバランス。
まさに見事の一言につきた (右の上下二つの写真)
ていた。 山額には、 古禅林 と書かれているが、 朝鮮国花庵 の筆で、将軍就任の慶賀使として来日した際に揮毫したものである。
大方丈の前にある石庭は、京都・竜安寺石庭の原形ともいわれるものである。 真白な砂に波紋と直線が織りなす造形、岩をさりげなく配する絶妙なバランス。
まさに見事の一言につきた (右の上下二つの写真)
しかも、無料でだれでも入れるのは大変良い。
私だけしかいなかったので、砂の波紋と岩を眺め、しばしの間、自分だけの 時間と空間 を楽しむことができた。
ここまで、駅から1.5キロあるかないかという距離である。
旧中山道は国道21号に合流してしまっているので、国道に戻り、伏見宿に向かう。
 少し歩くと、右側に、鬼の首塚があり、脇の石碑には、 関ノ太郎 の名が彫られていた。 鬼の首塚は、塚という程の高さはなく、社も質素である (右写真)
少し歩くと、右側に、鬼の首塚があり、脇の石碑には、 関ノ太郎 の名が彫られていた。 鬼の首塚は、塚という程の高さはなく、社も質素である (右写真)
傍らに書かれていた鬼の首塚の伝説は、鬼岩に住む鬼を退治するなかなか面白い話である。
先程訪れた願興寺境内にあった願興寺略縁起にも、「 正治元年(1198)の頃、御嵩の東方の奥岩に、関の太郎という、妖怪を使う賊がいて、願興寺界隈に出没
しては悪業三昧を繰り返しており、地頭纐纈盛康が、これを討ち取り、首を中村地内にねんごろに葬った 」 、と書かれている (巻末参照)
このあたりは 桶縄手 と呼ばれ、 木曾街道膝栗毛 を著わした 十辺舎一九は、
『 桶縄手 今もその名を 朽ちさりき 塩づけにせし 鬼の首かも 』 と詠んでいる。
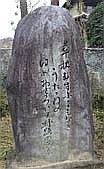 歴史上で鬼とされたものには、政府に逆らう反逆者や反体制者を支配者(政府側)が鬼に
歴史上で鬼とされたものには、政府に逆らう反逆者や反体制者を支配者(政府側)が鬼に
仕立てあげたということが現実には多い。 この話は、この地方で勢力があり、中央政府
に対抗した人物を鬼退治という形で表現したのではないだろうか? 関ノ太郎に関する
伝説が、この地方のその他の地にもあるので、そのような気がする
のである。
傍らに、正岡子規の歌碑があった。 子規が明治三十四年(1891)五月、木曽路を通って、
郷里の松山に帰る際記した かけはしの記 で詠まれた歌である
(右写真)
『 草枕 むすぶまもなき うたたねの ゆめおどろかす 野路の夕立 』
歌碑の脇に、かけはしの記の一部が墨で書かれていた。
「 御嵩行き越えて、松縄手に出づれば、数月の旅の労れ発して、歩行もものうげに覚ゆ。
肩の荷>卸して、枕とし、しばし木の下にやすらひて、松もあるじと頼めば、心地ただうと
うととなりて、行人征馬の響もかすかに聞ゆる頃、一しきりの夕立、松をもれて、顔を打つ
にあえなく、夢を驚かされて、荒物担ぎながら一散にかけ去りける。 浮世の旅路是非も
なきことなり。 」
子規も嶮しい木曽路や大井宿からの十三峠を越えてほっとしたのか、旅の疲れがでたの
ではないだろうか? うとうととしていたら、いつの間に来たか、夕立により心地良い眠り
 を醒まされたという、夕立に驚く様と夢路を妨げた恨みを少し込めた句であろう。
を醒まされたという、夕立に驚く様と夢路を妨げた恨みを少し込めた句であろう。
伏見に向かって歩く。
大庭の交差点の右側に 御嶽教会大平講大社長 とある大変大きな石碑と並んで 覚清霊神 の碑があり、裏には平屋の社務所のような建物があった。
くわしいことは分からないが、山岳宗教の 御嶽教 の一派なのだろう (右写真)
それにしても大きな石碑である。
ここから2km近く国道を歩くと、 顔戸の交差点。 顔戸は ごうど という地名だが、顔をごうとは読めないね!! 左側には可児川が流れていて、桜の木が
両脇にある。 水面には鴨が3組泳いでいた。 近くに、コンビニがあったので、暖かな飲み物を買って飲んだ。 寒い日には暖かなものが一番と感じた。
 ここから少し入ったところに名鉄広見線の顔戸駅があり、その近くに 在原行平の石碑 がある。
「 在原行平は、百人一首で有名な在原業平の兄で中納言で、歌人としても知られた。 碑は、美濃国の国司だった徳を偲んで、寛保三年(1743)に建てられた
もの。 」 とあったが、何故、江戸時代になって碑が建てられたのか?、疑問が残った。
空が時雨れてきて、ぱらぱらと服装を濡らしはじめた。
その先、右に行く道があるところが比衣である。 角に 比衣の一里塚跡 の石碑があった。
石碑がなければ、分からなかっただろう (右写真)
ここから少し入ったところに名鉄広見線の顔戸駅があり、その近くに 在原行平の石碑 がある。
「 在原行平は、百人一首で有名な在原業平の兄で中納言で、歌人としても知られた。 碑は、美濃国の国司だった徳を偲んで、寛保三年(1743)に建てられた
もの。 」 とあったが、何故、江戸時代になって碑が建てられたのか?、疑問が残った。
空が時雨れてきて、ぱらぱらと服装を濡らしはじめた。
その先、右に行く道があるところが比衣である。 角に 比衣の一里塚跡 の石碑があった。
石碑がなければ、分からなかっただろう (右写真)
右斜めに入る道があるので、入っていく。 細い道が左右に曲がりながら続いている。
 竹林の脇を通りぬけて、住宅が多くあるところを抜けると、また、国道に合流した。
竹林の脇を通りぬけて、住宅が多くあるところを抜けると、また、国道に合流した。
これが伏見宿までの道で僅かに残された旧中山道だった。 古くから住んでおられる人も
いるのだろうが、奥には住宅分譲された団地や中学校もできているので、旧街道が忘れ去
られていくのも時間の問題かも知れない、と思った。
国道に合流する手前の道端に石標があり、左伏見宿/右御嵩宿とあった (右写真)
高倉口の交差点を越えると登りになり、 名鉄八百津線 を越えるのだが、この路線は
99年9月で廃線になったので、いくら待っても電車は来ない。
左側に目を転じると、あたり一面、田圃が広がっていて、時雨れて遠くが霞んで見えた。
ここを上ると、伏見宿である。
( ご 参 考 ) 大智山愚渓寺縁起
妙心寺第5世義天玄承禅師(ぎしょうげんしょうぜんじ)が応永十七年(1409)当地、春木の里に無著庵を結び、応永三十四年(1427)、当地鈴ヶ洞に移し、創建し、山を大智山といい、寺を愚渓寺と名付けた。
藤木道藤、大垣内衛門、今井左近、三開基・細川勝元、土岐美濃守等の庇護の下、寺は盛んになった。
義天禅師は 臥竜 と名付けた石庭を作庭し、禅の世界を表現するともに、修行の道場としての位置付けを与えた。
天保十年(1840)、現在地に移築され、二重塔を含めて伽藍が整えられるとともに、石庭も再現されて、今日に至る。
( ご 参 考 ) 鬼の首塚の伝説
鎌倉時代の建久、正治の頃(1190~1200)のこと。
鬼の太郎 は西美濃の不破の関の生まれだったので、 関ノ太郎 と呼ばれていた。
正治元年(1199)、地元民が悪事の限りを尽くして人々を困らせていた 関ノ太郎 を退治するよう、地頭・交告源吾盛康に訴えたが、地頭は京にいて帰れないため、家臣4名に帰郷させて、退治を命じた。
しかし、なかなか討つことができなかったので、蟹薬師 に祈願したところ、 蟹薬師から「 太郎が女装して祭礼の日に現れる」 というお告げがあった。
お告げの通り、4月1日の祭礼の日に、女装して 太郎 が現れたので、討つことができた。
4人は太郎の首を京まで運ぼうとしてここまできたら、急に首桶が重くなり、一歩も歩けなくなった。
さらに、首桶を縛っていた縄が切れ、中から首がこぼれ落ち、落ちた首も動かすことが出来なくなったのである。
仕方がないので、太郎の首をこの地に埋めた。
( ご 参 考 ) 願興寺略縁起
願興寺境内にあった願興寺略縁起には、
『 正治元年(1198)、地頭の纐纈源吾盛康が寺を復興させた。
この頃、御嵩の東方、次月の地の 奥岩 に、関の太郎 という、妖怪を使う賊がいて、願興寺界隈に出没しては悪業三昧を繰り返しており、地頭の纐纈盛康は、これを討ち取り、首を中村地内にねんごろに葬った。
今もその地が「鬼の首塚」として、願興寺の北西に残っている。 』
と、刻まれていた。
伏見宿
 伏見宿は、廃線になった名鉄八百津線の線路のあたりの高倉集落あたりからである。
伏見宿は、廃線になった名鉄八百津線の線路のあたりの高倉集落あたりからである。
坂道を上ると、すぐ左が本陣だった場所で、しらない間に宿場の中心に着いてしまった。
本陣は、代々、岡田家が務め、門構えと玄関のある百二十坪の建物だった、というが、公民館になっていた。
本陣だったことを示す石碑は、道路側にあった (右写真)
伏見宿は御嵩宿開宿の約九十年後に、土田(どた)宿 (現、可児市土田)の廃宿にともない、誕生した新宿である。
宿村大概帳によると、宿場の長さは五町十六間(約570m)で、そこに、家の数八十二軒、四百八十五名が住み、本陣、脇本陣、問屋が各一軒、旅籠が二十九軒があった。
御嵩宿と旅籠数はほぼ同じであるが、規模は小さかったようである。
 御嵩宿は木曾方面への旅に備えて宿泊という客であったのに対し、伏見宿は遊べるところ
御嵩宿は木曾方面への旅に備えて宿泊という客であったのに対し、伏見宿は遊べるところ
と旅人の間では人気があった。 本陣碑の隣に、「是より東尾州領」と刻まれた領界石が
>立っているが、もともとは伏見小学校の校庭にあったのだが、体育館の建設に伴い、ここに
移設したのである (右写真)
土田宿は東山道時代からの古い宿場で、中山道の開設と同時に宿場になったが、慶安四年
(1651)、伏見から鵜沼までのルートが土田、犬山経由から太田、鵜沼東、西町経由に変えら
れたため、宿場の機能を失っていき、元禄七年(1694)に廃宿されてしまった。 伏見宿は
それまで間の宿だったが、宿場鑑札を得たのは、ルート変更の四十三年後の元禄七年(1694)
のことである。 街道が変更された慶安四年から除々に宿場の体裁を整えていったものと思わ
れる。 飯盛り女を多くかかえて宿場稼業を続けたのはこれらが関係しているのかも知れな
 い。 少し歩くと、伏見の交差点で、右手前の家の一角に、道標があった (右写真)
い。 少し歩くと、伏見の交差点で、右手前の家の一角に、道標があった (右写真)
気を付けない通り過ぎてしまうくらい小さなものだが、 右 御嶽、左 兼山八百津 と刻んで
あり、兼山道との追分である。 名鉄八百津線が廃止になったので、地域バスが
明智駅
からでているが、そのバスが曲がって行くのが見えた。
伏見宿は、旧中山道が交通量の多い国道21号になってしまったので、当時の町並みはほとん
ど残っていない。 しかし、古い家は交差点の左側に数軒並んで建っていた。
 卯建や連子格子を持つ黒塗りの建物である。
卯建や連子格子を持つ黒塗りの建物である。
手許の資料にある 三吉屋 という元旅籠や、煙草屋の看板がある家を探したが、どれだったのか分からない。
信号から二軒ある家の手前が旅籠、奥が煙草屋なのかなあ!!、と思ったが ・・・・
家も荒れ始めているので、今後これらの家屋がどうなるか心配である (右写真)
伏見宿では、これらの建物だけが当時の面影を伝えていた。
交差点を左折し、真っ直ぐ行くと、明智駅。
途中に「是より東は尾州領」と刻まれた領界石が置かれていた伏見小学校がある。
 手前に、真宗大谷派竹山浄覺寺という寺があった (右写真)
手前に、真宗大谷派竹山浄覺寺という寺があった (右写真)
徳川光友御菩提所 と刻まれた碑があった。 徳川光友は、尾張徳川家第2代だった人物であるが、なぜ彼の墓がここにあるのだろうか? 写真を撮っていると、車が寺の中に入り停まるのが見えた。 檀家が墓参りにきたのだろうと思っていた。 寺の建物はかなり立派なので、中に入っていった。
すると車を停めた男性が「ありがとうございました。」と声をかけてきた。 びっくりして、そっちをむいた。 寺の住職であった。 なかな饒舌家で、いろいろ話をしてくれる。
① 岐阜県には浄土真宗は多いのだが、この地区は少なくこの寺だけ。
② 本願寺は信長との戦いで和戦派と抗戦派があり、それが東本願寺と西本願寺になった。
③ 東本願寺は家康に保護され、現在の場所に大きな土地を貰ったが、当時は沼地でどう
しようもないところだった。
と、本願寺の由来を話し、当寺はかなり古い歴史を持つ寺で、
それを示す山門や鐘楼残っていたが、それを壊して今日のような建物に変えてきた、と自慢げ
である。 また、宿場について
 ① 旅籠は御嵩などにくらべ貧弱だったが、女が多く、飯盛り女や女郎を売り物にしていたので、それを目的にきた人で賑わっていた。
① 旅籠は御嵩などにくらべ貧弱だったが、女が多く、飯盛り女や女郎を売り物にしていたので、それを目的にきた人で賑わっていた。
② 宿場で商いを営んでいた人達は明治の廃宿で、東京、名古屋、古知野(現在の江南市)などに出ていってしまい、その後に、近辺から来た人たちが入り、商売などについた。
従って、現在このあたりに住んでいる人は、明治以降のひとがほとんどである と、教えてくれた。
境内には、岐阜県名木の指定を受けた 数百年を経た古木(名前をいわれたが忘れた)があり、その脇に芭蕉の句碑が建っていた (右写真)
『 古池や かわず飛び込む 水の音 』
幕末に近いころ、美濃地方(岐阜県)には、俳句に熱中する多くの人々がいたので、指導を
職にした師匠と称する人も少なからずいた。 この句碑も地元の俳諧の人達が金を出し合
って建てたものらしい。
壊した古い建物の瓦が残っているとのことだったが、それは見ず、
御礼を述べて退去した。
小学校の裏側にある洞興寺へ向かう。 夕方だったので、子供達が校庭で遊んでいた。
 校庭の中に、江戸時代のものがないか覗いたが、なかった。
校庭の中に、江戸時代のものがないか覗いたが、なかった。
洞興寺は、河北山洞興禅寺 といい、境内には大きな山茶花の木があり、盛りは過ぎて
いたが、一部がまだ咲いていた (右写真-洞興禅寺入口にある標柱と鐘楼門)
寺の右側に最近再建された子安観音堂があった。
「 子安観音堂に祀られている観音は古いもので、何回かの火災からも逃れて、その度に
洞興寺に預けられていた。 お堂を再建できたことで、やっと元の鞘に収まった。 」
 と、いうようなことがながながと石碑に書かれていた。
と、いうようなことがながながと石碑に書かれていた。
観音堂は旅人の道中安全を祈願しに立ち寄った他、宿場の人々が祈った場所である。
観音堂の前に、 女郎塚 と呼ばれる塚がある。 いつ築かれたものか分からないようであるが、塚の上に多くの石仏が奉納されていて、 三十三観音 といわれている (右写真)
一説では、「この宿には多くの飯盛り女が働いていたが、身寄りのないものも多かったので、死後、塚に葬むられた。」ことから、女郎塚と呼ばれるようになったともいわれ、
「 三十三観音はこの宿で死んでいった仲間を悼んで、彼女達が奉納した。 」 とも伝えられる。
真相は分からないが、彼女達とのかかわりがあるのは間違いないだろう。
 国道に戻り、先に進むと右側に東濃実業高校がある。
国道に戻り、先に進むと右側に東濃実業高校がある。
宿場の終わりの伏見西坂には、 幡隆上人 の名号碑 が建っていた(右写真)
幡隆上人は、 北アルプスの槍ヶ岳を霊場として開山した浄土宗の僧侶で、「天保年間に伏見宿や近隣の比衣村、中村、小屋敷村を訪れ、「南無阿弥陀仏」と独特の文字を刻んだ名号碑を建立した」といわれる。
宿場の繁栄に貢献したものとしては 新村湊(しんむらみなと) がある。 地元の年貢米や
瑞浪や土岐方面からの荷物の積み出しに使われ、また、伊勢参りに行く客も利用したので、この湊の繁栄振りが、土田宿廃宿後の新たな宿場選定に有利に働いたものと考える(巻末参照)
 正岡子規のかけはしの記には、明治四年(1891)五月、伏見宿に泊まったことが、書かれ
正岡子規のかけはしの記には、明治四年(1891)五月、伏見宿に泊まったことが、書かれ
ている。 その翌日の早朝、この湊に到着する舟を待ち、木曽川駅まで船旅をした様子は、
『 此夜伏見に足をとゞむ。
朝まだほの暗き頃より舟場に至りて下り舟を待つ。つどひ来る諸国の旅人七八人あり。
「 すげ笠の 生国 名のれ ほとときす 」
(以下船旅をした様子が書かれているが省略) 』
出発の際に詠んだ上記の句が、国道の脇に句碑となって建っていた(右写真)
このように繁栄した伏見宿と新村湊も、鉄道輸送の登場、そして、国道建設による陸上輸送により、水運輸送がなくなるとともに衰退していった。
私は、川湊があったと思われる日帰り温泉に入り、汗を流してから、国道を歩いて可児市に入り、
道を変えて
名鉄新可児駅まで歩き、本日の歩きを終えた。
( 温泉に興味のある方は、【八千代温泉】 をクリックください )
( ご 参 考 ) 新村湊(しんむらみなと)
伏見宿の繁栄に貢献した一つに新村湊(しんむらみなと)の存在があった。
宿場から出たあたりを新村というが、江戸時代には木曽川沿いに川湊が置かれた。
木曽川を下ると、伊勢湾に通じていたので、地元の年貢米はもとより瑞浪や土岐方面からの荷物の積み出しに使われた湊である。
文政以降になると、伊勢参りに行く客が増えたが、これらの人もこの湊から船を利用するようになり、明治に入っても、正岡子規なども利用している。
この湊の繁栄振りが、土田宿廃宿後の新たな宿場選定に有利に働いたものと考える。
なお、新村湊を探して歩いたが、場所がどこだったのか分からなかった。
木曽川はここでは川幅が広く、碧緑色をした水をたたえていて、陸と川面もなだらかであるから、船着き場が置きやすい場所だったに違いないと思った。 その先まで上ると、川幅が極端に狭くなっていたので、日帰り温泉があるあたりにあったと思うが間違いだろうか?
( 再 訪 問 )
名鉄顔戸駅から伏見宿
 平成二十三年五月二十五日、名鉄顔戸駅から太田宿に渡る今渡の渡し場跡まで歩いた。
伏見宿の終わりの上恵土交叉点から今渡りの渡し場跡は始めてだが、名鉄顔戸駅から伏見宿の間は七年前に歩いている。
従って、前回と変わっていたところや訪れなかったところを中心に記述する。
顔戸駅から国道に出て、顔戸交叉点を左折して国道を進む。
横浜飯店の反対の右側の高台に祠があったが、そこから少し歩くと正面に東海環状道の高架が見えてきたが、右側に兼山に行く三叉路があり、
住宅地への入口に 「 比衣の一里塚跡 」 「 中山道 」 の碑が建っている (右写真)
平成二十三年五月二十五日、名鉄顔戸駅から太田宿に渡る今渡の渡し場跡まで歩いた。
伏見宿の終わりの上恵土交叉点から今渡りの渡し場跡は始めてだが、名鉄顔戸駅から伏見宿の間は七年前に歩いている。
従って、前回と変わっていたところや訪れなかったところを中心に記述する。
顔戸駅から国道に出て、顔戸交叉点を左折して国道を進む。
横浜飯店の反対の右側の高台に祠があったが、そこから少し歩くと正面に東海環状道の高架が見えてきたが、右側に兼山に行く三叉路があり、
住宅地への入口に 「 比衣の一里塚跡 」 「 中山道 」 の碑が建っている (右写真)
住宅地へ入るが、住宅地は北西に向かって続くが、大きな住宅がある三叉路で左折して、
 東海環状道の高架下をくぐる。
少しいくと小さな川があるので、橋をわたると左手に高倉交叉点の見える三叉路に出る。
そのまま国道に出てもよいが、右にカーブする道を行き、交叉点で左折すると国道に出たが、右側の小高い丘の下に
「 左伏見宿 」 「 右御嶽宿 」 と書かれた石の道標があった (右写真)
東海環状道の高架下をくぐる。
少しいくと小さな川があるので、橋をわたると左手に高倉交叉点の見える三叉路に出る。
そのまま国道に出てもよいが、右にカーブする道を行き、交叉点で左折すると国道に出たが、右側の小高い丘の下に
「 左伏見宿 」 「 右御嶽宿 」 と書かれた石の道標があった (右写真)
前回訪れた時の高倉集落は名鉄八百津線が廃止になった後だったので、
その余韻が残っていたが、それから十年近く経つとそうしたことがあったことが地元でも消えつつあることに気付いた。
国道に入ると御嵩町伏見の陸橋があり、 「 国道21号 」 「 2km兼山→ 」 の道路標識が付いていた。
兼山への三叉路を越えると、道は上り坂になった。
 歩道は右側にしか設置されていないので、右側を上っていくと頂上の左側に見覚えのある伏見公民館が見えた。
なお、左側は坂を上り切ったあたりから、道に歩道を表示する白線が引かれ、歩道は赤茶色で染められていたが、これは最近実施されたものである。
前回、坂を上ったら、左側に突然現れた本陣跡には驚いた記憶がある。
伏見宿本陣跡の碑、「是より東尾州領」と刻まれた領界碑、それから、「中山道伏見宿 日本歴史街道 」 「 東御嵩宿 西太田宿 」 の木の道標は健在だった (右写真)
歩道は右側にしか設置されていないので、右側を上っていくと頂上の左側に見覚えのある伏見公民館が見えた。
なお、左側は坂を上り切ったあたりから、道に歩道を表示する白線が引かれ、歩道は赤茶色で染められていたが、これは最近実施されたものである。
前回、坂を上ったら、左側に突然現れた本陣跡には驚いた記憶がある。
伏見宿本陣跡の碑、「是より東尾州領」と刻まれた領界碑、それから、「中山道伏見宿 日本歴史街道 」 「 東御嵩宿 西太田宿 」 の木の道標は健在だった (右写真)
公民館の前で竹を数本担いた人にあったので聞くと、節電に協力するため、公民館にゴーヤを植えるための添え木とのこと。
御苦労さまです。 東電の原子力発電はこうした
 田舎にも影響しているのである。 その先の伏見交叉点一帯はこの7年間で変わっていた。
前回訪れた時は右手前の家の一角に、右 御嶽、左 兼山八百津 と刻んだ道標があったが、右角は伏見宿一本松公園に替わっていた (右写真)
田舎にも影響しているのである。 その先の伏見交叉点一帯はこの7年間で変わっていた。
前回訪れた時は右手前の家の一角に、右 御嶽、左 兼山八百津 と刻んだ道標があったが、右角は伏見宿一本松公園に替わっていた (右写真)
道標は交叉点の角に移されて、箱庭風の先に休憩所が設けられていた。
前回、目立たないように道標があったので、気になっていたが、この一帯を整備して、中山道を歩く人の小公園にしたのである。
また、休憩所の脇に、 「この道は中山道 可児市1.3km⇔御嵩宿4.8km ここは伏見宿 」 の表示板もあった。
伏見で残っている古い建物で気になっていたのが、交叉点の左二軒目の家だった。
無人のようだったので、取り壊され
 るのではと懸念していたが、 「 中山道伏見宿 お休み処 駱駝 」 の看板があり、
コーヒーの幟も立っていたので、よかったと思った (右写真)
るのではと懸念していたが、 「 中山道伏見宿 お休み処 駱駝 」 の看板があり、
コーヒーの幟も立っていたので、よかったと思った (右写真)
入口に自由にお入りくださいとは書いてあるが、中が覗けないので入りずらい。
もう少し入りやすいような工夫か、説明があるとよいのではないだろうか。
伏見交叉点を左折して進むと、伏見小学校があるが、公民館前にある領界碑は校庭が出来る前はここにあったのである。
その先の右手には洞興禅寺があり、上って右側の子安堂の左側には女郎塚がある。
今回もまた訪れたが、前回訪れなかったのが東寺山古墳である。
 洞興禅寺標柱の反対側、左側の小路に入り、突き当たりを右折すると東寺山古墳と書かれたところに出た。
東寺山古墳は東西に二つの古墳があるが、四世紀末から五世紀初頭に造営されたといわれるもの。
これは二号墳で、別名、伏見寺山西塚古墳といい、全長五十八メートルの前方後方墳である (右写真)
洞興禅寺標柱の反対側、左側の小路に入り、突き当たりを右折すると東寺山古墳と書かれたところに出た。
東寺山古墳は東西に二つの古墳があるが、四世紀末から五世紀初頭に造営されたといわれるもの。
これは二号墳で、別名、伏見寺山西塚古墳といい、全長五十八メートルの前方後方墳である (右写真)
比較的形状は残っているが、周囲に民家が建っているので、全体を見ることはできない。
また、濠などは埋まってしまっている。 なお、前方部の高さは二メートル十センチ、後方部の高さは四メートル五十センチである。
東側にある一号墳は伏見寺山東塚古墳と呼ばれ、全長四十一メートルの前方後円墳である。
墳丘は大きく破壊されていて、一部が
 残っているだけである。 これらの古墳の敷地は本陣の隣にある浄覚寺の所有である。
残っているだけである。 これらの古墳の敷地は本陣の隣にある浄覚寺の所有である。
小学校の方に向かおうとすると、左側に朱色の御堂があり、稲荷神社と書かれていた。
伏見交叉点に戻り、国道を進むと右側に東濃実業高校があり、その先右側には 幡隆上人 の名号碑 が建っていた。
そこは伏見西坂で、下った行くと、 「 左県道122号可児 直進国道21号岐阜美濃加茂 左県道381号八百津 」 の道路標識が現れた (右写真)
右にカーブする道を下ると、その先に上恵土交叉点があった。 ここを右折していくと新村湊跡に行けるが、ここが伏見宿のはずれである。
平成15年12月
平成23年5月(再訪問)
美濃路を行く(8)太田宿へ 旅の目次に戻る

 御嵩駅前まで戻り、旧中山道を京方面に歩く。 右手に願興寺の駐車場、その対面の左手には 秋葉神社 などを合祀した一角があった。
二百メートルくらい先で左へと、枡形に曲がり、更に五百メートルくらいで右へ曲がる。 旧中山道を歩いても、これといった古いものはなかった。
間もなく国道
21号線にぶつかった。 時間にゆとりがあったので、願興寺の仏像を救った僧侶達がいたという 愚渓寺 に足を伸ばすことにした。 国道を横切り、
五百メートルほど坂道を登ると、右手に 御嵩小学校 がある。 その奥に愚渓寺があった (右写真)
御嵩駅前まで戻り、旧中山道を京方面に歩く。 右手に願興寺の駐車場、その対面の左手には 秋葉神社 などを合祀した一角があった。
二百メートルくらい先で左へと、枡形に曲がり、更に五百メートルくらいで右へ曲がる。 旧中山道を歩いても、これといった古いものはなかった。
間もなく国道
21号線にぶつかった。 時間にゆとりがあったので、願興寺の仏像を救った僧侶達がいたという 愚渓寺 に足を伸ばすことにした。 国道を横切り、
五百メートルほど坂道を登ると、右手に 御嵩小学校 がある。 その奥に愚渓寺があった (右写真) 「 大智山愚渓寺といい、臨済宗妙心寺派の寺院で,妙心寺第五世義天玄承禅師(ぎしょうげんしょうぜんじ)が
応永三十四年(1427)、当地鈴ヶ洞に創建した寺である。
「 大智山愚渓寺といい、臨済宗妙心寺派の寺院で,妙心寺第五世義天玄承禅師(ぎしょうげんしょうぜんじ)が
応永三十四年(1427)、当地鈴ヶ洞に創建した寺である。  ていた。 山額には、 古禅林 と書かれているが、 朝鮮国花庵 の筆で、将軍就任の慶賀使として来日した際に揮毫したものである。
大方丈の前にある石庭は、京都・竜安寺石庭の原形ともいわれるものである。 真白な砂に波紋と直線が織りなす造形、岩をさりげなく配する絶妙なバランス。
まさに見事の一言につきた (右の上下二つの写真)
ていた。 山額には、 古禅林 と書かれているが、 朝鮮国花庵 の筆で、将軍就任の慶賀使として来日した際に揮毫したものである。
大方丈の前にある石庭は、京都・竜安寺石庭の原形ともいわれるものである。 真白な砂に波紋と直線が織りなす造形、岩をさりげなく配する絶妙なバランス。
まさに見事の一言につきた (右の上下二つの写真) 少し歩くと、右側に、鬼の首塚があり、脇の石碑には、 関ノ太郎 の名が彫られていた。 鬼の首塚は、塚という程の高さはなく、社も質素である (右写真)
少し歩くと、右側に、鬼の首塚があり、脇の石碑には、 関ノ太郎 の名が彫られていた。 鬼の首塚は、塚という程の高さはなく、社も質素である (右写真)
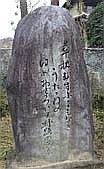 歴史上で鬼とされたものには、政府に逆らう反逆者や反体制者を支配者(政府側)が鬼に
歴史上で鬼とされたものには、政府に逆らう反逆者や反体制者を支配者(政府側)が鬼に を醒まされたという、夕立に驚く様と夢路を妨げた恨みを少し込めた句であろう。
を醒まされたという、夕立に驚く様と夢路を妨げた恨みを少し込めた句であろう。 ここから少し入ったところに名鉄広見線の顔戸駅があり、その近くに 在原行平の石碑 がある。
「 在原行平は、百人一首で有名な在原業平の兄で中納言で、歌人としても知られた。 碑は、美濃国の国司だった徳を偲んで、寛保三年(1743)に建てられた
もの。 」 とあったが、何故、江戸時代になって碑が建てられたのか?、疑問が残った。
空が時雨れてきて、ぱらぱらと服装を濡らしはじめた。
その先、右に行く道があるところが比衣である。 角に 比衣の一里塚跡 の石碑があった。
石碑がなければ、分からなかっただろう (右写真)
ここから少し入ったところに名鉄広見線の顔戸駅があり、その近くに 在原行平の石碑 がある。
「 在原行平は、百人一首で有名な在原業平の兄で中納言で、歌人としても知られた。 碑は、美濃国の国司だった徳を偲んで、寛保三年(1743)に建てられた
もの。 」 とあったが、何故、江戸時代になって碑が建てられたのか?、疑問が残った。
空が時雨れてきて、ぱらぱらと服装を濡らしはじめた。
その先、右に行く道があるところが比衣である。 角に 比衣の一里塚跡 の石碑があった。
石碑がなければ、分からなかっただろう (右写真) 竹林の脇を通りぬけて、住宅が多くあるところを抜けると、また、国道に合流した。
竹林の脇を通りぬけて、住宅が多くあるところを抜けると、また、国道に合流した。  伏見宿は、廃線になった名鉄八百津線の線路のあたりの高倉集落あたりからである。
伏見宿は、廃線になった名鉄八百津線の線路のあたりの高倉集落あたりからである。  御嵩宿は木曾方面への旅に備えて宿泊という客であったのに対し、伏見宿は遊べるところ
御嵩宿は木曾方面への旅に備えて宿泊という客であったのに対し、伏見宿は遊べるところ い。 少し歩くと、伏見の交差点で、右手前の家の一角に、道標があった (右写真)
い。 少し歩くと、伏見の交差点で、右手前の家の一角に、道標があった (右写真) 卯建や連子格子を持つ黒塗りの建物である。
卯建や連子格子を持つ黒塗りの建物である。  手前に、真宗大谷派竹山浄覺寺という寺があった (右写真)
手前に、真宗大谷派竹山浄覺寺という寺があった (右写真) ① 旅籠は御嵩などにくらべ貧弱だったが、女が多く、飯盛り女や女郎を売り物にしていたので、それを目的にきた人で賑わっていた。
① 旅籠は御嵩などにくらべ貧弱だったが、女が多く、飯盛り女や女郎を売り物にしていたので、それを目的にきた人で賑わっていた。 校庭の中に、江戸時代のものがないか覗いたが、なかった。
校庭の中に、江戸時代のものがないか覗いたが、なかった。  と、いうようなことがながながと石碑に書かれていた。
と、いうようなことがながながと石碑に書かれていた。 国道に戻り、先に進むと右側に東濃実業高校がある。
国道に戻り、先に進むと右側に東濃実業高校がある。  正岡子規のかけはしの記には、明治四年(1891)五月、伏見宿に泊まったことが、書かれ
正岡子規のかけはしの記には、明治四年(1891)五月、伏見宿に泊まったことが、書かれ 平成二十三年五月二十五日、名鉄顔戸駅から太田宿に渡る今渡の渡し場跡まで歩いた。
伏見宿の終わりの上恵土交叉点から今渡りの渡し場跡は始めてだが、名鉄顔戸駅から伏見宿の間は七年前に歩いている。
従って、前回と変わっていたところや訪れなかったところを中心に記述する。
顔戸駅から国道に出て、顔戸交叉点を左折して国道を進む。
横浜飯店の反対の右側の高台に祠があったが、そこから少し歩くと正面に東海環状道の高架が見えてきたが、右側に兼山に行く三叉路があり、
住宅地への入口に 「 比衣の一里塚跡 」 「 中山道 」 の碑が建っている (右写真)
平成二十三年五月二十五日、名鉄顔戸駅から太田宿に渡る今渡の渡し場跡まで歩いた。
伏見宿の終わりの上恵土交叉点から今渡りの渡し場跡は始めてだが、名鉄顔戸駅から伏見宿の間は七年前に歩いている。
従って、前回と変わっていたところや訪れなかったところを中心に記述する。
顔戸駅から国道に出て、顔戸交叉点を左折して国道を進む。
横浜飯店の反対の右側の高台に祠があったが、そこから少し歩くと正面に東海環状道の高架が見えてきたが、右側に兼山に行く三叉路があり、
住宅地への入口に 「 比衣の一里塚跡 」 「 中山道 」 の碑が建っている (右写真) 東海環状道の高架下をくぐる。
少しいくと小さな川があるので、橋をわたると左手に高倉交叉点の見える三叉路に出る。
そのまま国道に出てもよいが、右にカーブする道を行き、交叉点で左折すると国道に出たが、右側の小高い丘の下に
「 左伏見宿 」 「 右御嶽宿 」 と書かれた石の道標があった (右写真)
東海環状道の高架下をくぐる。
少しいくと小さな川があるので、橋をわたると左手に高倉交叉点の見える三叉路に出る。
そのまま国道に出てもよいが、右にカーブする道を行き、交叉点で左折すると国道に出たが、右側の小高い丘の下に
「 左伏見宿 」 「 右御嶽宿 」 と書かれた石の道標があった (右写真) 歩道は右側にしか設置されていないので、右側を上っていくと頂上の左側に見覚えのある伏見公民館が見えた。
なお、左側は坂を上り切ったあたりから、道に歩道を表示する白線が引かれ、歩道は赤茶色で染められていたが、これは最近実施されたものである。
前回、坂を上ったら、左側に突然現れた本陣跡には驚いた記憶がある。
伏見宿本陣跡の碑、「是より東尾州領」と刻まれた領界碑、それから、「中山道伏見宿 日本歴史街道 」 「 東御嵩宿 西太田宿 」 の木の道標は健在だった (右写真)
歩道は右側にしか設置されていないので、右側を上っていくと頂上の左側に見覚えのある伏見公民館が見えた。
なお、左側は坂を上り切ったあたりから、道に歩道を表示する白線が引かれ、歩道は赤茶色で染められていたが、これは最近実施されたものである。
前回、坂を上ったら、左側に突然現れた本陣跡には驚いた記憶がある。
伏見宿本陣跡の碑、「是より東尾州領」と刻まれた領界碑、それから、「中山道伏見宿 日本歴史街道 」 「 東御嵩宿 西太田宿 」 の木の道標は健在だった (右写真) 田舎にも影響しているのである。 その先の伏見交叉点一帯はこの7年間で変わっていた。
前回訪れた時は右手前の家の一角に、右 御嶽、左 兼山八百津 と刻んだ道標があったが、右角は伏見宿一本松公園に替わっていた (右写真)
田舎にも影響しているのである。 その先の伏見交叉点一帯はこの7年間で変わっていた。
前回訪れた時は右手前の家の一角に、右 御嶽、左 兼山八百津 と刻んだ道標があったが、右角は伏見宿一本松公園に替わっていた (右写真) るのではと懸念していたが、 「 中山道伏見宿 お休み処 駱駝 」 の看板があり、
コーヒーの幟も立っていたので、よかったと思った (右写真)
るのではと懸念していたが、 「 中山道伏見宿 お休み処 駱駝 」 の看板があり、
コーヒーの幟も立っていたので、よかったと思った (右写真) 洞興禅寺標柱の反対側、左側の小路に入り、突き当たりを右折すると東寺山古墳と書かれたところに出た。
東寺山古墳は東西に二つの古墳があるが、四世紀末から五世紀初頭に造営されたといわれるもの。
これは二号墳で、別名、伏見寺山西塚古墳といい、全長五十八メートルの前方後方墳である (右写真)
洞興禅寺標柱の反対側、左側の小路に入り、突き当たりを右折すると東寺山古墳と書かれたところに出た。
東寺山古墳は東西に二つの古墳があるが、四世紀末から五世紀初頭に造営されたといわれるもの。
これは二号墳で、別名、伏見寺山西塚古墳といい、全長五十八メートルの前方後方墳である (右写真) 残っているだけである。 これらの古墳の敷地は本陣の隣にある浄覚寺の所有である。
残っているだけである。 これらの古墳の敷地は本陣の隣にある浄覚寺の所有である。