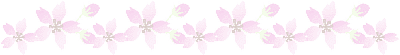
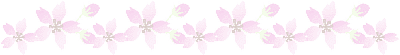
貴方は 目のゲストです!!
目のゲストです!!
写真をクリックすると、画面が大きくなります。
円山公園の桜
円山公園には、ソメイヨシノ、山桜、八重桜、しだれ桜などがあり、市内随一の桜の
名所として知られています。 中でも、公園中央にあるしだれ桜は一重白ヒガン枝垂桜
という品種で、祇園の夜桜として有名です。 初代の樹齢二百年の桜は昭和22年に
枯死してしまったが、桜守の佐野さんがその子の苗を昭和24年に元の位置に移植した。
現在の桜は二代目で、樹齢八十年を越えた。 夜間にライトアップされると、昼と違う
妖艶さが現れて、この桜の別の面を見ることができます。
|
|
|
|
|
|
円山公園の枝垂桜 |
| 円山公園の枝垂桜 |
| ライトアップ時の桜 |
二条城の桜
二条城は徳川家康が慶長八年(1603)に京の宿舎として築いた平城です。 城内
にはソメイヨシノ、イトザクラ、ヤマザクラ、シダレサクラが植えられています。
清流園には多くのシダレザクラが植えられていて、2022年には夜間の桜が紹介された。
上京・中京地区
二条城の南に神泉苑があり、池の中には雨乞い伝説の竜神が祀られている。
京都御所の近衛家には、室町時代、糸桜が植えられ、桜の御所と呼ばれていたという。
今でも、白や紅色などのしだれ桜が数十本植えられていて、3月下旬から楽しめます。
枝垂れ桜の阿亀の桜は千本釈迦堂の境内にある。 本堂を建設した棟梁が柱の寸法を
間違えたが、妻・阿亀(おかめ)の助言で、無事完成させた。 完成後、阿亀はその事実
を隠すため、自害した。 そうした阿亀を偲んで、後日付けられたのが阿亀桜です。
|
|
|
|
|
|
|
|
神泉苑 |
| 近衛家跡の糸桜 |
| 近衛家の枝垂桜 |
| 阿亀桜 (千本釈迦堂) |
東山地区
白川南通り新橋通りにかけては祇園新橋伝統的建造物保存地区に指定されています。
かっては御茶屋が建ち並んだところで、風情ある町並みが保存されています。
巽橋の近くの辰巳大明神は芸事の神様として祇園の芸者や舞妓の信仰を集めてます。
祇園の雰囲気が残る風景と川沿いのしだれ桜の組み合わせは絵になるでしょう。
|
|
|
|
|
|
|
|
祇園白川の桜 |
| 白川のしだれさくら |
| 辰巳大明神 |
| 巽橋界隈 |
知恩院は法然が住み没した地に建立された、浄土宗の総本山です。
三門(山門)は江戸幕府二代将軍秀忠に完成したが、焼失し、三代将軍家光の
時代の寛永十八年(1641)頃に完成したものです。 門前に桜が咲いていた。
勅使門の唐門も寛永十八年(1641)に建立された。 桜は落花しぎりでした。
知恩院前に咲く桜の車道を人力車が通り過ぎて行ったが、風情があった。
高台寺は、秀吉の正室・ねねが秀吉の冥福を祈るため建立した寺です。
境内の庭園に一本のしだれ桜があり、咲いた花は可憐で美しいです。
|
|
|
|
|
|
|
|
知恩院三門 |
| 知恩院唐門 |
| 人力車が行く |
| 高台寺のしだれ桜 |
北区・右京区
平野神社は平安遷都に伴い、奈良から遷座された神社で、二十二社の上七社の一つです。
桜を神紋とし、境内に六十種類、四百本の桜が植えられていて、有料で見学できます。
江戸時代から「平野の夜桜」として庶民に開放されたといわれます。 本殿は「平野造り」
と呼ばれる独特の造りで、国の重要文化財に指定されています。
|
|
|
|
|
|
|
|
平野神社の桜 |
| 平野神社の桜 |
| 平野神社の桜 |
| 平野神社の桜 |
御室のおたふく桜は、仁和寺の境内に咲いています。 仁和寺は宇多天皇の創建した寺
で、法親王が住侍していることから、御室御所と呼ばれたようです。 おたふく桜は境内
に約200本あるようです。 遅咲きの桜で、一斉に咲くと波のように広がって美しい。
原谷苑は桜守が所有する敷地四千坪の桜園で、シーズンだけ有料で公開しています。
樹齢五十年を越えたしだれ桜が百本ある他、ソメイヨシノ、みどり桜、御室桜などの桜
が植えられていて、その景観は圧巻です。
伏見区・山科区
醍醐寺は羽柴秀吉が秀頼、北政所、淀君を始め、多くの女房衆を招き、醍醐の花見を
行ったところで、しだれ桜やソメイヨシノ、山桜、八重桜など、1000本の桜があります。
霊宝館前の桜馬場の桜並木のソメイヨシノは見事に花を咲かしますが、花見客が多く、
ゆっくり鑑賞することができません。 霊宝館の敷地には大きなしだれ桜が数本あります。
その中でも大きなしだれ桜は樹齢百八十年で、醍醐大しだれ桜と呼ばれ、東西24m、
南北20mの大きさでしたが、2018年の台風で被害を受け、やや小さくなりました。
|
|
|
|
|
|
桜馬場の桜並木 |
| 霊宝館付近のしだれ桜 |
| 醍醐寺大しだれ桜 |
勧修寺(かじゅうじ)は醍醐天皇が開基した真言宗山階派の大本山です。
皇室とゆかりが深い門跡寺院ですが、元和二年、徳川家の寄進で現在の規模
になりました。 宸殿や書院は明正天皇の旧殿を移築したものです。 氷室池
は平安時代の優雅な庭で、桜、藤、杜若、花菖蒲などが季節になると咲きます。
随心院は小野小町が宮中を退いた後、晩年まで居住した所と伝えられています。
卒塔婆小町像や文塚、小町の化粧井戸があります。 夕日に桜が輝いてました。
桜で知られる毘沙門堂は七福神の一つ毘沙門天を本尊とする天台宗の門跡寺院です。
仁王門をくぐると本堂・宸殿・霊殿などがあるが、その前に樹齢百五十年の桜がある。
山科疏水の両側の道は約三キロの散策路となっていて、春は桜、秋は紅葉が楽しめます。
四ノ宮から日ノ岡までの疏水沿いに山桜を中心とした桜並木があり、散策によい。
|
|
|
|
|
|
|
|
毘沙門堂のしだれ桜 |
| 毘沙門堂のしだれ桜 |
| 山科疏水の桜 |
| 山科疏水の桜 |
写真集「兵庫・天の橋立高知の桜」へ

目のゲストです!!