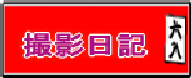

平成19年12月24日
名古屋駅のイルミネーション

神戸市で行われているイルミネーションはすごいと聞くので、一度訪れたいと思うが、実現していない。 名古屋では、
名古屋駅前のイルミネーションが一番である。 高島屋が名古屋駅にオープンしたのを機に始まったもので、最初はす
ごかったが、ここ数年はお金をかけないせいか、地味でぱっとしなかった。 今年はよいらしいよ!!、と家内がいう。
時期によってバージョンが違うようという。 どうせなら、クリスマスバージョンがよいなと思い、クリスマスイブに
出かけた。 たしかにここ数年のものにくらべ、派手になり、動きも豊富だった。 1時間に数回、画面にサンタクロースが
現われるようになっていて、家の玄関から出たり入ったり、二人になったり、空にそりでとんだりと、おもしろい。
とにかく、今年のはよかった。

平成19年11月28日
奉 納

11月19日、小田原から箱根関所まで歩いた。 年初から東海道を行けるところから、順不動に歩き、大磯から三島、
富士市から蒲原と草津から京都が残った。 雪が降る前にと思い、天下の険を登る。 小田原の宿を過ぎてまもなくのところ
に、板橋の地蔵堂がある。 身の丈一丈という大きなもので、胎内に弘法大師ゆかりの仏像が納められているという。
江戸時代には、目の前を東海道が通っていたので、多くの旅人が立ち寄ったことだろう。
本堂の中を覗いたら、納め札が目に付きそれを眺めて、上をみると、天井にいろいろな模様のようなものが描かれていた。
よく見ると家紋のように見えるので、奉納したもののように思えた。
一般的には、牡丹や藤や菊というようなものが描かれているので、インパクトがあった。

平成19年11月22日
諏訪大社

諏訪大社は不思議な神社である。 全国にある諏訪神社の総本山であるが、茅野市の諏訪神社前宮、諏訪市の諏訪神社上社本宮、そして、下諏訪町の諏訪神社下社春宮と同秋宮、これらの4つの神社を併せて、諏訪神社(戦前は諏訪大社)というのである。 神主は4つの神社に1人しかいないのであり、それでは困るのでは思ったが、神職が何人もいるので、問題はないようである。
これまで、そうとは知らず、幾つかの神社に訪れていたが、
平成19年11月8日(木)、4つの神社に御参りをした。 こうした人は珍しいと見て、朱印をいただいた家内に落雁をいただいた。 その中で、印象に残ったのが、前宮である。 この社には、古い時代の名残りが残るとともに、秋の紅葉がきれいだった (右写真)
創建の時期ははっきりしないが、古事記などにある大国主命が国を譲るのに反対した長男の神が諏訪に来て、この地を治め、祀られたのが起源である、とある。 その末裔が神社の大祝(神主)であると同時に、諏訪氏としてこの地の領主であったが、戦国時代の到来の頃、神社の管理者と領地の管理者が分離したようで、武田信玄が滅ぼした諏訪氏はその末裔であった訳である。

平成19年11月21日
川中島

11月6日(火)、山本勘助が亡くなったといわれる長野市の川中島を訪れた。 NHKの大河ドラマの「風林火山」に武田信玄に仕えた軍司として登場するが、彼は上杉謙信に策が読まれて、挟み撃ちに逢い、ここで亡くなったといわれる。 但し、『甲陽軍鑑』などの登場する勘助は実在の人物ではないというのが定説のようだが・・・・
川中島とあるので、川の縁にあると信じていたが、3つの川に囲まれた葦の茂った平地であった。 そこには博物館があり、特別展が開催されていたが、それより常設展の方が面白かった。
博物館の前の木々には秋が到来していて、霧に一部包まれた風情は大変よかった。

平成19年10月13日
紀州一周ドライブ

10月9日〜11日の2泊3日で、紀州を一周する計画で、ドライブしてきた。 メーターを見ると、700kmを越える距離を走ったことになるが、高速道路もかなりでき、国道も整備されていたので、一人で走りきることができた。 天気の神がついているという娘の神力も妻の雨女には負けたようで、やや雨交じりの天候だったので、潮岬と白浜は行くのをやめた。
もともと、熊野三山への詣でが目的だったので、時間がゆったりとれたので、かえってよかったような気がする。 那智大社に到着して当時は霧で視界が悪かったが、帰るときには少し霧が晴れ、写真がなんとが撮れた。

平成19年08月23日
狛 犬

旧盆の8月15日に郷里で十年振りの高校の同窓会があり、両親の墓詣りを兼ねて参加した。 翌日、日本橋から品川宿まで歩いたが、東京では珍しい35℃という猛暑に見舞われ、死ぬかと思うほど熱く、水をいくら飲んでも追いつかない状態だった。
それでも多くの会社が休んでいることから、第一京浜を走る車が少なく、そこから発生する排気ガスで苦しめられなかったので、助かった。
江戸時代の品川宿は北品川商店街と南品川商店街に代わってしまい、戦災で古いものは一つも残っていなかったが、歴史に残る史跡を訪ねて歩きまわった。
その一つの品川神社には備前焼の狛犬があった。 これは珍しい。
また、石製の狛犬だが、雌犬に2匹の子犬がまつわりついているのがあった(右写真)
これまでに1匹のは見たが2匹ははじめてである。

平成19年08月06日
丁子屋

5月22日に東海道の鞠子宿(丸子宿)を訪れ、元禄元年創業といわれる丁子屋に行ったが、開業時間の30分前だったので入れなかった。
弥次喜多のコンビが登場する東海道五十三次膝栗毛では、二人は茶屋の夫婦の喧嘩を仲裁している。 江戸時代の中期には、この宿の名物のとろろ汁はすでに有名になっていてようである。
また、浮世絵の鞠子宿にも梅の花と茶屋が描かれている。
名物にうまいものなしというが、確かめないと遺憾と思うし、とろろは好物なので、7月31日に再度、訪れた。
自然薯なので、かなり粘りがあると思っていたが、予想に反しあっさりしたものだった。
店の前は朱毛氈を敷いた縁台があり、右側には江戸時代の浮世絵がペンキで描かれていた。

平成19年06月18日
稚児橋

6月2日には江尻宿から府中宿まで東海道を歩いた。
江尻宿とは旧清水市、府中宿は旧静岡市、現在は静岡市清水区と葵区になっている。
江尻宿の終わりのところに江戸時代の慶長十二年(1607)に橋が架けられ稚児橋といった。
現在の橋は最近のものであるが、橋の四隅に河童の像そして橋の真ん中にはレリーフがある。
表情やポーズが違いなかなか可愛いものだった。
橋の渡り初めの日に老人夫婦が橋を渡ろうとすると、川の中から童子が現れ、橋脚を登ると入江方向に消え去ったことから、稚児橋に名前を変わた、といい、前述の童子は巴川に住む河童だったという話が残る。 江戸時代になって河童が登場する話はあわりないのではないだろうか?

平成19年06月05日
茶畑ばかり

5月22日に金谷から掛川まで東海道を歩いたが、この区間はお茶、お茶の畑が続いていた。
このあたりは山ではあるが、低いのでイメージ的には山という感じはしない。 高いのは880mあり、大井川鉄道に沿って延びているので、丘というイメージでもないが、金谷から菊川そして相良にかけては丘陵地帯なのだろう。
この地区でお茶が栽培されたのは明治以降というから、京都の宇治などと比べると歴史が浅い。
明治維新で職を失った幕府の役人によるとか、東海道の廃止による大井川の川越人足による開拓であるが、どちらにせよ、明治の変動期にスタートしたことに間違いない。
かっては、大量生産の静岡産の茶は京都と東京に送られ、各地のお茶がブレンドされて販売されていたが、最近の産地表示の義務付けで静岡県内での産地間の差別化が進みつつあるようである。
また、深蒸など焙煎のしかたにも工夫され、静岡を歩いていると
掛川茶、金谷茶、袋井茶、川根茶など産地の名をつけてPR合戦をしていたが、どう違うのか分らなかった。

平成19年06月1日
明治のトンネル

10日ほど前になるが、静岡県の中央部にある小夜の中山を越えた。
平安時代には蔦の小道として有名でいろいろの人が作品を残している。
江戸時代の東海道は別に作られたようで、小生はその道を歩いたわけだが、この道はがけ崩れなどでかなりの部分が変えられている。 そこで出遭ったのが明治のトンネルである (右写真)
ここは大正のトンネル、昭和のトンネルもあり、この2つは現役である。
明治九年に長さ223mのくの字形のトンネルを作ったが、このトンネルは有料で、通るのに人は五厘、荷馬は一銭二厘、人力車は一銭五厘かかったという。 明治天皇の行啓に使用されたのでそれを示す記念碑があった。 最初のトンネルは木枠で作られていたので、照明用のカンテラの失火で枠組が焼失し、明治三十七年、小生が見た赤煉瓦のトンネルになった。

平成19年05月14日
新茶の季節

5月に入り、西で残っていた鈴鹿越えを終えようと、11日(金)に関駅から伊勢坂下までバスで行き、そこから歩いた。
鈴鹿峠は標高500m程度であるが、東海道では箱根越えと並ぶ難所といわれてきた。
伊勢坂下からは2.5kmしかなかったこともあり、急坂ではなんなく突破とあいなった。
それよりは下りの土山宿までのだらだら下る道が長かった。
それを癒してくれたのがあたり一面の茶畑である。 今が一番茶の時期で葉の色も淡かった。
土山の道の駅で妻への御土産に新茶を買ったが、50gで1050円もした。

平成19年04月30日
さった峠で見た富士山

大型連休に入った4月29日、夜明けとともに起きて鈍行に乗って蒲原へ。
蒲原から由比へ歩き、由比では今の季節に取れるさくら海老がフルコースのさくら御膳を食べた。
それから東海道の難所の一つといわれたさった峠を越そうと歩き始めた。
歩くに比例して駿河湾が立体的になり、見える視野も広くなっていった。
しばし歩いた後振り返った先に見えたのが雲一つない富士山とその前に横たわる駿河湾。
そして下には、高速道路、国道1号線、新幹線と東海道線が平行して走るのが見えた。
朝早く起きるのはつらいが、こうしたご褒美がもらえるのなら、いいですね!!
大いに景色を満悦した1日だった。

平成19年04月03日
予期せず桜が見られた

東海道のひとり旅を続けていて、先月までに愛知県と三重県を終えたので、現在は静岡県を歩いている。
去る3月28日、掛川宿から袋井宿を歩いたが、途中掛川城に立ち寄った。
豊臣秀吉より山内一豊が拝領した城だが、昨年の大河ドラマで、千代の内助の功で得られた城
と放送され、昨年はブームに乗り多くの人が訪れたようである。
小生も、どのような城か興味があったので寄ったのだが、思いもかけず桜を見ることができた。
しだれ桜越しにみる掛川城は勇壮でよかった。
一豊と千代が天守閣から眺めた風景はどのようなものだったのだろうか?

平成19年03月24日
時移ろうて

時がたつのは早い。
冬と思っていたが、気がつくともう彼岸過ぎ。
今年は暖かだったので、季節感が感じられなかったのに、3月に入り寒くなった。
気象庁も桜の開花予想が大きく狂わされて迷走状態。
花の方もこの暖冬で、例年とは違い一斉に花を咲かせている。
先週の日曜日、三重県亀山市郊外にある、鎌倉幕府の勅願寺の石上寺に行った。
和泉式部が参籠したと伝えられる寺の境内で、ちょうど見ごろのこぶしに出逢った。

平成19年01月23日
ロウバイ

今年は暖冬である。
暮から正月にかけて寒い日があったが、その他は平年より暖かい。
個人的にはその方が楽でよいが、商売を営んでいる人には影響がでしょうだ。
冬物バーゲンは始まっていても、行こうという気にはなれないだろう。
昨年は異常な寒さだったので、冬物が飛ぶように売れたが、今年はストックの山ということにならなければよいが・・・・
花もその影響で、ロウバイは12月の終わりに咲き、もう満開である。
このままだと、1月一杯で終わるという感じだ。

最新の日記帳に戻る

 神戸市で行われているイルミネーションはすごいと聞くので、一度訪れたいと思うが、実現していない。 名古屋では、
名古屋駅前のイルミネーションが一番である。 高島屋が名古屋駅にオープンしたのを機に始まったもので、最初はす
ごかったが、ここ数年はお金をかけないせいか、地味でぱっとしなかった。 今年はよいらしいよ!!、と家内がいう。
時期によってバージョンが違うようという。 どうせなら、クリスマスバージョンがよいなと思い、クリスマスイブに
出かけた。 たしかにここ数年のものにくらべ、派手になり、動きも豊富だった。 1時間に数回、画面にサンタクロースが
現われるようになっていて、家の玄関から出たり入ったり、二人になったり、空にそりでとんだりと、おもしろい。
とにかく、今年のはよかった。
神戸市で行われているイルミネーションはすごいと聞くので、一度訪れたいと思うが、実現していない。 名古屋では、
名古屋駅前のイルミネーションが一番である。 高島屋が名古屋駅にオープンしたのを機に始まったもので、最初はす
ごかったが、ここ数年はお金をかけないせいか、地味でぱっとしなかった。 今年はよいらしいよ!!、と家内がいう。
時期によってバージョンが違うようという。 どうせなら、クリスマスバージョンがよいなと思い、クリスマスイブに
出かけた。 たしかにここ数年のものにくらべ、派手になり、動きも豊富だった。 1時間に数回、画面にサンタクロースが
現われるようになっていて、家の玄関から出たり入ったり、二人になったり、空にそりでとんだりと、おもしろい。
とにかく、今年のはよかった。 11月19日、小田原から箱根関所まで歩いた。 年初から東海道を行けるところから、順不動に歩き、大磯から三島、
富士市から蒲原と草津から京都が残った。 雪が降る前にと思い、天下の険を登る。 小田原の宿を過ぎてまもなくのところ
に、板橋の地蔵堂がある。 身の丈一丈という大きなもので、胎内に弘法大師ゆかりの仏像が納められているという。
江戸時代には、目の前を東海道が通っていたので、多くの旅人が立ち寄ったことだろう。
11月19日、小田原から箱根関所まで歩いた。 年初から東海道を行けるところから、順不動に歩き、大磯から三島、
富士市から蒲原と草津から京都が残った。 雪が降る前にと思い、天下の険を登る。 小田原の宿を過ぎてまもなくのところ
に、板橋の地蔵堂がある。 身の丈一丈という大きなもので、胎内に弘法大師ゆかりの仏像が納められているという。
江戸時代には、目の前を東海道が通っていたので、多くの旅人が立ち寄ったことだろう。  諏訪大社は不思議な神社である。 全国にある諏訪神社の総本山であるが、茅野市の諏訪神社前宮、諏訪市の諏訪神社上社本宮、そして、下諏訪町の諏訪神社下社春宮と同秋宮、これらの4つの神社を併せて、諏訪神社(戦前は諏訪大社)というのである。 神主は4つの神社に1人しかいないのであり、それでは困るのでは思ったが、神職が何人もいるので、問題はないようである。
これまで、そうとは知らず、幾つかの神社に訪れていたが、
平成19年11月8日(木)、4つの神社に御参りをした。 こうした人は珍しいと見て、朱印をいただいた家内に落雁をいただいた。 その中で、印象に残ったのが、前宮である。 この社には、古い時代の名残りが残るとともに、秋の紅葉がきれいだった (右写真)
諏訪大社は不思議な神社である。 全国にある諏訪神社の総本山であるが、茅野市の諏訪神社前宮、諏訪市の諏訪神社上社本宮、そして、下諏訪町の諏訪神社下社春宮と同秋宮、これらの4つの神社を併せて、諏訪神社(戦前は諏訪大社)というのである。 神主は4つの神社に1人しかいないのであり、それでは困るのでは思ったが、神職が何人もいるので、問題はないようである。
これまで、そうとは知らず、幾つかの神社に訪れていたが、
平成19年11月8日(木)、4つの神社に御参りをした。 こうした人は珍しいと見て、朱印をいただいた家内に落雁をいただいた。 その中で、印象に残ったのが、前宮である。 この社には、古い時代の名残りが残るとともに、秋の紅葉がきれいだった (右写真) 11月6日(火)、山本勘助が亡くなったといわれる長野市の川中島を訪れた。 NHKの大河ドラマの「風林火山」に武田信玄に仕えた軍司として登場するが、彼は上杉謙信に策が読まれて、挟み撃ちに逢い、ここで亡くなったといわれる。 但し、『甲陽軍鑑』などの登場する勘助は実在の人物ではないというのが定説のようだが・・・・
11月6日(火)、山本勘助が亡くなったといわれる長野市の川中島を訪れた。 NHKの大河ドラマの「風林火山」に武田信玄に仕えた軍司として登場するが、彼は上杉謙信に策が読まれて、挟み撃ちに逢い、ここで亡くなったといわれる。 但し、『甲陽軍鑑』などの登場する勘助は実在の人物ではないというのが定説のようだが・・・・  10月9日〜11日の2泊3日で、紀州を一周する計画で、ドライブしてきた。 メーターを見ると、700kmを越える距離を走ったことになるが、高速道路もかなりでき、国道も整備されていたので、一人で走りきることができた。 天気の神がついているという娘の神力も妻の雨女には負けたようで、やや雨交じりの天候だったので、潮岬と白浜は行くのをやめた。
10月9日〜11日の2泊3日で、紀州を一周する計画で、ドライブしてきた。 メーターを見ると、700kmを越える距離を走ったことになるが、高速道路もかなりでき、国道も整備されていたので、一人で走りきることができた。 天気の神がついているという娘の神力も妻の雨女には負けたようで、やや雨交じりの天候だったので、潮岬と白浜は行くのをやめた。 旧盆の8月15日に郷里で十年振りの高校の同窓会があり、両親の墓詣りを兼ねて参加した。 翌日、日本橋から品川宿まで歩いたが、東京では珍しい35℃という猛暑に見舞われ、死ぬかと思うほど熱く、水をいくら飲んでも追いつかない状態だった。
それでも多くの会社が休んでいることから、第一京浜を走る車が少なく、そこから発生する排気ガスで苦しめられなかったので、助かった。
旧盆の8月15日に郷里で十年振りの高校の同窓会があり、両親の墓詣りを兼ねて参加した。 翌日、日本橋から品川宿まで歩いたが、東京では珍しい35℃という猛暑に見舞われ、死ぬかと思うほど熱く、水をいくら飲んでも追いつかない状態だった。
それでも多くの会社が休んでいることから、第一京浜を走る車が少なく、そこから発生する排気ガスで苦しめられなかったので、助かった。  5月22日に東海道の鞠子宿(丸子宿)を訪れ、元禄元年創業といわれる丁子屋に行ったが、開業時間の30分前だったので入れなかった。
5月22日に東海道の鞠子宿(丸子宿)を訪れ、元禄元年創業といわれる丁子屋に行ったが、開業時間の30分前だったので入れなかった。  6月2日には江尻宿から府中宿まで東海道を歩いた。
6月2日には江尻宿から府中宿まで東海道を歩いた。  5月22日に金谷から掛川まで東海道を歩いたが、この区間はお茶、お茶の畑が続いていた。
5月22日に金谷から掛川まで東海道を歩いたが、この区間はお茶、お茶の畑が続いていた。  10日ほど前になるが、静岡県の中央部にある小夜の中山を越えた。
10日ほど前になるが、静岡県の中央部にある小夜の中山を越えた。  5月に入り、西で残っていた鈴鹿越えを終えようと、11日(金)に関駅から伊勢坂下までバスで行き、そこから歩いた。
5月に入り、西で残っていた鈴鹿越えを終えようと、11日(金)に関駅から伊勢坂下までバスで行き、そこから歩いた。  大型連休に入った4月29日、夜明けとともに起きて鈍行に乗って蒲原へ。
大型連休に入った4月29日、夜明けとともに起きて鈍行に乗って蒲原へ。  東海道のひとり旅を続けていて、先月までに愛知県と三重県を終えたので、現在は静岡県を歩いている。
東海道のひとり旅を続けていて、先月までに愛知県と三重県を終えたので、現在は静岡県を歩いている。  時がたつのは早い。
時がたつのは早い。 今年は暖冬である。
今年は暖冬である。