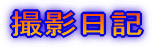
( Photo Diary )

2011年8月28日
秋葉神社の天狗

秋葉神社は山の上の秋葉神社上社と麓の秋葉神社下社と二つあり、
それらは五十丁といわれる山道の参道で結ばれていて、その途中に秋葉寺がある。
江戸時代には上社と秋葉寺が同じ境内にあったが、明治の神仏分離で別になった。
毎年十二月に秋葉の火祭が行われるが、秋葉神社は下社で神事が、秋葉寺では火渡りの行事が仏式で行われるようである。
秋葉さんいえば、火祭の他、連想されるのは天狗である。
国道152号から国道362号に入り、道の駅、いっぷく処横川を通り過ぎると、
秋葉神社前キャンプ場の看板があるところに天狗と高下駄の銅像があった (右写真)
昔、京都が火事になった時、遠州の秋葉三尺坊が大天狗になって現れ火事を消したという話が残るという。
この銅像は、天狗が飛来するための踏み台として残された高下駄と天狗を表現した、という説明碑もあったが、
高下駄は異様に大きかった。
江戸時代の江戸は 「 火事と喧嘩が江戸の華 」 といわれた程、火事が多かったので、
火防の神と信仰された秋葉神社の分社や石碑が多く
建立されると共に、秋葉詣でも盛んだったようである。

同年同月同日
高根城跡

国道152号の南信濃から天竜二俣までは観光客やツーリング客以外はほとんど通行はない。
地元民でも、長野県側と静岡県側での行き来は皆無に近いようである。
しかし、戦国時代には甲州と信濃の武田信玄、三河や駿河の徳川家康、全国統一を狙う織田信長などがこの地を重視
して、幾度かの戦争が行われた。
その一つが奥山氏が築いた高根城(久頭郷城)である (右写真)
奥山氏は藤原北家の井伊氏の一族で、南北朝の時代に遠江国引佐郡奥山郷を中心に勢力を伸ばした。
奥山定則は南朝方で、延元三年、高根城を築き、尹良親王を供泰した。
孫の定之の嫡男、民部少輔定益が高根城を継いたが、二男の水巻城主、定茂は信州遠山氏と謀って、
永禄十二年(1569)、高根城を攻め、落城させ、城主の定益を討死させた。
背後には武田家と今川家の存在があったのだろう。
城跡までの道はけっこう急である。
高根城跡は典型的な山城で、発掘調査後、再現した施設は城好きには一見の価値があるように思えた。
展望台の右手に上村集落、眼下
に水窪の町、正面には青崩峠のある熊伏山や観音山の山並みが見え、展望もよい。

2011年8月7日
兵越峠

国道152号は青崩峠手前で行き止まりとなるが、歩けば青崩峠にいける筈と出かけた。
中央道飯田インターから県道を経由し、三信遠自動車道矢筈トンネルをくぐり、上村から南信濃に出る。
和田は戦国時代には城下町だったところで、江戸時代には秋葉街道の宿場だったところ。
ここでは湯質の良いかぐらの湯に入り、昼食もとった。
その後、青崩峠に向うと、青崩峠への三叉路に土砂崩れで通行禁止の看板があり、中に入れない。
しかたがないので、兵越林道に入ると、長野県と静岡県の境の兵越峠に出た。
「 勝った方が国境を1メートル奥にすることができるというルールのもと、
毎年、峠の国取り公園で、信濃側の南信濃と静岡側の水窪町とで綱引きが行われる。 」 という
案内板があったが、兵越峠まで行くと、実際、それを示す杭が建っていた (右写真)
戦国時代に人を殺し合わず、こうした戦い方があったらおもしろかっただろうと思った。

同年同日
青崩峠

兵越峠を下ると、広い道に出て、草木トンネルを抜けると、左側に青崩峠への標識があるので、その狭い道に入った。
この林道は狭いが舗装はされていた。 しばらく行くと足神神社があり、湧き水で喉を潤した。
その先には瑟平太郎の墓や木地屋の墓などあったが、それらを見ながら進むと、右側に駐車できるスペースがあり、
その先は土砂崩れで通行禁止の看板があった。
ここには塩の道遊歩道の看板があったので、この道で青崩峠を目指した。
杉林の中を歩く道であるが、遊歩道というより登山道で、途中数か所には道の中に小川のように水が流れていた。
途中に武田信玄の腰掛け岩や茶屋だった建次屋敷跡があったが、程なく青崩峠に到着できた (右写真)
峠には 「 青崩峠 海抜一〇八二米 」の木標や「 新浜松の自然100選 青崩峠 」の標柱と「 秋葉道 塩の道 」の小さな道標があった。

その脇に三体の石仏が安置されていたが、右のは馬頭観音、中央は双体道祖神、左のは観音像であろうか?
静かに佇んでいた(右写真)
左側の小高いところには、「 静岡県指定史跡 青崩峠 」の石碑、
反対側には「 熊伏山登山口 」 の看板があった。
峠は穏やかでかつどこにでもある場所に思えたが、国道が造れないというのだから、地盤が脆いのだろう。
信濃側への降りる道は、コンクリート製の杭に囲まれ、かなり急である。
下りていって、どのような状態か確かめようかと思ったが、時々雷鳴がなり、稲妻が光り、徐々に近づいてくる
様子なので、やめにした。
青崩峠への訪問はここ十年来の課題だったので、訪れることが出来たのはうれしかった。

同年同日
天龍の森の鹿

青崩峠訪問の後、秋葉街道の宿場だった水窪により、その後、秋葉詣での旅人も寄ったといわれる山住神神社へ御参りに!!
山住神社は、和銅二年(709)、伊予国大三島の大山祇神を勧請して、山住大権現と称したことに始まる。
徳川家康が武田勢に追われて山住に逃げ込んだ時、ウォーウォーという山犬の大音声がおこり、武田勢を退散させたことから、徳川家康の崇敬を受けたといわれ、
神紋は徳川家の葵の紋で、神札には、山犬が描かれている。
参拝した頃から霧が濃くなってきて、神木を隠すようになった。
この後、秋葉神社上社へ行こうと思い、天竜スパー林道に入ったが、霧が更に深くなり、
十メートル先も見えない状態で、走行が難しかった。
なんとか天龍の森に辿りついたが、当然のことながら、車も人影もなく、寂寞とした雰囲気だった。
そのとき、奥の方にいたのが鹿達である。
人がいないのを良いことにして、広い駐車場の中を闊歩していた。

2011年6月19日
東福寺天得院

桔梗の寺として有名な東福寺塔頭の萬松山天得院を訪れた。
この寺は桔梗と萩が咲くこの時期と紅葉の秋にしか公開されない。
今年の公開は六月十七日からだったが、それに合せるかのように同窓会があったので、
早速訪問したのである。
場所は京阪東福寺駅から歩いて十分位にある中門から入って左側にある。
拝観料は五百円で、中に入ると左側に桃山時代に作られたと伝えられる庭があり、石組と燈籠以外はスギコケで覆われている。
コケの上に植えられているのは桔梗である。
お寺でいただいたパンフレットには白と紫の花が無数に咲く写真が掲載されていたが、
小生が見たのは三株に咲いた数輪の紫の花だけだったので、早すぎたようである。
桔梗の花言葉は 「 清楚、気品 」 であるが、花を見ているとまさしく清楚で気品がある。
機会があればまた訪れようと思った。

2011年6月19日
光明院の枯山水

東福寺の二十五塔頭の一つである光明院は鎌倉時代に創建された寺であるが、そこにある庭園により虹の寺とも呼ばれている。
光明院の名を有名にしたのはJR東海の 「 そうだ!! 京都に行こう!! 」 のキャンペーンポスターによる。
この寺には昭和の名造園家として有名な重森三玲が昭和十四年(1939)に作庭した 「 波心の庭 」 がある。
訪れてみると建物はL字形をしていて、その間に白砂と苔を配置し、その間に大小の石を並べた枯山水だった。
また、背後に植えられたサツキやつつじの刈り込みも変わった形で雲紋を表現しているようだった。

2011年6月5日
芝生の緑

箱根仙石原のポーラ美術館でレオナール・フジタの特別展を見てから、ラリック美術館を訪れた。
ルネ・ラリックは、ジュエリーデザイナーとしては卓越した才能を持ち、その分野で名声を得ていただけあって、
その作品には感心するものがあった。
しかし、その後の彼はガラスを香水瓶として商品化するなど今日の工業デザイナー兼事業家に転身。
ガラス美術製品を大量販売にした効は分るが、この美術館のガラス作品ではガレやドーム兄弟のような芸術性は感じられなかった。
それより美術館の前の芝生の緑が霧雨とあいまって、妙に印象に残った。

2011年5月25日
仁王像

瑞浪市には瑞桜山法明寺という高野山や比叡山と同規模の伽藍が建っている寺院があったという。
天台宗だったため、織田信長の弾圧により、立派な伽藍や二十四もあったという僧坊を焼かれてしまい、
江戸時代になって建てられた桜薬師堂のみが建っている。
また、市街地から離れているので、平安時代には多くの人が行き来したという実感は感じられないところである。
瑞浪は多治見や土岐とともに美濃焼の産地である。 寺院の入口には八脚門があり、そこには木製の仁王像が祀られていたが、
桜薬師堂の入口には陶製の仁王像の頭部分が左右に祀られ、小生が入るのを睨んでいた。

2011年5月15日
伊庭

滋賀県東近江市は最近の町村合併でできた市であるが、それを構成して町に旧能登川町があり、その中に伊庭集落がある。
伊庭は、伊庭千軒と称し、今の伊庭、能登川、安楽寺、須田の四つの集落を伊庭荘といい、皇室の御領地だった。
鎌倉時代の建久年間に観音寺城主佐々木行実の四男の高実が伊庭氏を名乗り、この地を領した、という歴史的に古いところである。
今回訪れたのは伊庭城跡を確認するために訪れたのだが、集落全体が用水濠で囲まれて風情があるところだった。
ちょうど菖蒲とつつじの季節だったので、水の中の黄色のしょうぶと陸のピンクのつつじのコントラストはよかった。

2011年5月4日
近江八幡

ゴールデンウィークの5月4日、朝鮮人街道を歩いて近江八幡を訪れた。
これまで2度訪れているところで、最初は家内が行きたいということで西国十番長命寺を訪れた後
訪問したが、当時は会社生活が多忙だったので、さっと済ませて家内からひんしゅくを買った。
家内からすれば、町の通りをゆっくり歩くことや水郷めぐりなどを考えていたが、こちらはできるだけ早く帰りたいという気であった。
次回行ったのは娘と安土城に行ったときで、近江八幡では八幡城跡を確認するのが狙いだったので、神社と八幡山のロープウエイで時間が一杯だった。
従って、八幡の街を歩いたのは始めてということになる。
しかし、当日は観光客が大勢で落ち着いて見ることはできず、外から建物を見て回ると云う事で終わった。
八幡堀に遊船があるのを見たのは始めてである。 水郷には以前から運行していたが、いつから始まったのだろうか?
昭和60年頃までの八幡堀はごみが捨てられたりして見られるものではなかったというが、水面に柳がたれて風情のある風景になっている。

2011年4月6日
さくら日和

さくら日和というのがあるのか否か分らないが、今日歩いた上街道の一日はどこにいっても桜が満開だった。
桜の撮影は青空の日がよいといわれるが、確かにそうで、曇り空では桜の白い花が雲に飲み込まれて、
灰色ぽい印象の薄い写真になってしまう。 それに対し、青空は白を引き立ててくれる。
上街道では五条川や新郷瀬川沿いの桜や観音寺や真禅寺などの桜もあり、どれも輝くような満開だった。
これらはソメイヨシノのような気がしたが、一部は違うのかも知れない。
その中で城東小学校の先の小山にあったのはヤマザクラだろう。 かなり大きな木で、純白な花が咲いていた (右写真)

2011年1月17日
初 雪

ここ数年は温暖化の傾向のせいか、名古屋地方には雪はほとんどなく、降ってもも積もることはなかった。
今年の冬はこれまでと一変して、暮れから寒い日が続き、灯油代の値上がりもあって、寒さが身にしみた。
そう思っていた1月17日、朝起きたら一面の銀世界だった。
フラワーボックスに咲いているビオラやパンジー、そして、ガーデンシクラメンにも、雪が被って寒そうだった。
雪がやむのを待って、道路を合わせて雪かきをしたが、けっこうな運動になった。
雪国の人はこんなのんきなことは云っておられないだろう。 申し訳ない・・・

2010年11月24日
富士川サービスエリア

東名高速道路を走ると、富士川サービスエリアに立ち寄ることにしている。
一番の目的は食事であるが、お土産ものも豊富でよい。
そして、最後に向かうには富士が見える展望台である。
右手には富士川が小さく見えて、左側は小山に展望が遮られるが、その奥に富士の雄姿が顔を出すので、
性懲りもなく、訪れるのである。
当日は手前の山に秋の風情が漂っていて、富士山には雲もあったが、久し振りの再会で満足した。

2010年3月3日
当尾の石仏めぐり

これまで京都府の南部にある浄瑠璃寺と岩間寺には何回か訪れていた。 これらの寺は京都と奈良の
間にあるが、誕生したのが平安時代のようで、なぜなのだろうかと思っていたので、
フリーハイクで当尾の石仏を歩くという企画を見つけて参加してみた。
現地に行くと、思った以上に多くの石仏が残っていて、平安末期から鎌倉時代のものだと分かり驚いた。
その中でも、笑い仏とある三体の石像は痛みもすくなく、千年近くそこにあるとは思えないものだった (右写真)
この地区は奈良興福寺の別所だったところだが、平安時代の末期に起こった末法思想により、阿弥陀信仰が起こったが、
その影響が大変大きかったところのようである。 それが体験できるのが浄瑠璃寺で、九体阿弥陀堂と浄土式庭園、そして、
三重塔である。 宇治の平等院鳳凰堂も同じ考えでできたものだが、この世も衰退すると予言された当時の人達は阿弥陀仏や
石仏を彫って、心の拠り所にしたのは現在も変わらないのではないかと思った次第である。
2010年1月17日
松花堂旧蹟

石清水八幡宮に詣でた時、上り参道の七曲がりにかかる所で、下に降りる道の下には下馬の石碑と
合鎚神社の小さな社がある。 東海道を歩いた時、京三条粟田口で刀匠三條小鍛冶宗近の家があった
ところに、正一位合槌稲荷明神が祀られていた。 この神社も同じ合鎚神社で、宗近が稲荷大明神
の神助を得て、名刀、小狐丸を打ったのは、ここ石清水で、使用した水は神社の先の山の井戸である
とあったが、本当だろうか? それはともかく、その先を歩いて行くと、門前に松花堂旧蹟の石碑が
建つ泰勝寺があった。 奥を覗くと
禅風の窓に植物の影が映り、左側には南天の実、中央には白い椿の花が活けられた壺が置かれている
のが見えた (右写真)
この寺には、近衛信尹、本阿弥光悦とともに寛永の三筆と称せられた松花堂昭乗が葬ら
れている。 松花堂は多才な人物で、男山の中腹に草庵を設けると、文化人が多く詰めかけたという。

2010年1月17日
石清水八幡宮

昨年から東海道57次を歩いている。 既に山科追分から中書島まで歩いた。 明日はその先、枚方宿
まで歩くつもりだが、その前日、初詣を兼ねて、八幡市の石清水八幡宮へ訪れた (右写真)
歴史書を見ると、天皇や平安貴族が牛車に揺られて、石清水八幡宮を訪れたことがしばしば出てくる。
また、戦国武将が石清水八幡宮に勝利を祈願したことは数多かった。 石清水八幡宮の案内には出て
こないが、もとは中腹にある石清水からの水を神とする原始宗教であったが、平安時代に大分の宇佐
八幡宮から応神天皇などの祭神を勧請して八幡宮になったもので、もとの神様は傍らに押しやられた
という観がする。
当日は厄払い大祭が開かれていたこともあり、多くの人が来ていて、1万3千円以上もかけて、祈とう
を受けていたのには驚いた。

これ以前に書いたものもどうぞ!!
2009年(平成21年)
2008年(平成20年)
2007年(平成19年)
2006年(平成18年)
2005年(平成17年)
2004年(平成16年)



 秋葉神社は山の上の秋葉神社上社と麓の秋葉神社下社と二つあり、
それらは五十丁といわれる山道の参道で結ばれていて、その途中に秋葉寺がある。
江戸時代には上社と秋葉寺が同じ境内にあったが、明治の神仏分離で別になった。
毎年十二月に秋葉の火祭が行われるが、秋葉神社は下社で神事が、秋葉寺では火渡りの行事が仏式で行われるようである。
秋葉さんいえば、火祭の他、連想されるのは天狗である。
国道152号から国道362号に入り、道の駅、いっぷく処横川を通り過ぎると、
秋葉神社前キャンプ場の看板があるところに天狗と高下駄の銅像があった (右写真)
秋葉神社は山の上の秋葉神社上社と麓の秋葉神社下社と二つあり、
それらは五十丁といわれる山道の参道で結ばれていて、その途中に秋葉寺がある。
江戸時代には上社と秋葉寺が同じ境内にあったが、明治の神仏分離で別になった。
毎年十二月に秋葉の火祭が行われるが、秋葉神社は下社で神事が、秋葉寺では火渡りの行事が仏式で行われるようである。
秋葉さんいえば、火祭の他、連想されるのは天狗である。
国道152号から国道362号に入り、道の駅、いっぷく処横川を通り過ぎると、
秋葉神社前キャンプ場の看板があるところに天狗と高下駄の銅像があった (右写真) 国道152号の南信濃から天竜二俣までは観光客やツーリング客以外はほとんど通行はない。
地元民でも、長野県側と静岡県側での行き来は皆無に近いようである。
しかし、戦国時代には甲州と信濃の武田信玄、三河や駿河の徳川家康、全国統一を狙う織田信長などがこの地を重視
して、幾度かの戦争が行われた。
その一つが奥山氏が築いた高根城(久頭郷城)である (右写真)
国道152号の南信濃から天竜二俣までは観光客やツーリング客以外はほとんど通行はない。
地元民でも、長野県側と静岡県側での行き来は皆無に近いようである。
しかし、戦国時代には甲州と信濃の武田信玄、三河や駿河の徳川家康、全国統一を狙う織田信長などがこの地を重視
して、幾度かの戦争が行われた。
その一つが奥山氏が築いた高根城(久頭郷城)である (右写真) 国道152号は青崩峠手前で行き止まりとなるが、歩けば青崩峠にいける筈と出かけた。
国道152号は青崩峠手前で行き止まりとなるが、歩けば青崩峠にいける筈と出かけた。  兵越峠を下ると、広い道に出て、草木トンネルを抜けると、左側に青崩峠への標識があるので、その狭い道に入った。
この林道は狭いが舗装はされていた。 しばらく行くと足神神社があり、湧き水で喉を潤した。
その先には瑟平太郎の墓や木地屋の墓などあったが、それらを見ながら進むと、右側に駐車できるスペースがあり、
その先は土砂崩れで通行禁止の看板があった。
ここには塩の道遊歩道の看板があったので、この道で青崩峠を目指した。
杉林の中を歩く道であるが、遊歩道というより登山道で、途中数か所には道の中に小川のように水が流れていた。
途中に武田信玄の腰掛け岩や茶屋だった建次屋敷跡があったが、程なく青崩峠に到着できた (右写真)
兵越峠を下ると、広い道に出て、草木トンネルを抜けると、左側に青崩峠への標識があるので、その狭い道に入った。
この林道は狭いが舗装はされていた。 しばらく行くと足神神社があり、湧き水で喉を潤した。
その先には瑟平太郎の墓や木地屋の墓などあったが、それらを見ながら進むと、右側に駐車できるスペースがあり、
その先は土砂崩れで通行禁止の看板があった。
ここには塩の道遊歩道の看板があったので、この道で青崩峠を目指した。
杉林の中を歩く道であるが、遊歩道というより登山道で、途中数か所には道の中に小川のように水が流れていた。
途中に武田信玄の腰掛け岩や茶屋だった建次屋敷跡があったが、程なく青崩峠に到着できた (右写真) その脇に三体の石仏が安置されていたが、右のは馬頭観音、中央は双体道祖神、左のは観音像であろうか?
静かに佇んでいた(右写真)
その脇に三体の石仏が安置されていたが、右のは馬頭観音、中央は双体道祖神、左のは観音像であろうか?
静かに佇んでいた(右写真) 青崩峠訪問の後、秋葉街道の宿場だった水窪により、その後、秋葉詣での旅人も寄ったといわれる山住神神社へ御参りに!!
山住神社は、和銅二年(709)、伊予国大三島の大山祇神を勧請して、山住大権現と称したことに始まる。
徳川家康が武田勢に追われて山住に逃げ込んだ時、ウォーウォーという山犬の大音声がおこり、武田勢を退散させたことから、徳川家康の崇敬を受けたといわれ、
神紋は徳川家の葵の紋で、神札には、山犬が描かれている。
参拝した頃から霧が濃くなってきて、神木を隠すようになった。
この後、秋葉神社上社へ行こうと思い、天竜スパー林道に入ったが、霧が更に深くなり、
十メートル先も見えない状態で、走行が難しかった。
なんとか天龍の森に辿りついたが、当然のことながら、車も人影もなく、寂寞とした雰囲気だった。
そのとき、奥の方にいたのが鹿達である。
人がいないのを良いことにして、広い駐車場の中を闊歩していた。
青崩峠訪問の後、秋葉街道の宿場だった水窪により、その後、秋葉詣での旅人も寄ったといわれる山住神神社へ御参りに!!
山住神社は、和銅二年(709)、伊予国大三島の大山祇神を勧請して、山住大権現と称したことに始まる。
徳川家康が武田勢に追われて山住に逃げ込んだ時、ウォーウォーという山犬の大音声がおこり、武田勢を退散させたことから、徳川家康の崇敬を受けたといわれ、
神紋は徳川家の葵の紋で、神札には、山犬が描かれている。
参拝した頃から霧が濃くなってきて、神木を隠すようになった。
この後、秋葉神社上社へ行こうと思い、天竜スパー林道に入ったが、霧が更に深くなり、
十メートル先も見えない状態で、走行が難しかった。
なんとか天龍の森に辿りついたが、当然のことながら、車も人影もなく、寂寞とした雰囲気だった。
そのとき、奥の方にいたのが鹿達である。
人がいないのを良いことにして、広い駐車場の中を闊歩していた。
 桔梗の寺として有名な東福寺塔頭の萬松山天得院を訪れた。
この寺は桔梗と萩が咲くこの時期と紅葉の秋にしか公開されない。
今年の公開は六月十七日からだったが、それに合せるかのように同窓会があったので、
早速訪問したのである。
桔梗の寺として有名な東福寺塔頭の萬松山天得院を訪れた。
この寺は桔梗と萩が咲くこの時期と紅葉の秋にしか公開されない。
今年の公開は六月十七日からだったが、それに合せるかのように同窓会があったので、
早速訪問したのである。  東福寺の二十五塔頭の一つである光明院は鎌倉時代に創建された寺であるが、そこにある庭園により虹の寺とも呼ばれている。
東福寺の二十五塔頭の一つである光明院は鎌倉時代に創建された寺であるが、そこにある庭園により虹の寺とも呼ばれている。  箱根仙石原のポーラ美術館でレオナール・フジタの特別展を見てから、ラリック美術館を訪れた。
ルネ・ラリックは、ジュエリーデザイナーとしては卓越した才能を持ち、その分野で名声を得ていただけあって、
その作品には感心するものがあった。
しかし、その後の彼はガラスを香水瓶として商品化するなど今日の工業デザイナー兼事業家に転身。
ガラス美術製品を大量販売にした効は分るが、この美術館のガラス作品ではガレやドーム兄弟のような芸術性は感じられなかった。
それより美術館の前の芝生の緑が霧雨とあいまって、妙に印象に残った。
箱根仙石原のポーラ美術館でレオナール・フジタの特別展を見てから、ラリック美術館を訪れた。
ルネ・ラリックは、ジュエリーデザイナーとしては卓越した才能を持ち、その分野で名声を得ていただけあって、
その作品には感心するものがあった。
しかし、その後の彼はガラスを香水瓶として商品化するなど今日の工業デザイナー兼事業家に転身。
ガラス美術製品を大量販売にした効は分るが、この美術館のガラス作品ではガレやドーム兄弟のような芸術性は感じられなかった。
それより美術館の前の芝生の緑が霧雨とあいまって、妙に印象に残った。
 瑞浪市には瑞桜山法明寺という高野山や比叡山と同規模の伽藍が建っている寺院があったという。
天台宗だったため、織田信長の弾圧により、立派な伽藍や二十四もあったという僧坊を焼かれてしまい、
江戸時代になって建てられた桜薬師堂のみが建っている。
また、市街地から離れているので、平安時代には多くの人が行き来したという実感は感じられないところである。
瑞浪は多治見や土岐とともに美濃焼の産地である。 寺院の入口には八脚門があり、そこには木製の仁王像が祀られていたが、
桜薬師堂の入口には陶製の仁王像の頭部分が左右に祀られ、小生が入るのを睨んでいた。
瑞浪市には瑞桜山法明寺という高野山や比叡山と同規模の伽藍が建っている寺院があったという。
天台宗だったため、織田信長の弾圧により、立派な伽藍や二十四もあったという僧坊を焼かれてしまい、
江戸時代になって建てられた桜薬師堂のみが建っている。
また、市街地から離れているので、平安時代には多くの人が行き来したという実感は感じられないところである。
瑞浪は多治見や土岐とともに美濃焼の産地である。 寺院の入口には八脚門があり、そこには木製の仁王像が祀られていたが、
桜薬師堂の入口には陶製の仁王像の頭部分が左右に祀られ、小生が入るのを睨んでいた。
 滋賀県東近江市は最近の町村合併でできた市であるが、それを構成して町に旧能登川町があり、その中に伊庭集落がある。
伊庭は、伊庭千軒と称し、今の伊庭、能登川、安楽寺、須田の四つの集落を伊庭荘といい、皇室の御領地だった。
鎌倉時代の建久年間に観音寺城主佐々木行実の四男の高実が伊庭氏を名乗り、この地を領した、という歴史的に古いところである。
今回訪れたのは伊庭城跡を確認するために訪れたのだが、集落全体が用水濠で囲まれて風情があるところだった。
ちょうど菖蒲とつつじの季節だったので、水の中の黄色のしょうぶと陸のピンクのつつじのコントラストはよかった。
滋賀県東近江市は最近の町村合併でできた市であるが、それを構成して町に旧能登川町があり、その中に伊庭集落がある。
伊庭は、伊庭千軒と称し、今の伊庭、能登川、安楽寺、須田の四つの集落を伊庭荘といい、皇室の御領地だった。
鎌倉時代の建久年間に観音寺城主佐々木行実の四男の高実が伊庭氏を名乗り、この地を領した、という歴史的に古いところである。
今回訪れたのは伊庭城跡を確認するために訪れたのだが、集落全体が用水濠で囲まれて風情があるところだった。
ちょうど菖蒲とつつじの季節だったので、水の中の黄色のしょうぶと陸のピンクのつつじのコントラストはよかった。
 ゴールデンウィークの5月4日、朝鮮人街道を歩いて近江八幡を訪れた。
これまで2度訪れているところで、最初は家内が行きたいということで西国十番長命寺を訪れた後
訪問したが、当時は会社生活が多忙だったので、さっと済ませて家内からひんしゅくを買った。
家内からすれば、町の通りをゆっくり歩くことや水郷めぐりなどを考えていたが、こちらはできるだけ早く帰りたいという気であった。
次回行ったのは娘と安土城に行ったときで、近江八幡では八幡城跡を確認するのが狙いだったので、神社と八幡山のロープウエイで時間が一杯だった。
従って、八幡の街を歩いたのは始めてということになる。
しかし、当日は観光客が大勢で落ち着いて見ることはできず、外から建物を見て回ると云う事で終わった。
ゴールデンウィークの5月4日、朝鮮人街道を歩いて近江八幡を訪れた。
これまで2度訪れているところで、最初は家内が行きたいということで西国十番長命寺を訪れた後
訪問したが、当時は会社生活が多忙だったので、さっと済ませて家内からひんしゅくを買った。
家内からすれば、町の通りをゆっくり歩くことや水郷めぐりなどを考えていたが、こちらはできるだけ早く帰りたいという気であった。
次回行ったのは娘と安土城に行ったときで、近江八幡では八幡城跡を確認するのが狙いだったので、神社と八幡山のロープウエイで時間が一杯だった。
従って、八幡の街を歩いたのは始めてということになる。
しかし、当日は観光客が大勢で落ち着いて見ることはできず、外から建物を見て回ると云う事で終わった。 さくら日和というのがあるのか否か分らないが、今日歩いた上街道の一日はどこにいっても桜が満開だった。
桜の撮影は青空の日がよいといわれるが、確かにそうで、曇り空では桜の白い花が雲に飲み込まれて、
灰色ぽい印象の薄い写真になってしまう。 それに対し、青空は白を引き立ててくれる。
さくら日和というのがあるのか否か分らないが、今日歩いた上街道の一日はどこにいっても桜が満開だった。
桜の撮影は青空の日がよいといわれるが、確かにそうで、曇り空では桜の白い花が雲に飲み込まれて、
灰色ぽい印象の薄い写真になってしまう。 それに対し、青空は白を引き立ててくれる。 ここ数年は温暖化の傾向のせいか、名古屋地方には雪はほとんどなく、降ってもも積もることはなかった。
今年の冬はこれまでと一変して、暮れから寒い日が続き、灯油代の値上がりもあって、寒さが身にしみた。
ここ数年は温暖化の傾向のせいか、名古屋地方には雪はほとんどなく、降ってもも積もることはなかった。
今年の冬はこれまでと一変して、暮れから寒い日が続き、灯油代の値上がりもあって、寒さが身にしみた。  東名高速道路を走ると、富士川サービスエリアに立ち寄ることにしている。
東名高速道路を走ると、富士川サービスエリアに立ち寄ることにしている。  これまで京都府の南部にある浄瑠璃寺と岩間寺には何回か訪れていた。 これらの寺は京都と奈良の
間にあるが、誕生したのが平安時代のようで、なぜなのだろうかと思っていたので、
フリーハイクで当尾の石仏を歩くという企画を見つけて参加してみた。
これまで京都府の南部にある浄瑠璃寺と岩間寺には何回か訪れていた。 これらの寺は京都と奈良の
間にあるが、誕生したのが平安時代のようで、なぜなのだろうかと思っていたので、
フリーハイクで当尾の石仏を歩くという企画を見つけて参加してみた。  石清水八幡宮に詣でた時、上り参道の七曲がりにかかる所で、下に降りる道の下には下馬の石碑と
合鎚神社の小さな社がある。 東海道を歩いた時、京三条粟田口で刀匠三條小鍛冶宗近の家があった
ところに、正一位合槌稲荷明神が祀られていた。 この神社も同じ合鎚神社で、宗近が稲荷大明神
の神助を得て、名刀、小狐丸を打ったのは、ここ石清水で、使用した水は神社の先の山の井戸である
とあったが、本当だろうか? それはともかく、その先を歩いて行くと、門前に松花堂旧蹟の石碑が
建つ泰勝寺があった。 奥を覗くと
禅風の窓に植物の影が映り、左側には南天の実、中央には白い椿の花が活けられた壺が置かれている
のが見えた (右写真)
石清水八幡宮に詣でた時、上り参道の七曲がりにかかる所で、下に降りる道の下には下馬の石碑と
合鎚神社の小さな社がある。 東海道を歩いた時、京三条粟田口で刀匠三條小鍛冶宗近の家があった
ところに、正一位合槌稲荷明神が祀られていた。 この神社も同じ合鎚神社で、宗近が稲荷大明神
の神助を得て、名刀、小狐丸を打ったのは、ここ石清水で、使用した水は神社の先の山の井戸である
とあったが、本当だろうか? それはともかく、その先を歩いて行くと、門前に松花堂旧蹟の石碑が
建つ泰勝寺があった。 奥を覗くと
禅風の窓に植物の影が映り、左側には南天の実、中央には白い椿の花が活けられた壺が置かれている
のが見えた (右写真) 昨年から東海道57次を歩いている。 既に山科追分から中書島まで歩いた。 明日はその先、枚方宿
まで歩くつもりだが、その前日、初詣を兼ねて、八幡市の石清水八幡宮へ訪れた (右写真)
昨年から東海道57次を歩いている。 既に山科追分から中書島まで歩いた。 明日はその先、枚方宿
まで歩くつもりだが、その前日、初詣を兼ねて、八幡市の石清水八幡宮へ訪れた (右写真)