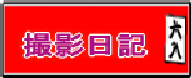

2008年12月28日
名古屋駅電飾

今年は8月までは順調であったが、9月に入ると米国の住宅ローン専門会社の破綻に端を発し、12月にはトヨタを
始めすべての自動車会社の生産中止と人員削減という未曽有の危機が訪れた。 米国や欧州で金融危機が訪れているのに、
日本は大丈夫と言いきった経済評論家、財務省、日銀、そして麻生首相の責任は重い。 また、バブルと承知しながら、
過大な設備投資をしたトヨタやシャープなどの経営者も同罪である。 今日のねぐらを探して、苦労する派遣社員や臨時工
の皆さんの苦労はいかばかりと思う。
来る年はどうなるのだろうか??、いささか心配である。
例年、名古屋駅の高島屋では、この時期に電飾で飾られる。 昨年は、クリスマスイブにいったら、サンタクロースが沢山
画面に現れた。 今年は、12月28日に訪れたが、白を基調とした電飾であった。
皆様良いお年をお迎え下さい!!

2008年12月03日
紅葉はどこにでも

秋になると紅葉を求めて、車を走らせてきた。 今年は東海地方の街道を歩いているせいか、そのような
気にならなかった。 ここ数年は1週間位遅く、紅葉がずれていたが、新聞を見ると、今年は以前と同じ
時期に紅葉が始まった、という。 小生は、12月7日〜9日まで京都に行くことになっているが、この
調子であれば、葉が散ってしまうだろう。 それはそれでしょうがない。
今日は鮎鮨街道を歩き、岐阜県笠松町から奈良時代、尾張国府が置かれた稲沢市にいこうと歩いていた。
途中の一宮市は尾張国一之宮が置かれたので、その名が付いたところである。 その神社を探して歩いて
いたとき、見えたのが九品地(くほんじ)公園で、天にも届きそうなトドマツ(と思うが)の素晴らしい黄葉
が見えた。 電線が邪魔したので、公園の中に入ったが、障害物があり、断念。 諦めたとき見えたのが、
この木。 見事に紅葉。 遠くに行かなくでも、紅葉は見られると思った。

2008年11月26日
なばなの里 電飾

桑名の先にある歯医者に歯の治療で、通うようになったため、高速を使い、都合10回程通った。 ただ通うだけではもった
いないと、立寄ったのが諸戸家住宅で、建物の立派なのと隣接したレストランのフランス料理が安くうまかったので、
治療終了日に、妻を誘った。 まず、桑名城跡と七里の渡し跡を訪れ、その足で諸戸家住宅へ。 諸戸家は、明治時代に財
をなした実業家で、その家は六華苑と呼ばれ、洋館に和風の建物が隣接し、日本庭園がある。 富豪の家とはこういうものだ
、と思わせる家である。 フランス料理で、腹を充たし、長島のジャズドリームに向かう。 ほぼ一周した後、結婚記念日の
プレゼントとして、彼女が気に入ったハンドバックを購入した。 夕方には間があったが、なばなの里へ行く。
電飾が灯るには早いが、ベコニアガーデンに案内すればよい、と思ったからである。 花の最盛期には早いようで、
水の中に浮かんでいた花数は少なかった。 秋の夜の訪れは早く、待っているうち、薄暗くなり、イルミネーションが始
まった。
電飾の下には、花畑があるとは思えないほど、赤、白、青と多彩の色で、覆われ、見事である。
ここ数年の電飾技術の発達はすごいと思った。

2008年11月21日
名古屋城の秋

江戸時代の名古屋は 尾張徳川家が居城する城下町であるが、東海道は熱田神宮がある宮宿から桑名に舟で
渡っていったので、名古屋は通過しなかった。 今は宮宿だったところも名古屋市なので、少し変に感じる
が、別の町だったのである。 とはいえ、熱田から中山道の垂井宿を結ぶ美濃路は名古屋を通っていて、
名古屋城の周りをぐるーと回るような道筋になっていた。
美濃路を歩いてみようと、地下鉄伝馬町駅から跡をたどると、本町通りから伝馬町通りに入るところで、城の
方向から西に向かう形になり、その後は城を右手に見ながら進むことが分かった。 江戸時代は今のように
高い建物がなかったので、旅人は名古屋城を見ることができたのだろうか?
春の名古屋城は桜の名所なので、数回訪れたが、秋は見たことがなかった。 今回の歩きで、街道を外れて
訪れてみると、桜が紅葉して秋の盛りだった。

2008年11月16日
浄瑠璃寺

三十数年振りに浄瑠璃寺を訪れた。 子供は幼い時で、義母を京都に案内した翌日、ここに来たように、記憶している。
三十年をすれば、変わるのが当たり前かも知れないが、砂利道だったところが、道が広くなり、舗装されていた。
また、売店や飲食店が出ていた。 浄瑠璃寺は、昔は多くの伽藍をようしたお寺だったようであるが、本堂と三重塔のみ
のお寺である 平安時代に、薬師如来を本尊として創建されたが、九品往生
(くほんおうじょう)思想の普及
により、六十年後の嘉承二年(1107)に、九体の阿弥陀如来を安置する本堂が建立された、という。 薬師如来は、三重塔に
祀られている。 平安時代、京都には、多くの塔が建立され、百塔参りが流行した。 九体の阿弥陀仏を安置したお堂は、
三十数棟建立された、というが、九体御堂も塔も戦乱に巻き込まれ焼失してしまった。 奇跡的に残った浄瑠璃寺の九体阿
弥陀仏を拝むこと
ができ、また、本堂と三重塔の間の宝池の周りの美しい紅葉も見られ、まさに命の洗濯をした。

2008年11月15日
紅葉の峠越え(国道425号線を走る)

奈良県の秘湯である十津川温泉を訪れた帰路、旅館の人には道が狭いので、勧められないといわれたが、十津川高滝下
から下北山村に抜ける国道425号を走った。 入るとすぐ、ダンプカーが10台ほど走ってきたので、困ったと思っ
たが、彼らは慣れているので、通り抜けていった。 少し走ると、右手に滝が見えてきた。 不動滝、別名高滝で、
落差46m。 水量は少ないが、紅葉した木の間から見る滝はきれいだった (右写真)
滝の水は芦廼瀬川に注ぎ渓谷を
造っている。 渓谷に沿って、国道は進むが、下を見ると紅葉した木々が連なり、見事である。 これまで紅葉といえ
ば、赤一色、黄一色というように一つの色を写してきたが、ここにはそうした塊はない。 いろいろな色がごじゃまぜに
した風景が展開している。 赤に黄土、そして黄色、それに緑、黄緑が微妙なバランスを保っていた。 これも紅葉
なのだと思った。 その先には、滑滝(なめりたき)といわれる、

水が川の傾斜に沿って、滑り下るような滝である。 日光のの華厳の滝のような直下型の滝もよいが、竜頭の滝のような
滑滝は安定感があり、好きである (右写真)
ここを過ぎると、高度が上がり、渓谷は下に見える。 対向車もあったので、すれ
違いに注意するため、運転に専念し、風景を見るのは妻に任せた。 その先は三叉路で、右に行くと瀞峡へ、左は
森林公園二十一世紀の森を経由し、国道425号は続く。 後で考えると、ここは瀞峡へ降りて、そこから国道169
号線を走った方が早かった、と思う。 森林公園はこのような交通のの不便なところに誰が来るのだろう、と思う
ところにある。 当日は土曜日であったが、訪れるものもなく、しーんとしていた。 雨に濡れて、雑木林の紅葉は
見事であった。

この後、国道425号はぐんぐん高度を上げながら、大峯山の山並みに沿って北上する。 左側は
白谷渓谷に落ち込む崖で、駐車する場所もないため、車を進めるしかない。
高度が高くなると、雨雲が上から下に流れるように下って行くのが見えた (右写真)
幾つかの峠を越えて、行仙岳(1227m)の白谷トンネルをくぐると、下北山村に入る。 ここは
惣田宿があったところのようである。 こちら側の道は急で、一気に駆け下りる感じがする。 下りた左手に町役場
があるが、この集落の戸数は少ない感じがした。 西の川に沿って下ると、池の平公園があり、明神池の前に池神社
があった。 そこから、狭いじぐざくの道を走ると、池郷川の橋を渡り、池原で国道169号に合流し、紅葉に彩ら
れた国道425号と別れを告げた。

2008年10月29日
木曾三川公園センター

木曽三川公園は、1987年10月に開設された、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)下流域一帯、愛知、岐阜、三重の三県に
わたる、日本最大級の国営公園である。 小生が訪れたのは、その中で一番古い木曽三川公園センター(岐阜県海津市)で、
そこには展望塔のある水と緑の館と 花壇、そして、輪中の農家である水屋が再現されている。 一眼レフのカメラを買い、
本格的に写真を撮り始めた時、妻に教えられて、コスモスを写しに訪れたことがあった。 桑名に歯を直すため、通う
ようになり、ふと思い出して、デジカメを持って、帰路立ち寄った。 コスモスが咲いていると思ったら、すでに終わって
いて、庭園には色とりどりの菊が植えられていた。 敷地の一角に、古い茅葺の民家があり、軒に長方形の形をした木製の
ものがあり、その脇にろがつけられていたが、水害時に使われる舟という。 このあたりは、輪中といわれる海抜0m地帯
で、戦前までは時々洪水で家や田畑が流されてところ、という。 隣の水屋はその時に備えた倉庫兼住宅である、とあった。
前回訪れた時には記憶にないので、最近造られたものかも知れない。

2008年10月29日
多度大社

多度大社には、以前に一度だけ訪れたことがある。 義母を案内し、養老の滝を見物した帰りに立ち寄ったもので、人里
離れた田舎と思っていた。 今回、東員町から訪れると、途中に桑名市大山田団地があり、丘稜地は虫食いのような開発
させつつあるなあ、と思った。 いなべ市にトヨタ車体の工場が進出したことも、住宅需要を刺激しているのかも知れない。
道は昔のままなので、住宅地を過ぎると狭くなり、間違えたかと不安になったが、杞憂に終わった。 道路側から馬鹿
でかい鳥居が建っているが、こちらが正面なのだろうか? 突き当たりに多度大社の石段が見え、左側に売店と駐車場が
あった。 平日のせいか、神社を訪れる人はほとんどなく、売店は暇を持て余していた。 神社を参拝後、養老鉄道の
駅に向かって歩くと、柿畑があり、小鳥に食べられたのであろう柿の実があった。 この道がかっての参拝道と思われ、
鯉料理店の大黒屋や多度豆の桔梗屋の古い重厚な建物があった。

2008年9月20日
伏見・寺田屋

江戸時代幕末に起きた寺田屋事件の舞台になった寺田屋に行ってきた。 寺田屋は京都郊外の伏見区にあり、
江戸時代には京と浪速を結ぶ川運の宿場だった、という。 寺田屋事件は、坂本龍馬襲撃事件と思っていたが、
その他にも、文久二年(1862)、当時薩摩藩の定宿だった寺田屋に、薩摩藩の過激派と尊王派が集まり、京都
所司代などを討とうと謀議しているところに薩摩藩から派遣された藩士達が訪れ、小競り合いが起き、七人の
死者を出した事件もあったようで、一階の奥まった部屋がその場所と書かれていた。 坂本龍馬襲撃事件は、
慶応二年(1866)、伏見奉行配下の捕り方が宿泊中の坂本龍馬を捕縛もしくは暗殺しようとした事件である。
入浴中の寺田屋の養女、お龍が、異常を察して、龍馬に知らせ、お龍は薩摩屋敷に駆けこんで、知らせたと
いう。 寺田屋にはその際出来た柱の刀傷とお龍が入ったという風呂を写真に収めたが、最近読んだ新聞
には、寺田屋は明治の後期に再建されたもので、刀傷や風呂は存在しないはずとあった。 それが本当なら
ぺてんということのなるが・・・・

2008年9月13日
八幡城跡の蔦

信長の築いた安土城跡を探索した後、近江商人の町として発展した近江八幡市を訪れた。 八幡堀の近くには、
今でも当時の面影を留める屋敷が残っている。 この町を開いたのは、豊臣秀吉の甥、豊臣秀次である。
秀次は近江四十三万石を与えられて、琵琶湖に臨む標高286mの八幡山に築城し、安土城下から多くの住民を
移住させ、城下町を造った。 その時、琵琶湖から水を引いて造られたのが八幡堀で、城の堀の他、運河の役目
を果たし、商業の発展に寄与した。 秀次が尾張清洲に移ると、京極高次が八幡城主になったが、彼も大津城に
移ると、八幡城は廃城となった。 この年、皮肉にも豊臣秀次は秀吉の逆鱗に触れ、高野山で切腹。 城に上る
と石垣だけが残り、石に蔦がからんでいた。 秀頼が生まれたことで、殺された秀次の無念を感じた。 城上
から、彼が築いた碁盤模様の町並みを眺めながら、そう思った。

2008年8月9日
室堂平散策

飛騨トンネル開通記念! 日帰りで行く立山・室堂ハイキングの旅行社の案内を見て、立山に日帰りで行ける
ならと申しこんだ。 どんなコースとか所要時間などを確認せずに・・・・
名古屋からは最低1泊はしないと無理と思っていたので飛びついたのであるが、行ってみて、かなり無理なことに
気づく。 名古屋を出ると、すぐに高速道路が渋滞、当日は土曜なのでトラックはいないと思っていたが、
お盆休みがすでに始まったようで、その先も混み、結局2時間近く遅れ、現地の室堂平の駐車場に着いたのは、
14時半を過ぎていた。 遅くても17時には出ないと、帰宅が深夜になるとあって、現地にいたのは2時間半
たらずだった。 カメラは一式もっていたが、みくりが池を中心に周り、あわだだしく撮影を終えた。 チング
ルマやヨシバシオガワ、コバイケイソウ、
ハクサンイチゲが咲いていたのに残念だった。 今度行く時は泊まろうと思った。

2008年7月17日
梅花藻咲く

醒ヶ井には、二年前の平成18年3月に中山道を歩いた時、訪れた。 醒ケ井の名は、日本書紀の 「 日本武尊
(やまとたけるのみこと) 、伊吹山にて大蛇をふみて、山中の雲霧にあい給ひ、御心地なやましたりしが、此水を
のみて醒めたまひぬとなん 」 に因むものである。 加茂神社前の池には、底からこんこんと清水が湧き出ているのが、
日本武尊を蘇生させた」という居醒(いすい)の清水である。 木曾路名所図会 に、「 此駅に三水四石の名所あり、
町中に流れありて至て清し、寒暑にも増減なし 」 とあるが、今も変わらず流れ出ていた。 ここは、清流に
しか育たないとされる梅花藻の貴重な繁殖地とされる。 かって通った日光の大谷川にもあったのだが、そのような
珍しいものと思わず、愛知に戻ってきていた。 その花が咲くのがこの時期なので、どのような花か?興味があった。
梅花藻は水の中に流れに任せているのだが、花が咲くに比例して、水の上に出てくることを始めて知った。

2008年7月17日
草津市立水生植物園

蓮の花は暑いところがよいのだろうか? 仏教では、お釈迦様と蓮花はセットになっている。 京都や滋賀の寺には
夏になると、水盤に植えられた蓮の花を多く見る。 その代表が、宇治の三室戸寺である。 昔はなかったので、
最近になって始めたように思われるが、これはこれで身近に花を鑑賞できるので、これはこれでよいと思う。 自然の
蓮を撮りたいと思っていたところ、写真倶楽部で草津市立水生植物園に行くというので、参加をした。 行ってみて
分かったのであるが、ここは琵琶湖の東側の烏丸半島に広がるところにあり、広大な敷地に蓮が自生しているのである。
撮影とか、鑑賞用に通路や橋が架けられている訳でもないので、撮影には不向きだった。 園内のスイレンは身近に
撮影できるポイントがあるので、よかったが・・・・

2008年4月12日
海津大崎

滋賀県の桜の名所として有名なのが、海津大崎の桜である。
トンネル開通を記念して植えたとされる
樹齢60年を越える600本の桜が琵琶湖湖岸に4kmにわたり続く。 駐車場が少なく、花見時には込むので、
行かないでいたが、今年思い切っていってみた。
海津大崎は、琵琶湖八景の暁霧・海津大崎の岩礁としても
有名と案内にあるが、今回は船に乗らず、陸地からの撮影で終了したが、湖の碧と爛漫と咲きほこるソメイヨシノ桜
との絶妙なコントラストは美しく、思わずシャッターを切った。
例年の見頃は4月15日の前後のようで、近畿圏では、花見の最後を飾るといわれる桜名所である。
混んできたので、半分くらいのコースで撮影を止めたので、来年は残りを写しに行きたい。

2008年4月10日
山高神代桜

樹齢千八百年から二千年と推定される日本最古の桜で、三春の滝桜、根尾薄墨桜と共に、三大桜といわれる。
神代桜の名は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が、東征の帰途に植えたという伝承による。 根回りは13.5m、
目通り幹囲は11mで、幹の太さは日本最大だが、長い悠遠の歳月を経てるうち、主幹上部は完全に失われ、
主幹の高さはわずか2.4mで、基幹は北側の一部を残すのみで、空洞になっている。 なお、大正十一年に
国の天然記念物に指定された。 主幹の上に被せていた屋根を取り除いたところ、樹勢が回復して、今年の花は
最高と地元の人の言である。 黒い幹は太く、この桜の生命力を感じたので、それを表現しようと写した。
当日は1日中雨だったが、それでも多くの人を集めていた。

2008年4月5日
長興山のしだれ桜

小田原藩主、稲葉家の菩提寺だった長興山紹太寺があった所に咲くシダレザクラ(イトザクラ)!
稲葉正則が祖母の春日の局を供養するために植えたといわれており、幹周りは約3m80cm、高さ約13m、
枝張りは12m〜13m、とある。 推定樹齢は約330年で、大小の二段傘のような樹形になっていた。
場所 小田急箱根鉄道線入生田駅から北方向に一キロほど離れた場所。 旧東海道沿いにある現在の紹太寺の
前を通って、坂道や石段を歩いて山を登っていくと桜に出会える。
駐車場がないので、電車で行くのが一番である。

最新の日記帳に戻る

 今年は8月までは順調であったが、9月に入ると米国の住宅ローン専門会社の破綻に端を発し、12月にはトヨタを
始めすべての自動車会社の生産中止と人員削減という未曽有の危機が訪れた。 米国や欧州で金融危機が訪れているのに、
日本は大丈夫と言いきった経済評論家、財務省、日銀、そして麻生首相の責任は重い。 また、バブルと承知しながら、
過大な設備投資をしたトヨタやシャープなどの経営者も同罪である。 今日のねぐらを探して、苦労する派遣社員や臨時工
の皆さんの苦労はいかばかりと思う。
今年は8月までは順調であったが、9月に入ると米国の住宅ローン専門会社の破綻に端を発し、12月にはトヨタを
始めすべての自動車会社の生産中止と人員削減という未曽有の危機が訪れた。 米国や欧州で金融危機が訪れているのに、
日本は大丈夫と言いきった経済評論家、財務省、日銀、そして麻生首相の責任は重い。 また、バブルと承知しながら、
過大な設備投資をしたトヨタやシャープなどの経営者も同罪である。 今日のねぐらを探して、苦労する派遣社員や臨時工
の皆さんの苦労はいかばかりと思う。  秋になると紅葉を求めて、車を走らせてきた。 今年は東海地方の街道を歩いているせいか、そのような
気にならなかった。 ここ数年は1週間位遅く、紅葉がずれていたが、新聞を見ると、今年は以前と同じ
時期に紅葉が始まった、という。 小生は、12月7日〜9日まで京都に行くことになっているが、この
調子であれば、葉が散ってしまうだろう。 それはそれでしょうがない。
今日は鮎鮨街道を歩き、岐阜県笠松町から奈良時代、尾張国府が置かれた稲沢市にいこうと歩いていた。
途中の一宮市は尾張国一之宮が置かれたので、その名が付いたところである。 その神社を探して歩いて
いたとき、見えたのが九品地(くほんじ)公園で、天にも届きそうなトドマツ(と思うが)の素晴らしい黄葉
が見えた。 電線が邪魔したので、公園の中に入ったが、障害物があり、断念。 諦めたとき見えたのが、
この木。 見事に紅葉。 遠くに行かなくでも、紅葉は見られると思った。
秋になると紅葉を求めて、車を走らせてきた。 今年は東海地方の街道を歩いているせいか、そのような
気にならなかった。 ここ数年は1週間位遅く、紅葉がずれていたが、新聞を見ると、今年は以前と同じ
時期に紅葉が始まった、という。 小生は、12月7日〜9日まで京都に行くことになっているが、この
調子であれば、葉が散ってしまうだろう。 それはそれでしょうがない。
今日は鮎鮨街道を歩き、岐阜県笠松町から奈良時代、尾張国府が置かれた稲沢市にいこうと歩いていた。
途中の一宮市は尾張国一之宮が置かれたので、その名が付いたところである。 その神社を探して歩いて
いたとき、見えたのが九品地(くほんじ)公園で、天にも届きそうなトドマツ(と思うが)の素晴らしい黄葉
が見えた。 電線が邪魔したので、公園の中に入ったが、障害物があり、断念。 諦めたとき見えたのが、
この木。 見事に紅葉。 遠くに行かなくでも、紅葉は見られると思った。
 桑名の先にある歯医者に歯の治療で、通うようになったため、高速を使い、都合10回程通った。 ただ通うだけではもった
いないと、立寄ったのが諸戸家住宅で、建物の立派なのと隣接したレストランのフランス料理が安くうまかったので、
治療終了日に、妻を誘った。 まず、桑名城跡と七里の渡し跡を訪れ、その足で諸戸家住宅へ。 諸戸家は、明治時代に財
をなした実業家で、その家は六華苑と呼ばれ、洋館に和風の建物が隣接し、日本庭園がある。 富豪の家とはこういうものだ
、と思わせる家である。 フランス料理で、腹を充たし、長島のジャズドリームに向かう。 ほぼ一周した後、結婚記念日の
プレゼントとして、彼女が気に入ったハンドバックを購入した。 夕方には間があったが、なばなの里へ行く。
電飾が灯るには早いが、ベコニアガーデンに案内すればよい、と思ったからである。 花の最盛期には早いようで、
水の中に浮かんでいた花数は少なかった。 秋の夜の訪れは早く、待っているうち、薄暗くなり、イルミネーションが始
まった。
桑名の先にある歯医者に歯の治療で、通うようになったため、高速を使い、都合10回程通った。 ただ通うだけではもった
いないと、立寄ったのが諸戸家住宅で、建物の立派なのと隣接したレストランのフランス料理が安くうまかったので、
治療終了日に、妻を誘った。 まず、桑名城跡と七里の渡し跡を訪れ、その足で諸戸家住宅へ。 諸戸家は、明治時代に財
をなした実業家で、その家は六華苑と呼ばれ、洋館に和風の建物が隣接し、日本庭園がある。 富豪の家とはこういうものだ
、と思わせる家である。 フランス料理で、腹を充たし、長島のジャズドリームに向かう。 ほぼ一周した後、結婚記念日の
プレゼントとして、彼女が気に入ったハンドバックを購入した。 夕方には間があったが、なばなの里へ行く。
電飾が灯るには早いが、ベコニアガーデンに案内すればよい、と思ったからである。 花の最盛期には早いようで、
水の中に浮かんでいた花数は少なかった。 秋の夜の訪れは早く、待っているうち、薄暗くなり、イルミネーションが始
まった。  江戸時代の名古屋は 尾張徳川家が居城する城下町であるが、東海道は熱田神宮がある宮宿から桑名に舟で
渡っていったので、名古屋は通過しなかった。 今は宮宿だったところも名古屋市なので、少し変に感じる
が、別の町だったのである。 とはいえ、熱田から中山道の垂井宿を結ぶ美濃路は名古屋を通っていて、
名古屋城の周りをぐるーと回るような道筋になっていた。
江戸時代の名古屋は 尾張徳川家が居城する城下町であるが、東海道は熱田神宮がある宮宿から桑名に舟で
渡っていったので、名古屋は通過しなかった。 今は宮宿だったところも名古屋市なので、少し変に感じる
が、別の町だったのである。 とはいえ、熱田から中山道の垂井宿を結ぶ美濃路は名古屋を通っていて、
名古屋城の周りをぐるーと回るような道筋になっていた。  三十数年振りに浄瑠璃寺を訪れた。 子供は幼い時で、義母を京都に案内した翌日、ここに来たように、記憶している。
三十年をすれば、変わるのが当たり前かも知れないが、砂利道だったところが、道が広くなり、舗装されていた。
また、売店や飲食店が出ていた。 浄瑠璃寺は、昔は多くの伽藍をようしたお寺だったようであるが、本堂と三重塔のみ
のお寺である 平安時代に、薬師如来を本尊として創建されたが、九品往生(くほんおうじょう)思想の普及
により、六十年後の嘉承二年(1107)に、九体の阿弥陀如来を安置する本堂が建立された、という。 薬師如来は、三重塔に
祀られている。 平安時代、京都には、多くの塔が建立され、百塔参りが流行した。 九体の阿弥陀仏を安置したお堂は、
三十数棟建立された、というが、九体御堂も塔も戦乱に巻き込まれ焼失してしまった。 奇跡的に残った浄瑠璃寺の九体阿
弥陀仏を拝むこと
ができ、また、本堂と三重塔の間の宝池の周りの美しい紅葉も見られ、まさに命の洗濯をした。
三十数年振りに浄瑠璃寺を訪れた。 子供は幼い時で、義母を京都に案内した翌日、ここに来たように、記憶している。
三十年をすれば、変わるのが当たり前かも知れないが、砂利道だったところが、道が広くなり、舗装されていた。
また、売店や飲食店が出ていた。 浄瑠璃寺は、昔は多くの伽藍をようしたお寺だったようであるが、本堂と三重塔のみ
のお寺である 平安時代に、薬師如来を本尊として創建されたが、九品往生(くほんおうじょう)思想の普及
により、六十年後の嘉承二年(1107)に、九体の阿弥陀如来を安置する本堂が建立された、という。 薬師如来は、三重塔に
祀られている。 平安時代、京都には、多くの塔が建立され、百塔参りが流行した。 九体の阿弥陀仏を安置したお堂は、
三十数棟建立された、というが、九体御堂も塔も戦乱に巻き込まれ焼失してしまった。 奇跡的に残った浄瑠璃寺の九体阿
弥陀仏を拝むこと
ができ、また、本堂と三重塔の間の宝池の周りの美しい紅葉も見られ、まさに命の洗濯をした。
 奈良県の秘湯である十津川温泉を訪れた帰路、旅館の人には道が狭いので、勧められないといわれたが、十津川高滝下
から下北山村に抜ける国道425号を走った。 入るとすぐ、ダンプカーが10台ほど走ってきたので、困ったと思っ
たが、彼らは慣れているので、通り抜けていった。 少し走ると、右手に滝が見えてきた。 不動滝、別名高滝で、
落差46m。 水量は少ないが、紅葉した木の間から見る滝はきれいだった (右写真)
奈良県の秘湯である十津川温泉を訪れた帰路、旅館の人には道が狭いので、勧められないといわれたが、十津川高滝下
から下北山村に抜ける国道425号を走った。 入るとすぐ、ダンプカーが10台ほど走ってきたので、困ったと思っ
たが、彼らは慣れているので、通り抜けていった。 少し走ると、右手に滝が見えてきた。 不動滝、別名高滝で、
落差46m。 水量は少ないが、紅葉した木の間から見る滝はきれいだった (右写真) 水が川の傾斜に沿って、滑り下るような滝である。 日光のの華厳の滝のような直下型の滝もよいが、竜頭の滝のような
滑滝は安定感があり、好きである (右写真)
水が川の傾斜に沿って、滑り下るような滝である。 日光のの華厳の滝のような直下型の滝もよいが、竜頭の滝のような
滑滝は安定感があり、好きである (右写真) この後、国道425号はぐんぐん高度を上げながら、大峯山の山並みに沿って北上する。 左側は
白谷渓谷に落ち込む崖で、駐車する場所もないため、車を進めるしかない。
この後、国道425号はぐんぐん高度を上げながら、大峯山の山並みに沿って北上する。 左側は
白谷渓谷に落ち込む崖で、駐車する場所もないため、車を進めるしかない。  木曽三川公園は、1987年10月に開設された、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)下流域一帯、愛知、岐阜、三重の三県に
わたる、日本最大級の国営公園である。 小生が訪れたのは、その中で一番古い木曽三川公園センター(岐阜県海津市)で、
そこには展望塔のある水と緑の館と 花壇、そして、輪中の農家である水屋が再現されている。 一眼レフのカメラを買い、
本格的に写真を撮り始めた時、妻に教えられて、コスモスを写しに訪れたことがあった。 桑名に歯を直すため、通う
ようになり、ふと思い出して、デジカメを持って、帰路立ち寄った。 コスモスが咲いていると思ったら、すでに終わって
いて、庭園には色とりどりの菊が植えられていた。 敷地の一角に、古い茅葺の民家があり、軒に長方形の形をした木製の
ものがあり、その脇にろがつけられていたが、水害時に使われる舟という。 このあたりは、輪中といわれる海抜0m地帯
で、戦前までは時々洪水で家や田畑が流されてところ、という。 隣の水屋はその時に備えた倉庫兼住宅である、とあった。
前回訪れた時には記憶にないので、最近造られたものかも知れない。
木曽三川公園は、1987年10月に開設された、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)下流域一帯、愛知、岐阜、三重の三県に
わたる、日本最大級の国営公園である。 小生が訪れたのは、その中で一番古い木曽三川公園センター(岐阜県海津市)で、
そこには展望塔のある水と緑の館と 花壇、そして、輪中の農家である水屋が再現されている。 一眼レフのカメラを買い、
本格的に写真を撮り始めた時、妻に教えられて、コスモスを写しに訪れたことがあった。 桑名に歯を直すため、通う
ようになり、ふと思い出して、デジカメを持って、帰路立ち寄った。 コスモスが咲いていると思ったら、すでに終わって
いて、庭園には色とりどりの菊が植えられていた。 敷地の一角に、古い茅葺の民家があり、軒に長方形の形をした木製の
ものがあり、その脇にろがつけられていたが、水害時に使われる舟という。 このあたりは、輪中といわれる海抜0m地帯
で、戦前までは時々洪水で家や田畑が流されてところ、という。 隣の水屋はその時に備えた倉庫兼住宅である、とあった。
前回訪れた時には記憶にないので、最近造られたものかも知れない。
 多度大社には、以前に一度だけ訪れたことがある。 義母を案内し、養老の滝を見物した帰りに立ち寄ったもので、人里
離れた田舎と思っていた。 今回、東員町から訪れると、途中に桑名市大山田団地があり、丘稜地は虫食いのような開発
させつつあるなあ、と思った。 いなべ市にトヨタ車体の工場が進出したことも、住宅需要を刺激しているのかも知れない。
道は昔のままなので、住宅地を過ぎると狭くなり、間違えたかと不安になったが、杞憂に終わった。 道路側から馬鹿
でかい鳥居が建っているが、こちらが正面なのだろうか? 突き当たりに多度大社の石段が見え、左側に売店と駐車場が
あった。 平日のせいか、神社を訪れる人はほとんどなく、売店は暇を持て余していた。 神社を参拝後、養老鉄道の
駅に向かって歩くと、柿畑があり、小鳥に食べられたのであろう柿の実があった。 この道がかっての参拝道と思われ、
鯉料理店の大黒屋や多度豆の桔梗屋の古い重厚な建物があった。
多度大社には、以前に一度だけ訪れたことがある。 義母を案内し、養老の滝を見物した帰りに立ち寄ったもので、人里
離れた田舎と思っていた。 今回、東員町から訪れると、途中に桑名市大山田団地があり、丘稜地は虫食いのような開発
させつつあるなあ、と思った。 いなべ市にトヨタ車体の工場が進出したことも、住宅需要を刺激しているのかも知れない。
道は昔のままなので、住宅地を過ぎると狭くなり、間違えたかと不安になったが、杞憂に終わった。 道路側から馬鹿
でかい鳥居が建っているが、こちらが正面なのだろうか? 突き当たりに多度大社の石段が見え、左側に売店と駐車場が
あった。 平日のせいか、神社を訪れる人はほとんどなく、売店は暇を持て余していた。 神社を参拝後、養老鉄道の
駅に向かって歩くと、柿畑があり、小鳥に食べられたのであろう柿の実があった。 この道がかっての参拝道と思われ、
鯉料理店の大黒屋や多度豆の桔梗屋の古い重厚な建物があった。
 江戸時代幕末に起きた寺田屋事件の舞台になった寺田屋に行ってきた。 寺田屋は京都郊外の伏見区にあり、
江戸時代には京と浪速を結ぶ川運の宿場だった、という。 寺田屋事件は、坂本龍馬襲撃事件と思っていたが、
その他にも、文久二年(1862)、当時薩摩藩の定宿だった寺田屋に、薩摩藩の過激派と尊王派が集まり、京都
所司代などを討とうと謀議しているところに薩摩藩から派遣された藩士達が訪れ、小競り合いが起き、七人の
死者を出した事件もあったようで、一階の奥まった部屋がその場所と書かれていた。 坂本龍馬襲撃事件は、
慶応二年(1866)、伏見奉行配下の捕り方が宿泊中の坂本龍馬を捕縛もしくは暗殺しようとした事件である。
入浴中の寺田屋の養女、お龍が、異常を察して、龍馬に知らせ、お龍は薩摩屋敷に駆けこんで、知らせたと
いう。 寺田屋にはその際出来た柱の刀傷とお龍が入ったという風呂を写真に収めたが、最近読んだ新聞
には、寺田屋は明治の後期に再建されたもので、刀傷や風呂は存在しないはずとあった。 それが本当なら
ぺてんということのなるが・・・・
江戸時代幕末に起きた寺田屋事件の舞台になった寺田屋に行ってきた。 寺田屋は京都郊外の伏見区にあり、
江戸時代には京と浪速を結ぶ川運の宿場だった、という。 寺田屋事件は、坂本龍馬襲撃事件と思っていたが、
その他にも、文久二年(1862)、当時薩摩藩の定宿だった寺田屋に、薩摩藩の過激派と尊王派が集まり、京都
所司代などを討とうと謀議しているところに薩摩藩から派遣された藩士達が訪れ、小競り合いが起き、七人の
死者を出した事件もあったようで、一階の奥まった部屋がその場所と書かれていた。 坂本龍馬襲撃事件は、
慶応二年(1866)、伏見奉行配下の捕り方が宿泊中の坂本龍馬を捕縛もしくは暗殺しようとした事件である。
入浴中の寺田屋の養女、お龍が、異常を察して、龍馬に知らせ、お龍は薩摩屋敷に駆けこんで、知らせたと
いう。 寺田屋にはその際出来た柱の刀傷とお龍が入ったという風呂を写真に収めたが、最近読んだ新聞
には、寺田屋は明治の後期に再建されたもので、刀傷や風呂は存在しないはずとあった。 それが本当なら
ぺてんということのなるが・・・・
 信長の築いた安土城跡を探索した後、近江商人の町として発展した近江八幡市を訪れた。 八幡堀の近くには、
今でも当時の面影を留める屋敷が残っている。 この町を開いたのは、豊臣秀吉の甥、豊臣秀次である。
秀次は近江四十三万石を与えられて、琵琶湖に臨む標高286mの八幡山に築城し、安土城下から多くの住民を
移住させ、城下町を造った。 その時、琵琶湖から水を引いて造られたのが八幡堀で、城の堀の他、運河の役目
を果たし、商業の発展に寄与した。 秀次が尾張清洲に移ると、京極高次が八幡城主になったが、彼も大津城に
移ると、八幡城は廃城となった。 この年、皮肉にも豊臣秀次は秀吉の逆鱗に触れ、高野山で切腹。 城に上る
と石垣だけが残り、石に蔦がからんでいた。 秀頼が生まれたことで、殺された秀次の無念を感じた。 城上
から、彼が築いた碁盤模様の町並みを眺めながら、そう思った。
信長の築いた安土城跡を探索した後、近江商人の町として発展した近江八幡市を訪れた。 八幡堀の近くには、
今でも当時の面影を留める屋敷が残っている。 この町を開いたのは、豊臣秀吉の甥、豊臣秀次である。
秀次は近江四十三万石を与えられて、琵琶湖に臨む標高286mの八幡山に築城し、安土城下から多くの住民を
移住させ、城下町を造った。 その時、琵琶湖から水を引いて造られたのが八幡堀で、城の堀の他、運河の役目
を果たし、商業の発展に寄与した。 秀次が尾張清洲に移ると、京極高次が八幡城主になったが、彼も大津城に
移ると、八幡城は廃城となった。 この年、皮肉にも豊臣秀次は秀吉の逆鱗に触れ、高野山で切腹。 城に上る
と石垣だけが残り、石に蔦がからんでいた。 秀頼が生まれたことで、殺された秀次の無念を感じた。 城上
から、彼が築いた碁盤模様の町並みを眺めながら、そう思った。  飛騨トンネル開通記念! 日帰りで行く立山・室堂ハイキングの旅行社の案内を見て、立山に日帰りで行ける
ならと申しこんだ。 どんなコースとか所要時間などを確認せずに・・・・
飛騨トンネル開通記念! 日帰りで行く立山・室堂ハイキングの旅行社の案内を見て、立山に日帰りで行ける
ならと申しこんだ。 どんなコースとか所要時間などを確認せずに・・・・ 醒ヶ井には、二年前の平成18年3月に中山道を歩いた時、訪れた。 醒ケ井の名は、日本書紀の 「 日本武尊
(やまとたけるのみこと) 、伊吹山にて大蛇をふみて、山中の雲霧にあい給ひ、御心地なやましたりしが、此水を
のみて醒めたまひぬとなん 」 に因むものである。 加茂神社前の池には、底からこんこんと清水が湧き出ているのが、
日本武尊を蘇生させた」という居醒(いすい)の清水である。 木曾路名所図会 に、「 此駅に三水四石の名所あり、
町中に流れありて至て清し、寒暑にも増減なし 」 とあるが、今も変わらず流れ出ていた。 ここは、清流に
しか育たないとされる梅花藻の貴重な繁殖地とされる。 かって通った日光の大谷川にもあったのだが、そのような
珍しいものと思わず、愛知に戻ってきていた。 その花が咲くのがこの時期なので、どのような花か?興味があった。
梅花藻は水の中に流れに任せているのだが、花が咲くに比例して、水の上に出てくることを始めて知った。
醒ヶ井には、二年前の平成18年3月に中山道を歩いた時、訪れた。 醒ケ井の名は、日本書紀の 「 日本武尊
(やまとたけるのみこと) 、伊吹山にて大蛇をふみて、山中の雲霧にあい給ひ、御心地なやましたりしが、此水を
のみて醒めたまひぬとなん 」 に因むものである。 加茂神社前の池には、底からこんこんと清水が湧き出ているのが、
日本武尊を蘇生させた」という居醒(いすい)の清水である。 木曾路名所図会 に、「 此駅に三水四石の名所あり、
町中に流れありて至て清し、寒暑にも増減なし 」 とあるが、今も変わらず流れ出ていた。 ここは、清流に
しか育たないとされる梅花藻の貴重な繁殖地とされる。 かって通った日光の大谷川にもあったのだが、そのような
珍しいものと思わず、愛知に戻ってきていた。 その花が咲くのがこの時期なので、どのような花か?興味があった。
梅花藻は水の中に流れに任せているのだが、花が咲くに比例して、水の上に出てくることを始めて知った。  蓮の花は暑いところがよいのだろうか? 仏教では、お釈迦様と蓮花はセットになっている。 京都や滋賀の寺には
夏になると、水盤に植えられた蓮の花を多く見る。 その代表が、宇治の三室戸寺である。 昔はなかったので、
最近になって始めたように思われるが、これはこれで身近に花を鑑賞できるので、これはこれでよいと思う。 自然の
蓮を撮りたいと思っていたところ、写真倶楽部で草津市立水生植物園に行くというので、参加をした。 行ってみて
分かったのであるが、ここは琵琶湖の東側の烏丸半島に広がるところにあり、広大な敷地に蓮が自生しているのである。
撮影とか、鑑賞用に通路や橋が架けられている訳でもないので、撮影には不向きだった。 園内のスイレンは身近に
撮影できるポイントがあるので、よかったが・・・・
蓮の花は暑いところがよいのだろうか? 仏教では、お釈迦様と蓮花はセットになっている。 京都や滋賀の寺には
夏になると、水盤に植えられた蓮の花を多く見る。 その代表が、宇治の三室戸寺である。 昔はなかったので、
最近になって始めたように思われるが、これはこれで身近に花を鑑賞できるので、これはこれでよいと思う。 自然の
蓮を撮りたいと思っていたところ、写真倶楽部で草津市立水生植物園に行くというので、参加をした。 行ってみて
分かったのであるが、ここは琵琶湖の東側の烏丸半島に広がるところにあり、広大な敷地に蓮が自生しているのである。
撮影とか、鑑賞用に通路や橋が架けられている訳でもないので、撮影には不向きだった。 園内のスイレンは身近に
撮影できるポイントがあるので、よかったが・・・・
 滋賀県の桜の名所として有名なのが、海津大崎の桜である。
滋賀県の桜の名所として有名なのが、海津大崎の桜である。  樹齢千八百年から二千年と推定される日本最古の桜で、三春の滝桜、根尾薄墨桜と共に、三大桜といわれる。
神代桜の名は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が、東征の帰途に植えたという伝承による。 根回りは13.5m、
目通り幹囲は11mで、幹の太さは日本最大だが、長い悠遠の歳月を経てるうち、主幹上部は完全に失われ、
主幹の高さはわずか2.4mで、基幹は北側の一部を残すのみで、空洞になっている。 なお、大正十一年に
国の天然記念物に指定された。 主幹の上に被せていた屋根を取り除いたところ、樹勢が回復して、今年の花は
最高と地元の人の言である。 黒い幹は太く、この桜の生命力を感じたので、それを表現しようと写した。
当日は1日中雨だったが、それでも多くの人を集めていた。
樹齢千八百年から二千年と推定される日本最古の桜で、三春の滝桜、根尾薄墨桜と共に、三大桜といわれる。
神代桜の名は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が、東征の帰途に植えたという伝承による。 根回りは13.5m、
目通り幹囲は11mで、幹の太さは日本最大だが、長い悠遠の歳月を経てるうち、主幹上部は完全に失われ、
主幹の高さはわずか2.4mで、基幹は北側の一部を残すのみで、空洞になっている。 なお、大正十一年に
国の天然記念物に指定された。 主幹の上に被せていた屋根を取り除いたところ、樹勢が回復して、今年の花は
最高と地元の人の言である。 黒い幹は太く、この桜の生命力を感じたので、それを表現しようと写した。
当日は1日中雨だったが、それでも多くの人を集めていた。
 小田原藩主、稲葉家の菩提寺だった長興山紹太寺があった所に咲くシダレザクラ(イトザクラ)!
稲葉正則が祖母の春日の局を供養するために植えたといわれており、幹周りは約3m80cm、高さ約13m、
枝張りは12m〜13m、とある。 推定樹齢は約330年で、大小の二段傘のような樹形になっていた。
場所 小田急箱根鉄道線入生田駅から北方向に一キロほど離れた場所。 旧東海道沿いにある現在の紹太寺の
前を通って、坂道や石段を歩いて山を登っていくと桜に出会える。
駐車場がないので、電車で行くのが一番である。
小田原藩主、稲葉家の菩提寺だった長興山紹太寺があった所に咲くシダレザクラ(イトザクラ)!
稲葉正則が祖母の春日の局を供養するために植えたといわれており、幹周りは約3m80cm、高さ約13m、
枝張りは12m〜13m、とある。 推定樹齢は約330年で、大小の二段傘のような樹形になっていた。
場所 小田急箱根鉄道線入生田駅から北方向に一キロほど離れた場所。 旧東海道沿いにある現在の紹太寺の
前を通って、坂道や石段を歩いて山を登っていくと桜に出会える。
駐車場がないので、電車で行くのが一番である。