品川宿から川崎宿
 |
{左}品川寺の常夜燈 東海道の青物横丁交差点から出発。 青物横丁は、近郊の農家が青物(野菜類)を運んで来て、市場が開かれたので、その名が付いたところである。 この交差点は、池上本門寺への参詣道である池上街道の追分(分岐点)であった。 その先の右側の山門前の常夜燈は、下から亀が支えているデザインで、門の前の提灯には、品川寺(ほんせんじ)と、書かれていた。 品川寺は、大同年間(806〜810)に、弘法大師空海が開山した、と伝わる寺で、長禄年間(1457〜 |
 |
{左}品川寺の六地蔵
1459)に、太田道灌が創建し、承応年間(1652〜1654)、弘尊上人の中興により、品川観音として信仰を集めるようになった、といわれる。 山門を入った左側に、大きな地蔵菩薩が鎭坐している。 江戸に出入りする六街道に安置された江戸六地蔵の一つで、中山道では巣鴨、日光街道では千住、東海道ではここなど、六ケ所におかれた。 境内には、樹齢六百年という大イチョウがあるが、幹回りが5.35mで、樹高は25mもある古木である。 |
 |
{左}海 雲 寺 イチョウの下には、道しるべ、道祖神と刻まれた石柱、小さなものと大きな庚申塔が建っている。 道の右側に、平蔵地蔵が祀られている海雲寺がある。 言い伝えでは、「 昔、鈴ヶ森刑場の番人をしていた乞食が三人いたが、その一人の平蔵が財布を拾い、持ち主を探してこれを返したが、礼金を受け取らなかった。 これを知った残りの二人は、これを怒り、平蔵を小屋から |
 |
{左}力 石
追い出して、凍死させてしまった。 財布を返してもらった仙台藩士は、これを知り、平蔵の遺体を引き取り、供養するために地蔵を造った。 」 と、いうものである。 平蔵地蔵は、以前は街道にあったが、道路の拡張でこの寺に移されたのである。 常夜燈の前に、力石と刻まれた石がある。 当時は、この門前近くに、漁師や親船から積荷を小舟に移す沖取りという沖仲止がいて、この石を何回持ち上げられるかなどを競っていた、という。 |
 |
{左}海晏(かいあん)寺
百メートル先の横町には、海晏寺への道標が建っている。 ここを右折し、国道を渡った駅の反対側に、寺がある。 鎌倉時代の北条時頼が創建した寺で、街道のあたり一帯までが境内だった、という大きな寺であった。 本尊は、門前の海でとれた大きなサメの腹から出た、と伝えられる聖観音である。 寺の右側奥には、幕末に活躍した松平春嶽の墓がある。 |
 |
{左}鮫頭(さめづ)商店街
街道を進むと、古い家の格子の前のコンクリートの上に、、日本橋講、和合講と書かれた石柱があった。 立場茶屋の釜屋があったのは、このあたりだろうか? 東大井1丁目に入ると、商店街も鮫頭商店街に変った。 昔の大井村、御林町(おはやしまち)で、俗に、鮫頭と呼ばれていた所である。 江戸時代には、漁師町で、将軍家に新鮮な魚介類を献上する御菜肴八ヶ浦のひとつになっていた。 |
 |
{左}八幡神社 交差点を右折し、京急鮫洲駅方面に向かい、ミニストップで左折すると、右側に、八幡神社がある。 昔は、御林八幡宮と称せられていた神社で、品川沖でとれた鮫の腹から正観音像が出て、これを本尊にしたのが海晏寺で、その鮫の頭を祀ったのが、この神社だと、伝えられている。 創祀の時期ははっきりしないが、寛文年間(1661〜1672)の御林町誕生のころと思われる。 社殿は、昭和四十七年(1972)に建直されているが、その前の狛犬は、町内猟師中と彫 |
 |
{左}涙橋(浜川橋)
られた漁師の寄進によるもので、嘉永弐年(1849)に造立、常夜燈は、安政三年(1856)に造られたものである。 鮫洲から八百メートル程歩くと、立会川に架かる浜川橋を渡る。 橋のたもとの案内板には、「 立会川が海に注ぐこのあたりの地名から名付けられた橋で、またの名を涙橋という。 この先に、慶安四年(1651)、仕置き場(鈴ヶ森刑場)が設けられ、処刑される罪人は |
 |
{左}鈴ヶ森刑場跡 裸馬に乗せられて、江戸から護送されてきた。 その時、親族らはひそかに見送りにきて、この橋で共に涙を流しながら、別れたことから、涙橋とも呼ばれた。 」 と、ある。 泣く子も黙るといわれた鈴ヶ森刑場跡は、その先の大経寺の境内にある。 大経寺から第一京浜に合流するあたり一帯が鈴ヶ森刑場の仕置き場で、敷地面積は、間口四十間(74m)、奥行九間(16.2m)、明治三年(1870)に廃止されるまでに、丸橋忠弥や八百屋お七、白井権八、ねずみ小僧、 |
 |
{左}髭題目碑
天一坊などが処刑された。 第一京浜に合流する三角形の土地に、いくつもの供養塔が建ち、火焙りや磔に使用した台石、首洗い井戸などがある。 その中で、特に大きい供養塔は、京都の谷口法悦という日蓮宗徒が、京都から江戸北方 の千住にかけての刑場に、受刑者供養のため建てた供養塔の1つで、髭題目碑といわれるもので、歌舞伎の舞台にも登場する。 |
 |
{左}京急大森海岸駅
ここで再び第一京浜と合流する。 国道に合流し少し進むと、鈴ヶ森入口交差点の左側に、品川水族館に入る入口があるが、国道の左手は、南北に、しながわ区民公園が続いている。 右手に京急大森海岸駅。 大森は海苔の産地だったが、埋め立てですっかり姿を消した。 ここから二つ目の信号、平和島口交差点を越えると、左に入る一方通行の細い道が東海道である。 左に大森スポーツセンター、その先の右側に美原不動尊がある。 |
 |
{左}梅屋敷跡
環七を越えると、美原通り交差点があり、商店街になっている。 橋を渡ると大森警察署前交差点に出て、第一京浜と、また、合流。 この間、九百メートルほどである。 八百メートル程先に、梅屋敷駅入口交差点があるが、その先の右側に、梅屋敷公園があり、門の前に明治天皇行在所梅屋敷の石柱が建っている。 江戸時代の道中常備薬・和中散を販売していた久三郎が、庭園に梅の名木を集め、休み茶屋を開いたところ、蒲田の梅屋敷として有名になり、 |
 |
{左}羽田空港線の踏み切り 広重の浮世絵にも描かれたという、梅の名所だったところである。 梅屋敷と思える ものは一つもなかったが、里程標が復元されていて、 距日本橋三里十八丁 蒲田村 山本屋 と、書かれていた。 その先にある京急蒲田駅は、高架化工事中。 国道を横切る形の踏切があり、京急蒲田駅から羽田空港まで行く電車が国道を横切っていった。 正月の箱根駅伝のテレビ中継でしばしば登場する踏切であるが、工事が終わると、高架化されるので、この踏切もなくなり、 |
 |
{左}六郷神社 正月の風物詩の一つが消える。 蒲田消防署を過ぎると、仲六郷、東六郷を経て 、京急雑色駅前にきた。 この間、二キロ程? 道の左側に、雑色アーケードがあり、ジャンボサガンという大きなビルがあった。 東六郷三丁目交差点を過ぎ、左に入ったところに六郷神社がある。 天喜五年(1057)、源頼義、義家親子が石清水八幡の分霊を勧請し創建、鎌倉幕府を開いた源頼朝が、梶原景時に命じて、建久弐年(1191)、社殿を造営した、と伝えられる神社である。 |
 |
{左}六郷橋の標柱
鳥居前にある太鼓橋は、その時、梶原景時が寄進したもの、といわれる。 境内の一対の狛犬は、独特な風貌がおもしろい。 六郷中町が寄進したもので、貞享弐年(1685)の作で、区内で一番古い狛犬である。 六郷橋の標柱も保存されていた。 国道を歩いて行くと、六郷北詰交差点で、車道は上り坂に、道の右側に宝珠院、左手に観乗寺がある。 歩道をそのまま進むと、 |
 |
{左}新六郷橋
六郷土手交差点にでた。 東海道は、左右の道路を横切り、行き止まりになる階段を昇る。 ここが東京都のはずれで、多摩川には新六郷橋が架かっていた。 徳川家康は、慶長五年(1600)、東海道の多摩川を越える六郷に橋を架けさせた。 その後、何度か橋は架け直されたが、貞享元年の橋が、貞享五年/元禄元年(1688)に洪水で流失以後は、橋は再建されず、かわりに六郷の渡しが設けられたのである。 |
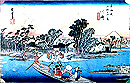 |
{左}浮世絵・川崎宿
江戸時代の旅人は、六郷の渡しに十三文を払い、橋から三十メートル下流から渡し舟に乗った。 渡しは、当初、江戸の町人が請け負ったが、宝永六年(1709)三月、川崎宿が請け負うことになり、これによる収入が川崎宿の財政を大きく支えたのである。 現在は渡しがないので、橋を渡るが、渡り終えると、川崎宿である。 |
 |
{左}明治天皇六郷渡し記念碑 橋を渡り、道から左に少し入ったところに、赤茶色の記念碑がある。 明治元年(1868)十月十二日、明治天皇が東征の折、六郷渡しを渡御された記念碑 で、それに埋め込まれた 「 武州六郷船渡図 」 のレリーフには、二十三艘でつくられた舟橋の上を、官軍が威風堂々と歩いて渡っていく姿が描かれていた。 両川岸から船を縄でつなぎ合わせ、船の上には砂か土を |
 |
{左}六郷の渡し跡
盛り、その上を多くの兵が長々と続く姿は絵になっただろうとし、これだけでも明治天皇の存在を高める効果があったように思われる。 この碑のある下手の土手下に、当時の渡しがあったと推定されるが、その痕跡は、見当たらない。 係留されたボートに、往時を連想するのみである。 明治天皇東征記念碑の先には、江戸時代に大変人気があり、多くの参拝者を集めた川崎 |
 |
{左}旧東海道の石柱 大師の献灯籠があった。 江戸時代、船着場から土手をあがった旅人は、現在の第一京浜(国道15号)を横切って、宿場内へ入ることとなる。 国道の右手にある道に入ると、道の左側に旧東海道の石柱が建っていた。 天保十四年の川崎宿の人口は二千四百三十三人、家数は五百四十一軒、本陣は二軒、旅籠は七十二軒となっていた。 |
 |
{左}奈良茶飯の万年屋跡
右側の緑灰色のビルの前に、旅籠兼茶屋の万年屋跡の案内板があった。 幕末のはやり唄に、 「 川崎宿で名高い家は、万年、新田屋、会津屋、藤屋、小土呂じゃ小宮・・ 」 なかでも、万年屋と奈良茶飯が有名だった、とある。 奈良茶飯とは、大豆、小豆、粟、栗などをお茶の煎じ汁で炊き込んだ飯で、これに多摩川でとれたシジミの味噌汁がついていた。 旅の疲れを |
 |
{左}稲荷横丁の石柱 回復する滋養のある食べものとして、全国に名を馳せた奈良茶飯だが、渡しの消滅と共に、万年屋は消滅し、奈良茶飯を食べさせる店は現在一軒も残っていない。 少し行くと、本町交差点で、国道409号(大師通り)と交差するが、その右手前にある小路との間に、旧東海道と稲荷横丁の石柱が建っている。 傍らの案内板には、このあたりは、新宿と呼ばれた、とあり、東海道 |
 |
{左}川崎稲荷社
には、馬の水飲み場があったようである。 道の反対に、弘法大師への道の道標が立っている。 手前の小路を左折して、少し行くと、道の左側に、八代将軍、徳川吉宗が、紀州から江戸城入りの際、ここで休息した、と伝わる川崎稲荷社がある。 前の道は稲荷横丁と呼ばれ、その先に大師用水に架かる石橋があり、府中道に合流していた。 街道に戻り、本町交差点を |
 |
{左}田中本陣跡
越えて、直進する。 本町一丁目交差点を越えた右側にも、旧東海道の石柱があった。 その先の右側にある深瀬小児科医院が、二軒あった本陣の一軒、江戸側にあったので、下の本陣ともいわれた田中本陣があったところである。 明治元年(1868)、明治天皇が東幸の際、田中本陣で昼食を召され、休息をとられた、という記録がある。 宝永元年( 1704)、本陣(名主)職を継いだ田中休愚(兵庫)は、幕府と交渉し、六郷の渡しの請負に成功し、伝馬役で疲弊して |
 |
{左}宗三寺
いた川崎宿の財政を建て直し、享保改革を進める吉宗に認められて、幕府の勘定格代官になった。 幾つかの交差点を越えると、右手奥に、宗三寺という寺がある。 鎌倉時代の初期に、僧玄統が開いた古刹で、後に、宇治川の先陣で名高い佐々木高綱がこの辺を領した時の菩提寺でもあった、といい、江戸名所図会には、 「 本尊釈迦如来は1尺ばかりの唐仏なり 」 と紹介 |
 |
{左}遊女の供養塔 されている。 宝暦十一年(1761)の大火で、小土呂から六郷渡しまでの町並が、ほぼ全焼し、宗三寺も焼けた、とある。 墓地の一番奥に、川崎宿貸座敷組合が建てた遊女の供養塔が建っていた。 砂子一丁目の交差点の手前右側に、旧東海道の石柱と川崎宿の大きな案内板があった。 案内板の場所が、幕末以前に廃業になった、中の本陣と呼ばれた惣兵衛本陣の跡である。 本陣の前には、高札場があり、道路の反対側にあるセブンイレブンあたりに、問屋場が |
 |
{左}詩人・佐藤惣之助(そうのすけ)の石碑 あった、とされる。 その先の砂子交差点は、左右に道幅が広い市役所通りが通り、右折すると、JR川崎駅である。 道を横断した先には、大きなビルが並んでいたが、左側の川崎信金本店の一角には、詩人、佐藤惣之助の石碑がある。 佐藤惣之助は、江戸時代に上の本陣といわれた佐藤本陣の後裔である。 本陣があった場所は、道の向かい側の三菱UFJ信託銀行が入っているビル辺りだろう。 |
 |
{左}小土呂橋の擬宝珠(ぎぼうし)
新川通りを横断すると、道の右手に、小土呂橋の擬宝珠が保存されている。 小土呂橋は、東海道と幅五メートルの新川掘が交差する地点にあった石橋で、川が暗渠になり、橋が撤去された際、二基の擬宝珠を地元の自治会がここに設置したものである。 小川町に入り、キングスホテルの先の交差点を右折すると、教安寺がある。 境内には、江戸時代に鋳造された梵鐘 |
 |
{左}教安寺(きょうあんじ)の徳本上人六字名号碑
や、当時熱狂的に信者の信仰を集めた徳本上人の六字名号碑があった。 門前の左側の石燈籠は、上手土居(かみてどい)から移転したものである。 富士山に彌勒の浄土を求めた庶民信仰の富士講は、幕末の不安な風潮を背景として、関東一円で爆発的な流行をみたが、この石燈籠は、富士講のなかのタテカワ講によって、建立されたものである。 |
 |
{左}馬嶋病院の芭蕉弟子達の句碑
街道に戻り、二百メートル歩くと、市電通りと交わる交差点で、これを越えて百メートル行くと、右側に、馬嶋病院が経営する老人ホームがある。 更に、少し歩くと、左側に大きなビルの馬嶋病院があり、土居にあったとされる芭蕉句碑がここにあったことが書かれていて、芭蕉と別れた弟子達の句が表示されていた。 京側の入口の土居の位置は旧馬嶋病院なのか、新馬嶋病院のところなのか、確認できなかったが、どちらにしても、川崎宿はこのあたりまでだったのだろう。 |