藤沢宿から平塚宿
 |
{左}引地橋 小田急江の島線藤沢本町駅が右に見える陸橋を越えると、藤沢宿は終りである。 右手の緑豊富な小高い山は伊勢山で、その一部が伊勢山公園になっている。 湘南高校交差点を過ぎると、鵠沼(つげぬま)神明である。 伊勢山が終りになるところに、引地川が流れている。 川に架かる引地橋を渡ると、羽島地区である。 スーパーのそうてつローゼンを越えると、引地坂と呼ばれる上り坂になった。 上って行くと、道はカーブし、右側に、大きな何連かのタンクが |
 |
{左}おしゃれ地蔵 見えてきた。 メルシャンワインの工場である。 坂の途中の左側の道端に、おしゃれ地蔵と地元で呼んでいる小さな祠があった。 かたわらの説明には、 女性の願い事なら、何でもかなえて下さり、満願のあかつきには、白粉を塗ってお礼を する と、伝えられているものだが、実際は地蔵ではなく、道祖神(双体道祖神)だろう、 と記されていた。 メルシャンの工場正門前には石仏が祀られていた。 坂もここで終り、平坦になった。 |
 |
{左}四ッ谷交差点 羽島交差点は左の道を行く。 その先の三叉路は、右折は、県道43号で厚木、用田方面へ、旧東海道は44号である。 そこから少し歩くと、四ッ谷信号交差点で、右折して行くと、新湘南バイパス藤沢ICの入口にでる。 広い国道1号線を横切り、向こう側に渡ると、正面にある新聞販売店の左側に狭い道がある。 |
 |
{左}大山道の道標 江戸時代の大山道であるが、国道との間の狭い土地に、石の道標とお堂が建っている。 お堂の中には、大山道の道標を兼ねた不動明王が祀られていた。 延宝四年(1676)、江戸横山町の講中が、東海道と大山道が交差する四谷辻に建てたもので、大山不動尊の下の正面に、 「 大山道 」 、両側面には、 「 これより大山みち 」 と、刻まれている。 片足をぶらんと下げ、眼をひん剥いてこっちを睨んで座っている不動明王は、四谷不動と呼ばれている、と、傍らの案内板にあった。 お堂の外にある道標が初代で、万冶四年(1661)に江戸浅草蔵前の講中に |
 |
{左}大山道鳥居 よって建てられた。 江戸時代に入ると、江戸の町人達の間に大山詣が盛んになり、落語にも登場するほどの人気で、ここ四谷辻には、多くの茶屋が立ち並び、参詣客を誘い込んでいたのである。 狭い大山道に、天狗のお面が付いた大山への鳥居が建っている。 鳥居をくぐり、車が一台だけ通れる道を歩いて行くと、右側に大庭トンネルが見える大きな道に出た。 道を横切った先には、先程と同じような狭い道が続いている。 |
 |
{左}大山道の地蔵尊 少し先の三叉路の正面に、地蔵尊が祀られている。 祠の左側には、「 市野道 地蔵も花も 笑ひけり 」という句碑があった。 二股に分かれた道は、右は大山道で、左側の道は東海道に通じているようである。 句碑に刻まれた文字が市野なのか布野なのか、迷う。 大山道はこの先続くようであるが、ここで歩くのをやめて、四谷交差点まで引きかえし、国道1号を進む。 羽鳥交番前交差点を左折すると、JR辻堂駅であるが、東海道は直進する。 |
 |
松並木と一里塚跡の木柱(右側にある) すると、少ないながら松並木が現われた。 松の木の下が歩道になっているのだが、松を保護するため、凸凹している。 右側にある一里塚跡の木柱には、江戸から十四里目の一里塚で、左に榎、右には松が植えられていた、と書かれていた。 その先の二ッ家稲荷神社の境内に、寛文十年(1670)建立の庚申供養塔があった。 現在の地名は二ツ谷だが、二つ家だったのが変化したといい、江戸時代には、二軒茶屋の立場があったところである。 |
 |
{左}常光明真言道道標
歩いて行くと、大山口交差点の両脇に、道標があった。 道より小高いところにある道標の一つは、寛保二?の年号と下が土に埋まっているが常光明の字である。 道標の常光明は、鎌倉街道の別名、常光明真言道が刻まれているようである。東海道分間延絵図には、二ツ谷木橋を渡るとすぐ左側に、寛保二壬戌之三月の供養塔の記述があるので、それだろう。 道の右側には、奉巡礼西国坂東秩父供養塔があり、是より大山道と書かれた道標で、享和三年(1803) |
 |
{左}明治天皇の小休止碑 に建てられたもの。 茅ヶ崎市に入ると、道の北側は小和田で、その先の北西は菱沼である。 このあたりの松並木は、背が高く立派である。 東小和田交差点の手前二十メートル右側の民家の前に、明治天皇の小休止碑があった。 江戸時代、藤沢宿と平塚宿との距離は十三キロ強と長かったので、間(あい)の宿として、三つの立場があった。 一つは、先程の二軒茶屋で、残りは菱沼と南湖(南郷)である。 石碑に説明がなかったので、明治天皇が休憩された家の |
 |
{左}馬頭観音
ことは分らなかったが、菱沼が立場だったことと関係があるのではないか? 道は南西に向って、続いている。 上正寺交差点の南側は、代官町、本宿町の町名が付いている。 小和田のバス停近くで、左の路地を入ると、右にカーブする突き当たりに、地蔵堂があり、その向かいには馬頭観音があった。 昔はここが東海道だったのかもしれない。 その先の信号交差点の |
 |
{左} 松並木 左手前に千手院があり、右側には広徳寺がある。 このあたりから道は右にカーブしやや上り道になる。 北側の地名も、小和田から松林に変った。 菱沼バス停の先で、道は左にカーブし、このあたりから、再び、松並木が現れた。 松林中学校交差点を越えると、本村である。 さて菱沼の立場だが、牡丹餅(ぼたんもち)を名物とした茶屋があったので、いつしか牡丹餅茶屋が立場の呼び名となった、とある。 茶屋があった位置であるが、茅ヶ崎高校のバス停付近 |
 |
{左}松並木の案内板 にあったという説があるが、菱沼とあることを考えると松林地区にあったとするのが無難だろう。 それはともかく、茅ヶ崎高校前には東海道の松並木の案内板があった。 それによると、国道1号線の黒松の中には、二メートル二十センチの高さのものがあり、四百年を経てる、とあった。 なお、安藤広重の藤沢宿松並木の絵は南湖(南郷)を描いたものである。 更に歩いて行くと、本村交差点の手前の右奥に、海前寺が見えた。 |
 |
{左}海前寺山門 道を入っていくと、海前禅寺と書かれた石柱がある山門の両脇に、仁王立ちした石仏があり、その左側に大きな灯篭がある。 徳川二代将軍秀忠の菩提のため、慶安四(1651) 久留米藩二十一万石の二代目藩主、有馬忠頼が奉納したもの、とあった。 山門をくぐって境内に入ると、本堂の左右に、供養燈篭が建っていた。 左側のずんぐり太い燈篭は、堀長門守が宝暦十一年(1761)に、第九代将軍家重の供養のため、建立したと、傍らの案内にあった。 |
 |
{左}小笠原長逵寄進の供養燈籠 堀長門守とは信濃国須坂藩1万石の藩主のことだろう。 右側の燈籠は、播磨国安志藩第二代目小笠原長逵が同じ年に建立したものである。 安志藩は、豊前中津藩主の小笠原長邑が六歳で没したため、無嗣改易となるところを名家ということで、当時五歳だった弟の長興に播磨安志1万石の名跡がゆるされたことから、誕生した藩である。 長逵はその子であるが、家名が |
 |
{左}八王子神社 維持できた将軍に感謝し、供養燈籠を寄進したものと思われる。 旧東海道は高台にあり、北側は低いため、右側を見ながら歩くと、尾根沿いの道のようである。 右下の八王子神社を見下ろすと、まさにその感を強くした。 右側にサティがあり、このあたりから道はなだらかになった。 車の往来は激しいが、歩道を覆うように松並木が続いているので、夏の暑さはしのぎやすい。 |
 |
{左}茅ヶ崎一里塚 元町に差し掛ると、道はゆるい下り坂となった。 その先の一里塚交差点の左側には、石垣が築かれ、何本かの木が植えられているところがある。 これは、江戸から十四番目の茅ヶ崎一里塚を復元したものである。 ここからJR茅ヶ崎駅へ通じる道には、一里塚通りという名称が付けられている。 また、駅に近いからか、一里塚あたりから、人が急に多くなったが、このまま東海道を歩いた。 |
 |
{左}元寛永寺の供養燈篭 駅交差点を過ぎた右側に、樹木が茂った一画があり、その中に三基の灯篭があった。 傍らの説明によると、徳川家菩提寺の上野寛永寺は戦災に遭い、その復興を援助した人達に、全国の大名が歴代将軍へ奉納した供養燈篭を贈った、とあるので、先程訪れた海前寺の燈篭も、同じ理由で、あそこにあるのだろう。 その先にひときわ目立つ高い松の木があるが、周囲のビルと比較すると十五メートルはありそうである。 |
 |
{左}第六天神社 その先左側に郵便局があり、そのあたりから緩い坂道になる。 茅ヶ崎郵便局の反対側には、背の高い松が見下ろすような姿で立っている。 びっくりドンキーの前にも松の木があった。 十間坂交差点を過ぎると、少し上り坂になったが、これが十間坂である。 十間坂2交差点を越えた、右側にある神社は第六天神社で、祭神は、於母陀琉神(おもだたがみ)と妹阿夜詞志泥神(いもあやかしこねのかみ)である。 神社の由緒には、元弘三年の新田義貞の鎌倉攻めで |
 |
{左}南湖立場跡 兵火にあった、と伝えられる古い神社で、於母陀琉神は天地創造の神で、天神七代の第六代目の神であると、書かれていた。 道は下りになり、南湖入口交差点を過ぎると茶屋町郵便局があり、左側に古るそうな家が一軒があった。 。 茶屋町とあるのは、藤沢宿から平塚宿の間にあった間の宿の一つで、南湖の立場は茶屋町と称せられた程の大きな立場だったのである。 茅ヶ崎高校前の東海道の松並木の案内板にあった、広重の松並木の風景はこのあたりと、 |
 | {左}南湖の左富士之碑 思えるが、松の木は一本も残っていない。 道は左にカーブし、カーブを曲がりきると少し上りとなり、その上に千川が流れ、鳥井戸橋が架かっている。 千川はそれ程大きな川ではないが、橋を渡ると、橋のたもとの左側に、南湖の左富士之碑が建っていた。 このあたりは、北西に道が続くので、左側に富士山が見えたのである。 富士山がある方向には民家があるので、今でも見えるのか、当日は曇っていたこともあり、確認できなかった。 |
 |
{左} 弁慶塚 道の反対側の赤い鳥居は、ここから約一キロ北方にある鶴嶺八幡宮の鳥居である。 鳥居をくぐると、右側の民家の中庭に弁慶塚がある。 弁慶塚は、武蔵国稲毛の領主、稲毛三郎重成が、亡妻の供養のため、相模川に橋を架け、文久九年十二月、落成供養を行なった際、参列した源頼朝は、その帰途、鶴嶺八幡 宮付近に差し掛かったとき、義経、行家等の亡霊が現れ、頼朝は落馬し、重傷を負い、翌、正治元年に亡くなった。 後年、里人は義経一族の霊を慰める |
 |
{左}神明神社 ため、塚を築いた、と伝えられるものである。 街道に戻り、松並木が残っている道を歩く。 橋から三百メートル程歩くと、新湘南バイパス 茅ヶ崎西 300m という標識が現れた。 ここから道は大きく左にカーブするが、その先の左側に、神明神社があり、本堂には、龍の彫刻が施されていた。 境内の左側には、厄神大権現とある大きな石碑と祠の中に、道祖神など、三体の石仏が祀られていた。 道はこの先、左に大きくカーブし、傾斜のある上り坂になった。 |
 |
{左}道祖神碑と道祖神像
坂の左側に、東海道の名物まんじゅう でかまん、という看板を掲げたお菓子屋があった。 新湘南バイパスの下に流れる川は、小出(こいで)川で、それ程大きな川ではないが、川に架かる下町谷橋を渡ると、左側に松の木があった。 その先の今宿バス停の道の右側には上国寺という日蓮宗のお寺があり、その先の下の川入口交差点の先には、信隆寺がある。 産業道路を越えると、新田交差点の手前右側に、道祖神碑と道祖神像が小さな祠の中に祀られていたが、気を付けないと、通り過ぎるところだった。 |
 |
{左}馬入橋 道を上って行くと、相模川で、馬入橋という大きな橋が架かっている。 江戸時代には、相模川には橋を架けることは幕府により禁止されたので、馬入の渡しにより、川を渡った。 「 舟着場は中島村と対岸の馬入村にあったが、川会所と川高札場は馬入村にあった。 川会所には、川名主三人、川年寄三人が勤務し、船頭は昼夜を問わず十六人が待機していた。 また、寛永十一年(1634)の三代将軍家光の上洛時と慶応元年の十四代将軍家茂の長州征伐に際しては、舟橋を架けられた。 」 、と案内板にあった。 馬入橋を渡ると陸軍架橋記念碑があり、大正 |
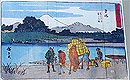 | {左}安藤広重の平塚宿の馬入川舟渡りの絵 時代に陸軍の手で橋が架けられたことが分かる。 ここから平塚市。 左側の工事中のビルの塀には、広重の平塚宿の馬入川舟渡りの絵が描かれていた。 二百メートル先の馬入交差点で、国道1号線は右折して分かれていくが、旧東海道はそのまま直進する。 このあたりに一里塚があったはずだが、どこにあったのか確認できなかった。 |
 | {左}蔵屋敷バス停付近 国道129号線を渡った、蔵屋敷バス停あたりが馬入村の西の外れである。 江戸時代には、このあたりから、新宿まで松並木が続いた。 平塚は戦時中、戦災に遭っているので、現在ある松並木は最近のものだろうか? 松原バス停など、松並木があったことを示す地名は残っている。 松原バス停を過ぎると、宮の前地区に入る。 その先は平塚駅前交差点を右折すると、平塚八幡宮のある八幡山公園にでる。 相模国風土記には、平塚宿が困窮し、公役の負担 |
 |
番町皿屋敷のお菊の墓 に耐えられないため、慶安四年、八幡村の一部を加宿とし、平塚新宿とした、とある。 こことその先の明石町が旧平塚新宿だと思うが、この一帯はビル街になっていた。 平塚は、北条氏の城下町として発展し、相模川水運による物資の集散地のため、東海道、中原往還(中原街道)、八王子道が通る交通の要衝として発展した。 番町皿屋敷お菊塚は、街道を左に入った長崎屋の裏あたりの紅谷町公園にあった。 番町皿屋敷で自害させられたお菊さんの墓があったと |
 |
{左}平塚宿江戸方見附 されるところだが、塚の脇に詳しい案内板がある。 街道に戻り、市民プラザ前交差点を横切ると、見附町に入る。 右側に、旧東海道平塚宿史跡絵地図という看板があり、その先に、平成十三年(2001)に復元された江戸方見附があった。 宿場の入口の街道の両側に、石垣を築いて、塚をつくり、その上に矢来を組み、宿場に入る旅人を監視したのが、見附である。 平塚宿は、途中から平塚新宿が加わったが、それ以前の平塚宿は、東西十四町六間(約1.5km)の |
 |
{左}平塚里歌碑
間に、十八軒町、二十四軒町、東仲町、西仲町、柳町と、上方見附まで続き、四百四十三軒の家に、二千百十四人が住んでいたのである。 市民プラザの中庭には、 平塚里歌碑があり、「 哀れてふ 世のしるし朽ちはてて かたみもみえめ 平塚の里 」の歌が記されている。 文明十二年(1480)、平安紀行の作者(太田道灌)が、京に上る途中、ここで隠遁して亡くなった三浦遠江入道定可のことを思い出し、里人に墓などを尋ねたが、誰も知らなかったのを悼んで、 |
 |
{左}脇本陣跡 この歌を吟じたものである。 見附跡から四百メートル程行くと、旧二十四軒町で、右側の茅沼酒屋前に脇本陣蹟の石柱があり、「 脇本陣は、当初は西問屋場の西にあったが、天保年間に現在地に移転し、山本安平衛が営んでいた。 」と、案内板にはあった。 平塚本陣郵便局を過ぎると、旧東仲町で、右側の山口屋茶舗前に、平塚宿高札場の蹟の石碑があった。 平塚宿高札場は、長さ二間半(約五メートル)、横一間(一.八メートル)、高さ一丈一尺(約三メートル)。 |
 |
{左}東組問屋場蹟碑 土台は石垣で、その上を柵で囲み、高札が掲げた部分には、風雨を避けるための屋根が作られて、その下に隣の宿場までの公定運賃などの高札が掲げられていた。 道の反対側には、東組問屋場蹟碑が建っている。 百メートル先の右側の神奈川銀行平塚支店の前に、平塚宿本陣旧跡という標柱が建っている。 加藤七郎兵衛が務めた本陣があったところで、間口約30m、奥行は約63mの総ケヤキ造りの建物だった、と伝えられる。 |
 |
{左}平塚信金前の交差点
平塚宿には、古い建物や往時の面影は残っていないが、この通りに五十四軒の旅籠が 軒を並べていたのである。 平塚信金前の交差点を左折した先にある宝善院が平塚宿本陣の菩提寺になっていた。 また、右折する道が新豊田道で、その先で中原街道と交差する。 徳川家康は、鷹狩のために造営した中原御殿(雲雀御殿ともいわれた)に訪れていたが、その際、中原街道を好んで使ったという。 それだけでなく、江戸と駿河の往来にも利用した、とある。 |
 |
{左}西組問屋場跡 東海道を直進すると、旧西仲町で、少し歩くと、右側に分かれて行く狭い道がある。 右側のなまこ壁の消防小屋が西組問屋場跡である。 問屋場は、二十四軒町に東組問屋場、西仲町に西組問屋場があり、東西の問屋場が十日毎に、問屋1名、年寄1名、帳付3名、馬指2名の構成で、交替で勤めた。 この建物を右折して行くと、突当りに松雲山要法寺がある。 山門前に、七面大明神と書かれた大きな石柱があり、松雲山要法寺縁起(案内板)があった。 |
 |
{左}松雲山要法寺
縁起によると、鎌倉幕府の執権、北条泰時の次男、泰知が、この地の地頭をしていた時、日蓮上人が平塚にご来臨されるという、七面天女のお告げを受けた。 日蓮上人はこの地に宿泊され、法華経のご説法したところ、邸内の平真砂子塚にそびえ立つ老松に、紫雲たなびくという端相が現れた。 それを見た人々は法華経の信者になり、北条泰知は、弘安五年(1282)、自らの館を献上して、当寺を開山した、とある。 |
 |
{左}平塚 少し行くと、右側に西仲町公園がある。 その公園の一角に平塚と呼ばれる塚がある。 天安元年(857)、桓武天皇の曾孫で坂東平氏の始祖といわれる平真砂子が、一族とともに東国へ向かう途中、ここで没したため、遺骸を埋め、この塚を築いた、といわれるものである。 これが平塚の地名の由来である。 隣には、春日神社があった。 東海道に戻り進むと、右からきた国道1号線と合流した。 |
 |
{左}上方見附
国道に入り、百メートル程歩くと、西組問屋場跡のところで分れた道と合流する三差路の古花水橋交差点があった。 江戸時代には、旧柳町のこのあたりに上方見附があったといわれ、交差点の左側に、復元された上方見附がある。 上方見附は平塚宿の京都側の入口なので、ここで平塚宿は終わりになる。 |