平塚宿から大磯宿
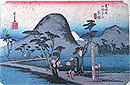 |
{左}安藤広重の東海道五十三次 平塚宿 安藤広重の東海道五十三次 平塚宿に、平塚宿西端の古花水付近を描いたものがある。 東海道の畷道がつづら折りに続き、道の右側の大きな松の下に、榜示杭と関札が見える。 その脇を旅人が通り過ぎていく。 榜示杭は、大住郡と淘綾(ゆるぎ)郡の境を示すためのもので、関札は、平塚宿を利用する大名が、宿場の入口に掲げたものである。 道の先に高麗山が見え、富士山も一部姿を現わしている。 右側に見えるのは大山だろうか? |
 |
{左}花水橋より見た高麗山 平塚宿の京方見附から大磯宿までは三キロと短い。 花水橋東交差点は三叉路で、右折は秦野に行く県道、東海道は直進する。 右手に、安藤広重が描いたこんもりと丸い高麗山の姿が見えてきた。 高麗の王族が移り住んだとか、虎御前の庵があったなどと伝えられる山である。 その先の花水橋まで行くと、山の姿が大きくなり、その右側に大山のある丹沢連峰がよく見えたが、浮世絵にあった富士山はなかった。 |
 |
{左}善福寺 橋を渡ると、大磯町である。 花水橋交差点を越えると、左側に善福寺がある。 山門を入ると、左側に親鸞聖人旧跡碑があるが、この寺は、親鸞聖人の高弟の一人、了源上人(伊東祐光)の創建である。 平塚入道ともいわれた伊東祐光は、伊豆の押領使、伊東祐親の孫にあたり、仇討ちで有名な曽我兄弟とは従兄弟の関係にあり、一族の菩提を弔うため、武士を捨てて出家し、親鸞の弟子になった。 寺には、鎌倉時代の木造了源坐像(国重文)と阿弥陀如来立像 |
 |
{左}茅葺きの古い家 (県重文)がある。 その先の道の右側に、茅葺きの古い家が残っていた。 このあたりは、江戸時代の寛政年間に、大磯宿高麗寺領(百石)が高麗寺村になったところである。 高麗(こま)寺には、家康を祭った権現社があったことから、村内には 下車の制札が掲げられ、大名は駕篭を降り、頭を下げて神社前を通った、といわれる。 高来神社入口交差点の右側に、高来 |
 |
{左}慶覚院 神社の石柱と鳥居が建っていたので、鳥居をくぐって歩いていくと、右側に慶覚院という寺があった。 慶覚院は、慶長十八年(1613)に大磯宿南下町に創建された寺だが、明治十五年の大磯の大火で、高麗寺地蔵堂があったところに移転した、とされる。 最近建て替えられたので、建物は新しいが、建治四年(1278)造立の木造地蔵菩薩坐像(県重文)や当寺本尊の木造千手観音立像が祀られていた。 大きな神燈が建つ参道を歩くと、左側に力石が置かれていた。 |
 |
{左}高来神社(たかくじんじゃ)社殿 その先の左側にある神社らしくない建物が、高来神社の社殿である。 神社らしくないのも、当然で、江戸時代まで、高麗寺の観音堂だったのである。 高来神社は、神功皇后の三韓征伐から帰国後、武内宿祢の奏請により、高麗大神、和光を勧請したのがはじめという説や高句麗が滅び、その王族、若光の一行が日本に逃れて来て、この地に上陸し、その一族を祀ったのがはじめという説もあり、神社の創建 の時期や起源ははっきりしない。 |
 |
元神輿殿 右隣の建物は、元々神輿殿だったようだが、これもまた、寺院風の建築である。 高来神社由緒に、 「 漁民が海から引き揚げた千手観音を本尊とした寺を、行基上人が高麗寺と認めたことから、山頂の高麗大権現を上社、山麓の高麗寺を下社とし、山頂の左右の峰に白山と毘沙門を勧請して、高麗三社権現と称した。 」、とあるように、高来神社は、江戸時代までは神仏混淆で、高麗大権現と高麗寺は一体とされていたのである。 明治の神仏分離の嵐が吹き |
 |
{左}虚空蔵尊の石標と小さな祠
寄せ、高麗寺が廃寺となった時、山頂の高麗権現社を観音堂に移し、高麗神社と名を変えて、観音堂の建物は残った。 そして、明治三十年、現在の名前の高来神社に改称したのである。 高麗寺は徳川幕府の庇護下にあったため、明治政府により、観音堂と神輿殿を除き、すべての建物が破壊された。 街道に戻り、歩き始めると、道の右側に虚空蔵尊の石標があり、小さな祠が建っていた。 傍らの案内板によると、「 江戸時代には、青木宮という熊野権現と虚空蔵 |
 |
{左}化糀坂(けはいさか) 侍を祀ったお堂があり、隣に下馬標、反対の左側に村の境を示す、三メートル程の寺領傍示杭が立っていて、村の境に字駒留橋が架かっていた。 」とある。 道は右にカーブし、更に進むと、道の右側に松の木があり、その先に三叉路の化粧坂交差点があった。 東海道は右の狭い道に入るが、緩い上り坂で化糀坂という名が付けられていた。 平安時代から鎌倉時代にかけては化粧坂近辺が大磯の中心地だったようで、化粧坂には遊女屋も多かった、という。 |
 |
{左}虎御前の化粧井戸
街道に入ってすぐの右側に車屋という、水車がある手打ち蕎麦屋があった。 百五十メートル程歩くと、左側に黄色い壁の家があり、化粧井戸があった。 大磯一の美女といわれた虎御前は、このあたりに住んでいて、この井戸で、朝夕化粧をした、と言い伝えられる井戸である。 車は殆ど通らず、古いたたずまいを感じさせる道の両側には、樹齢百二十年〜百三十年の榎(えのき)の巨木が立ち並んでいた。 |
 |
{左} 東海道五十三次 大磯宿 虎ヶ雨看板 坂を上りきった右側に、王城 釜口古墳 0.3km の木柱があるが、王城山には横穴古墳が多くあり、釜口古墳は高麗王若光の墓だという説もある、という。 街道を進むと、東海道五十三次 大磯宿 虎ヶ雨 という標題の浮世絵看板が現れ、 右手は高麗山の麓、虎御前と曽我兄弟の悲恋伝説も雨にぬれそぼってわびしい 、と書かれていた。 その先の左側に、三界万霊供養塔と馬頭観音が祀られている。 坂の頂上と思えるところで、東海道は東海道本線により寸断 |
 |
{左}大磯宿江戸方見附跡 されてしまっていた。 右側の随道(徒歩と自転車のみ)をくぐり、反対側に出ると、ここから下り坂となり、松並木が現れた。 松の木はかなり大きいので、東海道の生き残りのように思えた。 その先に、見附の案内板があったので、大磯宿に到着である。 道の右側にあった江戸方見附の案内坂には、さっき通り抜けてきた随道の手前あたりに、大磯一里塚があったように表示されていた。 このあたりには大きな松の木は残っているのだが、両脇に住宅が建っている |
 |
{左}三沢橋東側交差点 ので、現世を感じさせる風景になってしまった。 坂を下ると、大磯宿と書かれた宿場行燈が立っていた。 大磯宿は、 天保十四年の東海道宿村大概帳によると、宿内人口は三千五十六人、家数は六百七十六軒で、本陣が三軒、脇本陣はなく、旅籠が六十六軒だった。 東海道は、その先の三沢橋東側交差点で、国道1号線と合流する。 ここからしばらくは、国道を歩くことになる。 三沢橋交差点を過ぎると、神明神社があり、境内には、松の木が多く茂っていた。 |
 |
{左}穐葉神社入口交差点 江戸中期に神明台より遷座した神社で、神明町はこれに由来する。 大磯駅入口交差点の右手には大運寺があるが、そのまま直進すると、穐葉神社入口交差点手前の左側に鳥居と虎御石の案内板があった。 「 鳥居の先の秋葉神社は、宝暦十二年(1761)一月十九日の大磯宿の大火により、宿場の殆どが焼けたため、翌年、遠州秋葉山より勧請し、大運寺内に建立された神社である。 しかし、明治の神仏分離令により、寺から他に移され、大正七年(1918)に、 |
 |
{左}虎御石案内板 現在地に遷座してきた。 」 と書かれていた。 また、虎御石案内板には、 「 虎御石は、曽我十郎の剣難を救った身代わり石、また、虎御前の成長につれて、大きくなったといわれる生石である。 江戸時代の東海道名所記に、 虎が石とて、丸き石あり、よき男のあぐればあがり、あしき男の持つにはあがらず、という色好みの石なり、とある。 」 と、書かれていた。 虎御前は、大磯一の美女で舞の名手だったといわれ、曽我十郎佑成の愛人で、曽我兄弟の |
 |
{左}延台寺 仇討ちのため助力した、と伝えられる女性であるが、虎御前が、恋人の曽我十郎とその弟の五郎の菩提を供養するため、結んだという庵の跡に建てられた、と伝えられるのが、路地を少し入ったところにある、延台寺である。 慶長四年(1599)に、身延山十九世、法雲院日道上人が建てた日蓮宗のお寺で、日道上人が虎御前を供養するために建てたといわれる、虎御前供養塔がある。 前述の虎御石は、最近建てられた法虎庵曽我堂の中に収められているので、入館料 |
 |
{左}大磯遊女の墓 二百円を納めないと拝見できない。 また、小さな丸い墓碑の大磯遊女の墓もあった。 大磯の遊女は、人知れず無縁坂に葬られるものが多かったが、当寺信徒はこの寺に葬られた、という。 江戸時代、このあたりは北本町で、虎御石の道の反対の中南信用金庫駐車場の金網前に、北組問屋場の標示板があった。 享和三年(1803)の大磯宿には、小嶋、尾上、石井の三本陣があり、その建坪は、夫々二百四十六坪、二百三十八坪、二百三十五坪だった、という。 |
 |
{左}地福寺 少し先の右側にある蕎麦屋のあたりが小嶋本陣跡で、その前に標示板があり、「 小嶋本陣の裏に地福寺があり、本陣の裏口から出られるようになっていた。 」 とあった。 消防署前交差点を右折すると、承和四年(837)の創建と伝えられる地福寺があった。 山門の前には、真言宗地蔵堂の石柱が建っていて、墓地には大磯で亡くなった島崎藤村の墓がある。 |
 |
{左}尾上本陣跡 江戸時代には、消防署前交差点あたりに境橋があり、ここから先は南本町だった。 中南信用金庫の前には、大磯小学校発祥之地の大きな石柱があり、石柱の右側面には、尾上本陣跡と書いていた。 中南信用金庫は尾上本陣の跡で、気がつかないで、通り過ぎるところだった。 もう一軒の石井本陣は、幕末になる前に廃業になったので、標示板や石柱はないが、尾上本陣の筋向いの現在の大内館(旅館)の場所にあったようである。 道の右側の古い家を改築した |
 | {左}大磯名物 虎子まんじゅう西行まんじゅうの杵新 ような商店は、多くの客で賑わっていた。 大磯プール入口交差点にある杵新は、明治二十四年の創業で、、大磯名物 虎子まんじゅう西行まんじゅう という看板を揚げていたが、建物はかなり古そうに思えた。 交差点を左に入ると、突き当たりに松本順謝恩碑がある。 初代軍医総監松本順の尽力により、明治十八年に日本最初の海水浴場が大磯に開設された。 街道に戻ると、 左側の民家に南組問屋場の標示板があった。 少し歩くと、照ヶ崎海岸入口交差点に |
 |
{左}新島襄先生終焉の地 出た。 東海道はここで大きく右にカーブするが、角の三角形をしたところに、照ヶ崎海水浴場の道標が建っている。 大磯は日本で最初に海水浴が始められたと伝えられるところである。 植え込みの中に、同志社大学の創始者新島襄先生終焉の地という大きな石碑があった。 新島襄は、米国から帰国後、学校教育の必要性を感じて、大学創設に尽力中に病に冒され、大磯の百足屋旅館で療養していたが、明治二十三年(1890)、四十七歳の若さで亡くなった。 |
 |
{左}鴫立沢 この場所は、百足屋があったところである。 江戸時代は、ここを過ぎると、南茶屋町だった。 その先には、さざれ石バス停があり、少し歩くと鴫立沢(しぎたつざわ)交差点である。 江戸時代には、交差点手前の右側に高札場があったようで、民家の前に標示板があった。 また、南茶屋町との境には、鴫立石橋が架かっていた、という。 信号を越えた左手の鬱蒼とした森と鴫立沢に囲まれて、鴫立庵があった (9時〜16時、100円) |
 |
{左}鴫立庵
鴫立沢は、西行法師が、「 心なき 身にもあはれは しられけり 鴫立沢の 秋の夕暮れ 」を詠んだところといわれ、江戸時代の寛文四年(1664)に、小田原の崇雪(そうせつ) が五智如来を運び、西行寺を作る目的で草庵を結んだのが鴫立庵の始めで、元禄八年(1695)、俳人の大淀三千風が入庵して、ここを俳諧道場にしたことから有名になり、京都の落柿舎、近江の無名庵とともに、俳諧三大道場と呼ばれたところである。 境内には、五智如来石像や歴代の庵主の |
 |
{左}円位堂 供養碑が祀られている。 また、芭蕉などの句碑や佐々木信綱筆の西行上人歌碑などが所狭しと並んでいる。 鴫立庵の対面には虎御前を祀る法虎堂があり、上った正面には西行の旅姿の立膝坐像が祀られている円位堂が建っていた。 崇雪が建てた鴫立澤と書かれた石碑の前には湘南発祥の碑という看板があった。 この碑のどこかに、著盡湘南清絶地と書かれているようで、中国洞庭湖のほとり、湘江の南側がこの地に似ていることから湘南という地名が生ま |
 | {左} れたのである。 街道に戻ると、右側に古い家があり、入口にパン屋と書いてあったが、店という感じではないが、中に入れば営業しているのだろうか? それはともかく、このあたりは、江戸時代の加宿東小磯村で、現在は南台町である。 その先の右にある狭い道を入り、次に左折していくと、右側に島崎藤村の居宅だった家がある。 島崎藤村は、晩年の2年間をこの家で過ごし、七十二歳で亡くなり、前述の地福寺に葬られた。 |
 | {左}上方見附跡 街道に戻ると、左側のレストランガストの先の松の下に、上方見附の案内板があった。 案内板には、 「 大磯宿上方見附は、東小磯村加宿のはずれにあり、現在の統監道バス停付近にあった。 街道を挟んで高さ一メートル六十センチの台形の石垣の上に、竹矢来が組まれ、御料傍示杭が立っていた。 」 とあった。 大磯宿はここで終わりである。 |