金谷宿から日坂宿
 |
{左}石畳茶屋 金谷宿の不動橋を越えると、両側に古い家が建っていた。 なだらかな登り坂が、やや急な坂に変ると、左側の家の一角 に、小さな社が祀られていた。 この坂を登りきると、国道473号線に出たが、そのまま、道を横切り、旧東海道石畳入口 と、大きな看板がある道に入った。 急傾斜の坂なので、歩くペースは落ちたが、百五十メートルほど歩くと、右側に 立派な建物の石畳茶屋が現れた。 旧金谷町が建てたもので、金谷宿に関するものが展示されていた。 |
 |
{左}金谷坂の石畳 半分のスペースには売店や畳の部屋があり、自由に休憩や食事ができる。 小生も一面に拡がった茶畑を見ながら、お菓子を 食べ、お茶を飲み、一服した。 ここから金谷坂の石畳が始まる。 説明板によると、 「 江戸時代には、金谷宿から日坂宿の金谷坂に、石畳が敷かれていた。 近年は、僅か三十メートル の石畳を残すのみで、コンクリートの道になっていた。 平成四年に、町民六百人の参加をえて行われた平成の道普請で、 四百三十メートルの石畳が復元された。 」、 とあった。 石畳を歩き始めたところに、すべらず地蔵があり、その脇の 小道を |
 |
{左}鷄頭塚と庚申堂 登ると、左側に鷄頭塚、そして、奥に庚申堂があった。 鷄頭塚とは、六々庵巴靜が詠んだ句、 「 曙も 夕ぐれもなし 鶏頭華 」 から、付けた句碑のことである。 六々庵巴靜は江戸時代の俳人で、 薫風を広め、寛保四年(1744)に亡くなったが、彼を慕った金谷の門人たちが、金谷坂入口北側に、自然石の句碑を建てた ものである。 その先には、河浦向延命地蔵尊が祀られていて、その隣に、三匹の猿を刻んだ庚申塚三猿の石碑があった。 |
 |
{左}松並木 奥の庚申堂には、芝居の白浪五人男に出てくる、日本駄右衛門が、夜働きの際の着替え場所だった、という言い伝えが残る。 周りが薄暗いので、いかにも追いはぎがでてきそうな雰囲気なところだった。 石畳を登って行くと、赤い幟が沢山現れ、 右側の六角堂に祀られていたのは、滑らず地蔵である。 石畳を復原した際に、石畳を滑らないようにとの願いを込めて、 祀られたもの、という。 このような広範囲の石畳は、東海道では箱根峠、中山道では落合の石畳 |
 |
{左}芭蕉句碑 だけとあった。 坂を上りきると、広い道に出た。 正面の建物はNTTの通信施設のようである。 それを囲む土塁の上 に、明治天皇駐輦阯碑があった。 道を右折すると、左側に芭蕉の句碑があった。 句碑には、 「 馬に寝て 残夢月遠し 茶の烟 」 と、いう句が刻まれていたが、これは、野ざらし紀行の中で 詠まれた句である。 中国の詩人、杜牧の早行という詩を意識した作品といわれ、前文には、「 二十日ばかりの月微かに 見えて、山の根際いと暗 |
 |
{左}広々とした茶畑 きに馬上に鞭垂れて数里未だ鶏鳴ならず、杜牧が早行の残夢、 小夜の中山に至りて忽ち驚く 」 と、ある。 この先は、広々とした茶畑を左に見ながら歩く。 なお、芭蕉の前文は、 ( 未明の空に二十日月がかすかに見えて、山の麓あたりがたいそう暗い中を、鞭を垂れたまま馬の足取りにまかせ、数里を旅してきたが、いまだ、鳥の鳴き声が聞こえてこない。 杜牧が 早行 の詩に詠んだあの夢見心地のまま、馬に揺られ、小夜の中山まで 来たところで、やにわ |
 |
{左}諏訪神社鳥居と諏訪原城阯碑 に目が覚めた。 ) という意。 やがて、諏訪原城跡の看板が見えてくるが、そのまま進み、アルムという喫茶店手前の 小道を右折すると、鳥居と諏訪原城阯の石碑が建っていた。 鳥居をくぐり、奥に入ると、諏訪神社と書かれた案内と諏訪原 城全体の案内板があったが、湿気が多く、薄暗い。 諏訪神社は、小屋のような貧弱なものだった。 神社の前を通り過ぎ ると、いくらか明るくなって、城の空堀跡に出た。 諏訪原城は、武田勝頼が、天正元年(1573)に、 |
 |
{左}今福浄閑の墓塚 馬場氏勝に命じて築いた山城で、浜松の徳川家康に対する前線基地だった。 複雑な地形を利用し、堀を幾重にも張り巡ら せ、押し寄せる敵を防ぐ工夫が施された難攻不落の天然の要害だったが、今ではそのほとんどが、畑や茶畑と、なってしま っている。 茶畑の中に、ここで戦死した武田方の城主の今福浄閑の墓塚があった。 歩いて行くと、武家屋敷や馬場などが あったところは林に変り、二之丸や三之丸は茶畑になっていた。 二之丸や三之丸は、近年、学術調査 |
 |
{左}天守台跡 で掘り返され、その痕跡も残り、二之丸は武将が集まって戦術を打ち合わせたところ、三之丸は火薬や武器を貯蔵していた ところ、というような説明板が設置されていた。 天守台跡と書かれてところにきた。 天守台とは、天守閣の ような建物ではなく、物見櫓程度のものだったようである。 前方は急斜面になっていて、攻めてくる敵には石や矢で見なが ら攻撃できる位置にあったというが、今や木が繁茂しているので、一部しか眺望できなかった。 城址の保存 |
 |
{左}菊川の里
状態がよいこともあり、興味深く見学したため、二十分程度、時間を費やしてしまった。 東海道に戻り、先に進むと、県道 234号線に出た。 県道を横切ったところに、案内板と休憩所があり、眼下には、菊川の里が見えた。 休憩所で持参したおにぎりを食べ、お茶を飲んだ。 菊川坂を下る。 菊川坂は、金谷坂と同じような石畳の道である。 菊川坂には、江戸時代後期、近隣十二ヶ村に割り当てられていた助郷により、三百八十間(690m)の石畳が敷かれたが、 |
 |
{左} 菊川坂 百メートル程になっていた。 平成十三年、周囲の人達五百名余の力で、ほぼ元の姿に復元された、という。 石畳が終わった先には、東海道、菊川坂と書かれた道があったが、小生は宗行卿塚の案内を見つけたので、道を右折して車道に入り、歩いていく。 やがて、両脇は林になり、眼下に茶畑が広がったが、しばらく歩くと、左側に中納言宗行卿塚入口の木柱があった。 車道と別れ、二百メートルほど下っていき、その先で、右折した突き当たりに、宗行卿塚が |
 |
{左}宗行卿塚 あった。 中納言、藤原宗行は、承久三年(1221)、後鳥羽上皇が、鎌倉幕府を倒そうと兵を挙げ た承久の乱に敗れ、幕府に捕らえられ、鎌倉へ護送の途中、菊川の駅に泊まり、宿の柱に漢詩を残した。 その数日後、 藍沢原(現御殿場)で処刑された。 宗行卿塚は、水戸藩士の渡辺源進が、文久三年(1863)に、中世に築かれた墳墓の上に、 宗行卿塚と書かれた石碑を建てたものである。 塚は、西方二十メートルのところにあったが、昭和四十三年の国道1号金谷 |
 |
{左}間の宿 菊川 バイバス工事で、ここに移された、とある。 国道のガードをくぐり、法音寺に下り、大通りにでると、 東海道で、そこを右折し、まっすぐ進むと高麗橋がある。 橋の手前は、菊川の辻と呼ばれたようであるが、鎌倉時代には 宿駅で、江戸時代には間の宿だった菊川の入口である。 間の宿は、宿場と宿場の間が三里から四里ある場合に置かれたが、 菊川は一里二十四町しかないのに置かれたのは、小夜の中山や物見坂などの険しい坂があったから、といわれる。 |
 |
{左}秋葉山の社 大名などが休息する茶屋本陣は橋を渡り、少し先の左側の路地手前にあったようだが、 そのことを示す表示はなかった。 その先の右側に、秋葉山の社があった. 江戸時代には、秋葉山の隣に脇本陣があり、その前に庄屋を兼ねた鍵屋が務めた問屋場があったようである。 間の宿には厳しい制限があり、川留めなどで周りの宿場が利用できない時しか宿泊は許されない他、 尾頭付きなどの贅沢な食事は認められなかったという。 菊川名物になったのが菜飯田楽で、 |
 |
{左}鏃(やじり)鍛冶 特に、下菊川おもだか屋宇兵衛茶屋が有名で、尾張藩の殿様が賞味したと伝えられている。 左側の家のシャッターに、菊川のもう一つの名物だった鏃を造る風景が描かれていた。 鏃鍛冶の元祖は京五條の鍛冶で、この村に下ってきて定住したが、小夜の中山に出た怪鳥を射た矢の根が有名になり、 徳川家康が大阪城を攻略する際献上されて、幸運の鏃として、ここを通行する大名達が購入した、という。 少し歩くと、右側奥に、この鄙びた里には似つかわしく |
 |
{左}菊川の里会館 ない立派な建物があった。 菊川の里会館で、日曜日には地元の主婦によるさんぽ茶屋が開かれる、とある。 入口にある二つの石碑は、中御門中納言藤原宗行の詩碑と日野俊基の歌碑である。 宗行は、承久三年(1221)、後鳥羽上皇 が鎌倉幕府を倒そうと兵を挙げた承久の乱に敗れ、鎌倉に送られる途中、この宿駅で、宿の柱に漢詩を書いたことは既に述 べたが、この石柱には、その辞世の詩が刻まれている。 その隣にある日野俊基の歌碑であるが、 |
 |
{左}藤原宗行の詩碑と日野俊基の歌碑 彼は、宗行の約百十年後、後醍醐天皇が倒幕を企てた正中の変(1324)でとらえられ、鎌倉の葛原岡で処刑された人物 である。 歌碑に、『 いにしへも かゝるためしを 菊川の おなじ流れに 身をやしづめん 」 という歌が、刻まれているが、 彼もまた、捕られられ、鎌倉護送の途中、この地で宗行の故事を思い、詠んだ歌である。 これらの歌碑は、もとは街道左手奥の菊川神社(旧若宮八幡神社)の境内にあったものを平成三年に移転し、建て替えられたものである。 |
 |
{左}四郡橋 集落を過ぎて、しばらく行くと、小川にかかる四郡橋がある。 四郡とはなにかと思っていたが、橋を渡った左側に、 小さな石柱があり、榛原郡、山名郡、城東郡、佐野郡とあり、四つの郡の境になっているのだ、ということを知った。 小夜の中山へは、ここを左折し、車道を横断し、目の前の石段と石畳を登りその先の細い道を歩くことになるが、菊川の里はこれで終わりである。 |
 |
{左}小夜の中山への急坂 いよいよ小夜の中山への急な坂道である。 樹木が茂ったところを過ぎると、明るいところにでた。 正面に鉄塔があるが、 道の傾斜は半端ではない。 この先、伊勢国の石薬師宿に向かう途中の杖突坂も急坂だが、こちらの方が距離が長いので、 大変である。 我慢して歩いて行くと、平らなところに出た。 しばらく尾根のような道を歩く。 下を見ると絶景で、 下に向かって茶畑が果てしなく続いている。 また、向かいあう山の傾斜にも、茶畑が展開し、茶畑にアクセント |
 |
{左}茶畑の美しい風景 をつけているのは、点在する林や数本の樹木である。 季節は五月の茶摘みの季節だったこともあろう。 しばらく歩くと、 また、上り坂になるが、右側に、島田市と掛川市の境を示す道標があり、菊川と日坂宿の表示があった。 茶畑の間の急激な 坂道を登り続けると、十六夜日記を著した阿仏尼の 「 雲かかる さやの中山 越えぬとは 都に告げよ 有明の月 」 の歌碑があった。 |
 |
{左}衣笠内大臣の歌碑 これは、( 雲がかかる佐夜の中山を越えたと、都の子供らに伝えておくれ、有明の月よ。 ) という意。 この先も、 上り坂は続き、しばしの間、あえぎながら上ると、 左側に、最近建てられたと思える衣笠内大臣の 「 旅ごろも 夕霜さむき ささの葉の さやの中山 あらし吹くなり 」 の歌碑があった。 衣笠内大臣は、若くして定家の門弟となり、後鳥羽院や順徳天皇の内裏歌壇に参加。 弘長二年(1262)には続古今集の撰者の一人に加えられたが、 |
 |
{左}佐夜中山 久延寺 完成以前に没した。 彼の京嵐山にあった別荘が、後年、地蔵院となり、紅葉の名所になっている。 両側に数軒の家があるところで、坂道は終了。 その先のT字路を直進すると久延寺、右折すると、小夜の中山峠とあるが、 右折すると左にぐるーと回りこんむみたいで、左側に久延寺に入る道があった。 久延寺は真言宗の寺院で、正式名称 は佐夜中山久延寺である。 本尊の聖観音像は殺された子供を育てたということから、子育て観音と呼ばれている。 |
 |
{左}夜泣き石 掛川城主、山内一豊が、関ヶ原に向かう家康をもてなしたと伝えられることから、江戸時代には、ここを通る大名は、寺をおまいり するか、駕篭の戸を下ろして会釈して通り過ぎた、という。 木が茂る草むらにある茶亭址の石柱が、一豊が家康を もてなした跡の痕跡を示していた。 久延寺で有名なのが夜泣き石である。 小夜の中山に住むお石という女が、菊川からの 帰りに通りがかりの男に殺されたが、お石の魂は丸石に乗り移り、夜毎に泣いたため、里人はおそれ、 |
 |
{左}子育飴の扇屋 誰いうともなく、夜泣き石と呼ぶようになったと、今も語り継がれている。 芭蕉が野ざらし紀行で、小夜の中山で詠んだ 「 馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり 」 の句碑が庭の一角に建っていた。 街道に戻ると、右側に、扇屋という店が ある。 和尚が子供を育てるときなめさせたという子育飴を売っているが、土日曜日にしか営業していない。 その先の左側には、小夜の中山公園がある。 入口のところに一般的な歌碑と違う、大きな歌碑があるが、それには、 |
 |
{左}西行法師歌碑 「 年たけて また越ゆべしと 思いきや 命なりけり 小夜の中山 」 という、西行法師の歌が刻まれていた。 西行法師が、文治弐年(1186)、六十九歳の時に再び、当地を通った。 出家して、全国巡礼に出たときと違い、 今度は、死出の旅になるかもしれない旅で、この険しい山道を差し掛かった感慨がよくあらわれている。 小夜の中山から日坂宿までは、坂道を下っていく。 左側の木立の中に、江戸から五十四番目の佐夜鹿一里塚跡の石柱が立っている。 奥の土手には、古くなったもう1つの石柱もあった。 |
 |
{左}鎧(よろい)塚 その先には、蓮生法師の 「 甲斐ヶ嶺に はや雪しろし 神無月 しぐれてこゆる さやの中山 」という歌碑があった。 蓮生法師とは、源平の戦いで有名な熊谷次郎直実で、蓮生は、法然のもとで出家した後の法名である。 少し行くと三叉路で、直進が東海道である。 道の左側に階段があり、薄暗い中に、鎧塚があった。 建武弐年(1333)、中先代の乱の際、北条時行の一族の名越邦時は、京都へ上る途中、この地で今川頼国と戦って、壮絶な討ち死にを |
 |
{左}坂道をどんどん下る 遂げた。 敵将の今川頼国が、名越邦時の武勇をたたえて、ここに葬ったのが鎧塚である。 先代(北条氏)と後代(足利氏)の間で、一時的に鎌倉を制圧したことから「中先代の乱」と呼ばれる。 茶畑に挟まれた坂道をどんどん下ると、 その先にも、藤原家隆朝臣の 「 ふるさとに 聞きあらしの 声もにず 忘れ人を さやの中山 」の歌碑、 芭蕉の 「 道のべの 木槿(むくげ)は 馬に食はれけり 」 ( むくげの花を馬の上から眺めていると、あれよという間に、馬がその花を食べてしまったよ。 ) という句碑があった。 歌碑が並ぶ道を下っていくと、右側に、 |
 |
{左}小夜の中山 白山神社 の道標 白山神社があり、夢舞台東海道 小夜の中山 白山神社 の道標があり、日坂宿まで十四町(約1600m)とある。 道は尾根道のようになり、両側の茶畑の方が石垣が組まれて高くなっていた。 この先にも歌碑がいくつかあったが、紹介は省略したい。 白山神社から三百五十メートルほど歩いた石垣の上に、丸い石に馬頭観音が刻まれて祀られている。 さやの中山に現れる怪鳥を退治するため、京から下ってきた三位良政卿の馬を葬ったところ、という。 |
 |
{左}妊婦の墓 そこから二百メートル程の右側にある墓は、妊婦の墓と呼ばれ、良政卿の娘、 小石姫が嫌な結婚を前に、松の根元で自殺した後、葬られた場所と、伝えられるものである。 小石姫の霊がそばの松に留まり、松籟(松に吹く風音)となって、旅行く人々に哀切の情誘った、とある。 その先の左側に、涼み松広場という石柱があり、松の木の下に、芭蕉句碑が建っていた。 |
 |
{左}涼み松 「 命なり わずかの笠の 下涼み 」 芭蕉がこの松の下で、この句を詠んだため、この松を涼み松という。 ここには、 「 馬に寝て 残夢月遠し 茶のけぶり 」 の句碑もあった。 この先は少し下り、また、平らな道という具合である。 その先の左側には、夜泣石跡の標柱が建っている。 夜泣石は、明治元年まで、この場所の道の中央にあったが、明治天皇の東京行幸の際、道の脇に寄せられ、その後、東京の博覧会に出品された後、 |
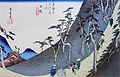 |
{左}安藤広重の小夜の中山峠 国道一号線の小泉屋脇に置かれた、とあり、石に、南無阿弥陀と刻まれている、という。 安藤広重は、小夜の中山の道が印象深かったようで、宿場を描かないで、夜泣き石付近を描いているが、道の真中に石があったことが確認できた。 その先の民家のところで、下にストーンと落ちる感じの急勾配の下り坂になった。 車で下るのは怖いという急勾配なので、江戸時代、馬に乗った人は、下を見てすくんだのではないだろうか? |
 |
{左}沓掛集落 このあたりは沓掛という地名だが、昔の旅人は草鞋をここで履き替え、古いものを木に掛けたことが語源である。 下り続けると、急勾配のまま、曲がりくねった道になるが、二曲がりと呼ばれるところである。 左手に、 日乃坂神社がある。 やがて、目の前が開け、向こう側に、国道1号の高架橋を走る車が見えてきた。 坂の終わりの石垣と石の水路があるところは、江戸時代、坂口町と呼ばれていたところ。 両側は茶畑で、民家はなかった。 |
 |
{左}江戸時代の日坂(にっさか)宿 苦しかった坂道が終わり、国道1号線のガードをくぐると、広い道にでた。 これで、金谷から始まった長く厳しい坂道の旅は終わった。 なお、この区間は、坂道が多いので喉が渇くが、途中に自動販売機も売店もないので、飲み物だけはしっかり確保したい。 国道を越えると、右側に下り坂の道があり、下って行くと、日坂宿上町に入った。 今も江戸時代と変わらず、静かな佇まいだった。 日坂宿は、長さは、六町(約700m)で、天保十四年(1843)の東海道宿村大概帳 |
 |
{左}秋葉山常夜燈 によると、人口は七百五十人、家数百六十八軒、本陣一軒、脇本陣一軒、旅籠が三十三軒と、東海道では坂下宿、由比宿に次いて、三番目に小さな宿場である。 日坂は小夜の中山峠の西の入口にあたるので、西坂、入坂などとも、呼ばれた。 道の右側に、秋葉山常夜燈が祀られている。 安政三年(1856)に建立された常夜燈が老朽化したので、平成十年に復元したものである。 日坂宿は火災が多かったようで、火防の神様を祀る常夜燈は、相伝寺と古宮 |
 |
{左}扇屋本陣跡 公会堂脇と、三つある。 宿場の大きな案内板の先には、大きな門があり、日坂宿の本陣跡と表示されていた。 江戸時代には、扇屋(片岡家)が 本陣を営んでいたが、明治三年の東海道制度の廃止に伴い廃業、建物は四つ辻小学校の校舎として利用されていたが、 現在は日坂幼稚園になっている。 大きな案内板の脇には、夢舞台東海道 日坂宿本陣跡 の道標があった。 家はみな、宿場町時代の屋号の看板を出していた。 街道沿いの家の並びは、江戸時代の |
 |
{左}元旅籠 池田屋 町割りとほぼ同じのまま残っているので、江戸時代の屋号と現在の住居とがほぼ一致するというから驚きである。 本陣の先の 道を挟んだところに問屋場があった、という。 道はその先で、逆くの字に曲がるが、両側に古い家が残っていた。 右側の家 は江戸時代、池田屋という名で旅籠を営んでいた家で、現在は末広亭という名で、旅館、割烹、仕出し屋をやっている。 その隣の雑貨屋、山本屋は脇本陣黒田屋の跡である。 脇本陣はしばしば代わったようで、大沢 |
 |
{左}問屋役 伊藤又七郎邸 富三郎が営む黒田屋が、最後の脇本陣だったようだが、明治天皇は、明治二年と明治十一年の二回、小休止をされている。 道は左にカーブするが、右側の古く立派な家は、宿場で最後の問屋役を務めた伊藤又七郎邸である。 文久弐年(1862) の宿内軒並取調上帳によると、伊藤家は、文七の営む藤文と吉右衛門が営むかえで屋に分かれていたようで、藤文部分の建物が、 江戸末期に、かえで屋の建物が明治初期に建てられたものである。 法讃寺がある先の |
 |
{左}元旅籠 萬屋 右側には、旅籠を営んでいた萬屋の建物がある。 嘉永十五年(1852)の日坂宿の大火で焼失後、安政年間 (1854〜59)頃再建された建物だが、間口四間半、奥行七間半の建物で、旅籠としては小さな部類に属する、と案内に あった。 宿場の中は、道が曲がりくねっている。 奥の方に、国道1号のバイパスが見えるが、左側の川坂屋 の前からは下り坂になった。 川坂屋は、大阪の陣で深手を負った武士が、手当てを受けたこの宿に永住し、その子孫の 問屋 |
 |
{左}元旅籠 川坂屋 役を務めた斎藤次右衛門が始めた、という旅籠だったところで、 建物は、嘉永十五年(1852)の日坂宿の大火後、再建されたものだが、文久弐年 (1862)の宿内軒並取調上帳によると、間口六間、奥行拾三間で、敷地は三百坪ほどあり、前述の萬屋よりかなり大きい。 精巧な木組み、細かな格子、床の間付きの部屋、当時禁制だった檜材を用いていることは、身分の高い武士や公家が宿泊 した格式の高い旅籠だったことを意味する。 明治の要人の山岡鉄舟、巌谷 |
 |
{左}相伝寺 秋葉常夜燈 一六、西郷従道などの書が残ることから、明治に廃業後も、要人には宿を提供していた、と思われる。 敷地は、国道の 工事の都度削られて、小さくなった。 その斜向かいの相伝寺を入ったところには、日坂宿の三つの秋葉常夜燈の一つが 祀られている。 これは、天保十年に建立されたものである。 境内には石仏群があった。 寺の前に、復元された高札場があったが、江戸時代、 ここが京方の宿場入口だった。 |
 |
{左}日阪宿の下木戸は小さな橋 宿場には、外部から侵入を防ぐため、鉤型(枡形)を設けるか、大木戸を建てる場合が多いが、この宿場の場合、宿場が 小さいこともあり、この小さな逆川の橋がそれだった。 当期の川は、もっと狭かったようで、かけた木橋を外すことで、 その役を果たしていた、といい、日阪宿の下木戸は小さな橋だったわけである。 これで、日坂宿は終わる。 |