見附宿から浜松宿
 |
{左}加茂川交差点 見附宿には古い建物など残っていなかったが、東海道本線から離れでいることもあり、落ち着いた雰囲気の町だった。 加茂川 橋を渡ると、見附宿は終わり、加茂川信号交差点で、国道1号線を越えると、坂道になった。 天平通りとあるが、江戸時代の 分間絵図を見ると、この坂道は石畳になっていたようである。 頂上付近の右側に磐田南高校、左に磐田郵便局があった。 その先の右側に、特別史跡・遠江国分寺跡の石柱が建っていたので、中に入っていく。 |
 |
{左}遠江国分寺跡 国分寺は、奈良時代、聖武天皇の命令で各地に造られたが、遠江国分寺は、中泉のこの地に建立され、国分尼寺は、北側二百メ ートルに配置された。 国分寺は、東西百八十メートル、南北二百五十メートルの広さで、伽藍は金堂を中心に、七重塔や講堂 、中門などが配置され、それらを築地塀などで囲んでいた、というもので、発掘調査が行われた際、七重塔や金堂跡などが確認 された、とある。 今は跡形もなく、だだ広い空間に案内板が一つ建っていた。 |
 |
{左}薬師堂 中世に入り、国分寺は衰退したが、その後、その一隅に薬師堂が建てられた。 南無薬師瑠璃光如来と、書かれた赤い幟が立つ お堂がそれで、手洗石は、国分寺の礎石をくり抜いてつくられたものである。 街道に戻ると、道の反対側に、府八幡宮と書か れた木造の大きな鳥居が建っている。 大鳥居をくぐり、参道を歩くと、寛永十二年(1635)建立の楼門があった。 入母屋 |
 |
{左}府八幡宮随身門 造りで、建物全体が深みのある美しい随身門だった。 府八幡宮とあるのは、奈良時代の天平年間、天武天皇の曽孫、桜井王 が、遠江国司として赴任したとき、国の安定を願い、国府内に祭られたのが神社のはじめとあることから。 その後、今川氏の 羽鳥庄の地頭職となった秋鹿氏が、神主を務め、江戸時代には、徳川幕府の代官に任じられ、二百五十石を給せられた。 楼門 をくぐって中に入ると、文化年間に再建されたという中門があり、その奥に幣殿と本殿が |
 |
{左}府八幡宮幣殿 あった。 幣殿は拝殿付きで、寛永十二年(1635)に建立され、正徳四年(1714)の再建されたもの。 本殿は、後水尾天皇の皇后 、東福門院が寄進し、元和三年(1617) に建てられたものである。 神社の祭神は、仲彦命(仲哀天皇)、誉田別命(応神天皇) 、気長足姫命(神功皇后)だが、明治維新までは、阿弥陀如来像を祀る、神仏混合の神社だった。 右側の奥の方に歩いて 行くと、駐車場の一角に、桜井王と時の天皇の問答歌が刻まれた万葉歌碑がある。 |
 |
{左}ジュビロの選手の足型 街道に戻り、歩き始める。 市役所入口信号交差点を過ぎると、左に曲がる道は、幾つかあるが、東海道はまっすぐである。 磐田中町バス停を過ぎたところのコンビニ前に、旧救院跡の石碑があった。 商店街は屋根付きで、歩道にはジュビロの選手の 足型が刻まれていた。 磐田はサッカー日本一に輝いたジュビロの本拠地で、この通りはジュビロ通りという名で呼ばれて いる。 |
 |
{左}中泉御殿裏門の案内板 東町バス停の先に中泉御殿裏門と西願寺の案内があった。 徳川家康が、天正十四年(1587)、初代代官を務めた秋鹿氏の屋敷跡に御殿を造ったのが中泉御殿で、 東海道の往来時の宿泊施設や鷹狩り時の休息所として利用された。 家康の死後、寛文十年(1670)に御殿が廃止された際、建物は周りの寺院に払い下げられた。 表門は見附の西光寺に払い下げられ、、裏門は西願寺の表門になった。 その先はビルが建ち並び、JR磐田駅が見えてきた。 |
 |
{左}磐田駅前 東海道は、磐田駅前信号交差点の手前で、右に入る細い道である。 手前のビルは現在工事中で、その角に、木製の東海道の案内板があった。 右折し進むと、右奥に、村社浅間神社が見える。 西町を過ぎると、緩やかな上り坂で、登っていくと、道の両脇に古そうな家があるが、その他は新しい。 旧中泉村は、江戸時代には三百三軒の家があった、というが、かって農村だった面影はすっかり消えていた。 中泉公民館も立派な現代風の建物である。 |
 |
{左}中泉公民館 道側に、夢舞台東海道 中泉 の道標があり、また、江戸時代と大正時代の中泉の絵図が掲示されていた。 その前を通り過ぎると、すぐに、江戸時代には立場だった旧大乗院村に入る。 大正時代には、中泉軌道がこのあたりを通っていたようである。 中泉軌道は軽便鉄道で、磐田駅(当時は中泉駅)から田中神社の近くを通り、北上し、現在の県道261号線に出て、左折するルートである。 小さな橋を渡ると、右側に大乗院坂の石碑があった。 少し歩くと、 |
 |
{左}西新町
旧大乗院村のはずれ(今の西新町)で、右からの市役所からの広い通り(県道261号線)と合流してしまった。 すぐ先が旧豊田町(磐田市に編入合併)で、小さな川に架かる一言橋を渡る。道の左の磐田化学工業の敷地内に、くろんぼ坊様 という黒坊大権現が祀られていた。 万能橋を渡ると、宮之一色に入る。 スズキの販売店の前から、短い区間ながら、松並木 が残っていた。 万能橋から約二キロ行ったところの右側、経済連バス停前に、宮之一色一里塚跡 |
 |
{左} 宮之一色 秋葉山常夜燈 がある。 江戸から六十三番目の一里塚で、昭和四十六年に復元されたものである。 松並木が終わり、しばらく行くと、左側に秋葉山常夜燈がある。 文政十一年(1828)に建立された、木製の常夜燈で、祠の中 には、毎年、可睡斎からいただくお札を祀っている、という。 透かし彫りの立派なものだった。 宮之一色西バス停の先からは、道の左側に、松並木が残っている。 森下の歩道橋の先は三叉路。 歩道橋をくぐると、森下南信号交差点で、県道は右にカーブ |
 |
{左}森下羽田橋 していくが、旧東海道は直進し、車が一台しか通れない狭い道をいく。 交差点の右手に若宮八幡があるが、このあたりは、ひっそりとした町並である。 少し歩くと、森下羽田橋に出るが、江戸時代には、橋のたもとに、森下村の高札場があったようである。 そのまま歩いていくと、右側の民家の垣根に、夢舞台東海道 長森立場 長森かうやく の道標があり、看板に、 長森立場は、これより数十メートル東にあった、とある。 立場は、掛茶屋、立場茶屋などと呼ばれる |
 |
{左}夢舞台東海道 長森立場 長森かうやく の道標 茶屋を兼ねていた。 旅人は、ここでお茶を飲んだり、名物の餅などを食べて、休憩したもので、馬にも湯や麦などを補給した。 長森かうやくは、江戸時代の万治年間に、山田与左衛門が始めたあかぎれや切り傷に効果のある軟膏で、参勤交代の一行や東海道の旅人の土産として人気があった。 やがて、T字路になり、木内建設の工場に突き当たるが、江戸時代の東海道は、工場のところを直進し、天竜川の土手に登り、北に進み、天竜川橋より少し上流の河原 |
 |
{左}土手に上る から、船渡しで川を越えていったのである。 天竜川は、暴れ天竜と呼ばれ、徒歩渡りができないほどの急流だったため、大井 川の徒歩渡しと違い、舟渡しだったが、それでも、水が増えると、川止めが頻繁に行われた。 また、渡船場が街道よりも上流 にあったのは、川の流れが速いためであろう。 突き当たった工場で、右折して進むと、右側の源平新田公民館前に、天竜橋跡 の碑がある。 公民館を過ぎたところで左折し、川の見える土手に上っていく。 |
 |
{左}天竜川橋 現在は天竜川の水量が減り、川岸は公園になっていた。 国道にでて、天竜川橋を渡る。 明治七年(1874)に架けた橋は、船を つなぎ、上に板を載せた舟橋で、二年後に、巾三メートル六十センチの木製の橋に架け替えられたが、橋銭を徴収する有料橋だ った。 木製の橋は、流される度に架け替えられたが、昭和八年に現在の鉄製の橋になった。 |
 |
{左}天竜川全景 造られた当時は自動車がこんなに多くなるという想定がなかったためか、幅が七メートル四十センチの道は、歩道がない上、 歩道帯もなく、大変危険な橋なのである。 その日は、トラックの通行が少なかったので助かったが、橋の長さが九百 二十メートルと長いので、ひやひやしながら、歩く。 |
 |
{左}藤原宗行の詩碑と日野俊基の歌碑 川の中央部には水量は多かっ たが、川の流れは穏やかで、河川敷の風景からは、暴れ天竜と呼ばれた当時の姿は想像できない。 やっとの思いで渡り終え、浜松市に入った。 浜松市は、今回の市町村合併で、上流の天竜市などと合併し、政令指定都市に なった。 土手を三百メートルほど下流へ歩くと、天竜川木橋跡と舟橋跡の木標があったが、対岸は公民館あたりなので、 位置 的にここに架けられていたということは納得できた。 |
 |
{左}明治大帝御聖蹟標柱と玉座迹記念碑 右側に、明治大帝御聖蹟の標柱と玉座迹の記念碑があったが、明治天皇が行幸された時、金原明善と謁見した場所である。 金原明善は、全財産を売り払って資金を作り、治水工事の費用に充てた、といわれる人物である。 右側の狭い道を下ると、右側に六所神社があり、その前に、東海道の標柱が建っていた。 このあたりは中野町で、十返舎一九の東海道中膝栗毛に、「 舟よりあがりて建場の町にいたる。 此処は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、 |
 |
{左}中野町集落 ふりわけの所なれば中の町といへるよし 」 と、あるが、京都と江戸のちょうど中間点にあることから付いた地名と、いう。 その先で横に延びる道は、浜松宿までほぼ一直線で、西へ続いている。 道の左端に、西町通りの標柱がある。 太陽は、かな り低くなってきたが、浜松はまだ遠い。 右側の立派な屋敷の前に立つ松は、東海道の松並木時代のものだろうか? その先に右側に、軽便鉄道軌道跡の標柱がある。 しばらく歩くと、右手に松林寺が見えてきた。 |
 |
{左}金原明善の生家 道の反対側の民家の駐車場に、かやんば高札場跡の標柱があったが、かやんばは、萱場のことで、旧安間村である。 その先の 右側に、白壁に黒い板が張られた塀で囲まれた大きな家が建っていた。 これは、前述した旧安間村の庄屋で、明治、大正期の 実業家、金原明善の生家である。 金原氏は、天竜川の治水に人生を賭けた人で、明治八年に天竜川の治水に着手したが、政府 からの補助金が少なかったため、全財産を売り払って資金を作り、治水工事の費用に |
 |
{左}安間一里塚跡 充てた、といわれる。 生家の向かいの金原明善記念館では、彼の生涯を知ることができる。 しばらく行くと、右からの広い 道と合流するが、この道は、先程、天竜川橋を渡ったところで、別れた道である。 金網の中に、安間一里塚跡の木柱があるの だが、木が生え茂っていて、気を付けないと、見過ごしところだった。 なお、右側の道の少し手前の安新町交差点に、 北へ行く道があるが、江戸時代、姫街道と呼ばれた、吟味の厳しい新居関所を避けた人達が利用した道である。 姫街道は、 前述の見附宿追分から池田に出て、池田から船渡りして、市野に |
 |
{左}安間橋 いたる道だが、この道は市野で合流していた。 少し歩くと、安間川に架かる安間橋を渡る。 その先の左側に、背の高い松の 木が現れた。 国道1号線の高架をくぐると、道幅が狭くなったが、車が多く、歩道もないので、少し怖い道である。 ここか ら、およそ百メートルほど松並木が続いた。 その後、松並木はなくなったと思ったら、薬師のバス停から、五十メートルほど の間に、松並木が残っていた。 その先も、ところどころに松が残っている。 |
 |
{左}浜松アリーナ 天竜川駅への十字路があるあたりが、昔の橋場(はしば)で、道の右側に、永禄年間の創建で、慶安元年に再建された、という 六所神社があった。 神社には、蒲村東方端和(はしわ)村六所大明神と、書写された古文書が残り、現在の社(やしろ)は、大正弐年(1913)の造営である。 やがて、右側に見えてきた大きな建物は、浜松アリーナである。 道脇には、東海道浮世絵浜松宿の看板があった。 |
 |
{左}子安交差点 少し歩くと、右側に、六軒京という漬物店があったが、かっての六軒茶屋に、由来するようだった。 更に進むと、右側にエッ ソのスタンドがある大きな交差点に出た。 右から左へ斜めに交差する子安信号交差点であるが、東海道は直進する道で、表示 が国道152号線に変った。 国道152号線は、浜松市を起点に、長野県上田市に向かう道だが、この交差点を右折して、 北上すると、途中の青崩峠があり、この峠は、国道であるのに、自動車が通れないのである。 |
 |
{左}琵琶橋 道の左側を歩いてくると、地下道を使わなければならないが、エッソ側は横断歩道で向こう側に渡れる。 その先で、芳川に架 かる琵琶橋を渡った。 西遠学園入口交差点の右側にある、大きな木の鳥居は、蒲神明宮の鳥居で、参道の入口である。 参道 に入り、少し歩くと、車道に出たが、信号があるのは右側の交差点なので、迂回しなければならない。 |
 |
{左}蒲神明宮鳥居 車道の反対にある道を進むと、やがて、右側の森の中に、蒲神明宮はあった。 古くは、蒲大神ともいわれたが、平安時代初期、 大同元年(806)に、伊勢皇太神宮に勧請し、創建された古社で、鎌倉時代の三代実録、貞観十六年の条に、従五位下を授く、と ある由緒ある神社である。 蒲氏の祖、越後国司、藤原静並は、蒲二十四郷を開発し、皇太神宮に寄進し、伊勢神宮の御厨とな ったと、神社の由来書にあるが、蒲(かば)の地名は、藤原静並が住み着いた頃、 |
 |
{左}蒲神明宮(かばしんめいぐう) 蒲が生いしげる荒地だったことに由来する。 藤原氏は、その後、蒲氏と改称し、蒲神明宮の神主になり、代々継承した。 正面の建物は神明造りの拝殿で、その奥に、天照皇大神を祭神とする内宮が、そして、西寄りに豊受皇大神を祀る外宮がある 。 また、ここの神主は、源頼朝の弟、範頼の末裔であると言われている。 源範頼は源義朝の六男で、頼朝の平家討伐の戦いに 加わり、弟義經とともに戦功を挙げたが、義經が討たれて後、讒により伊豆修善寺に幽閉 |
 |
{左}馬込(向宿)一里塚跡 され、建久四年(1853)に殺された。 街道に戻ると、このあたりには古い家が多少残っていた。 ここから浜松宿までは二キロ弱 であるが、日がだいぶ傾いてきたので、浜松宿の入口で今日の旅を終えよう。 道の右側に竜梅禅寺、左はNTTのマイクロウ エブ、その向こうに、東海道本線が見えた。 右側のセブンイレブンの反対側の植え込みで、馬込(向宿)一里塚跡の標柱を 見つけた。 東鎧橋を渡ると相生町、木戸町と変わった。 |
 |
{左}馬込橋 少し歩くと馬込川に架かる馬込橋が見えてきた。 江戸時代には、この橋を渡ると浜松の宿だった。 浜松宿は、次回ゆっくり見ようと、今日の袋井駅からの旅はここで 終えることにして、走ってきたバスに乗った。 すると、あった言う間に、浜松駅に着いた。 浜松宿を歩くため、再び、浜松駅へ、今日は、浜松宿を経て、舞阪宿まで歩く予定である。 浜松宿は、天保十四年の東海道 宿村大概帳によると、人口は五千九百六十四人、家数千六百 |
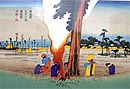 |
{左}広重の東海道浜松宿 二十二軒、旅籠が九十四軒もある、遠江国と駿河国で、一番大きな宿場だった。 安藤広重の東海道浜松宿の浮世絵には、遠く に浜松城が見える。 浜松は、江戸時代から綿織物の産地として栄え、昭和三十年代までは、綿織物の生産地だったが、現在は 自動車と楽器の製造業が主体で、大企業の下請けの多い町である。 駅から前回終わった馬込橋までは歩いていった。 橋入口の道路左側に、浜松宿の外木戸跡の木柱があるはずだが、残念ながら、 |
 |
{左}夢告地蔵尊 見付けられなかった。また、最初の信号交差点を越えた左側あたりに、番所があったといわれるが、区画整理で、新しい建物 が建ち、全てが抹殺された感がある。 浜松宿は、ここ新町から西へ進み、連尺町で左折し、伝馬町、旅籠町を経て、菅原町で 終わる宿場だが、浜松城の城下町でもあった。 駅前に差し掛かると、左側のビルの間からアクトシティが現れる。 新町交差点の右側には、夢告地蔵尊が祀られている小さなお堂があった。 |
 |
{左}板屋町交差点 江戸時代の末期に、コレラで亡くなった人々を祀るために建立されたが、明治時代の廃仏毀釈により、土中に深く埋められてい たが、町民の夢枕に出て助けを求め、町民達の手で掘り出されて、新たなお堂に安置された、という逸話が残る。 板屋町 交差点の先には、遠州鉄道西鹿島線の高架が見える。 高架の下に万年橋があるが、川は蓋をされて公園になっている。 高架 をくぐると、田町、ゆりの木通りという表示がある。 商店街には違いないのだが、大きな |
 |
{左}連尺交差点 ビルが建ち、ビジネス街の感がした。 そのまま進むと上り坂になり、上りきったところに、連尺信号交差点があり、国道15 2号と257号が接している。 東海道は、ここで左折する。 交差点を右折し、市役所前信号交差点を左折すると、浜松城 公園前に出られる。 浜松城は、徳川家康が遠州攻略の拠点として築いた城で、元亀元年(1570)六月に入城し、天正十四年 (1586)十二月、駿河城に移るまでの十七年間をこの城で過ごした。 これまでの地名、 |
 |
{左}浜松城本丸石垣 曳馬(引馬)は縁起が悪いと、荘園時代の浜松の名に変えたのも、家康である。 せっかくなので、浜松城に寄る。 市役所前交 差点の左側の浜松市役所は、浜松城の二之丸の跡である。 浜松城は、東西六百メートル、南北六百五十メートルの規模で、南 の東海道に大手門が開き、東から西に三之丸、二之丸、本丸、天守台と連なり、順次高くなっていた。 市役所の左側に入ると、 本丸の石垣が残っていた。 野づら積みと呼ばれる堅固な作りで、石は湖西から船で |
 |
{左}復元された天守櫓 運ばれたのだろうと、書かれていた。 本丸跡には、徳川家康の銅像が建つ。 吉川英治の太閤記には、 「 徳川家康は、 武田信玄との三方ヶ原の戦いで破れて、この城に逃げ帰る。 武田軍が、浜松城まで追撃してきたが、家康は、空城の計を使 い、居留守を極めこむ。 大手門は開き、かがり火を真っ赤に燃やし、城内はしーんと静まりかえっていたのを見た信玄は、 それを見て、うかつに手が出せぬと、城攻めをせずに撤退をした。 」、というシーンがある。 |
 |
{左}浜松宿 高札場跡 浜松城は、出世城として名高かったが、その割りには浜松藩の石高が低く、五万~七万石だった。 連尺交差点まで戻り、旅を 再開。 東海道は、連尺交差点で、直角に左に曲がり、南に向かう。 浜松宿は、宿場でありまた城下町でもあったが、曲がり 角は少なく、ここ1ヶ所のみである。 交差点を左に曲がった右側の谷島屋書店前に、高札場跡の説明板がある。 連尺町からこの先の伝馬町までが宿場の中心で、本陣が六軒もあった(脇本陣はない) |
 |
{左}佐藤本陣(彩画堂) 道の反対(左側)の彩画堂と緑屋装室あたりが佐藤本陣のあったところで、道の脇に、佐藤本陣は、二百二十五坪(約745㎡)の 敷地だった、という説明板があった。 道の左奥に、五社神社と諏訪神社があった。 五社神社は、遠江国主、久野越中守が、 曳馬城内に奉斉し、家康は、その子・秀忠が城内で誕生したので産土神として崇敬した。 天正八年、当地に転座され、社殿が 建てた、とある神社である。 諏訪神社は、徳川家康が社殿を造営し、家光が現在地 |
 |
{左}五社神社と諏訪神社 に転座した。 五社神社と諏訪神社の社殿は、国宝に指定されていたが、昭和二十年の空襲で燃失、両神社は合祀され、現在の 建物は、昭和五十七年に再建したものである。 街道に戻ると、右側に浜松信金伝馬町支店があるが、ここは杉浦本陣の跡で、 歩道に、「 杉浦本陣は二百七十二坪(約900㎡)の敷地だった 」 、という説明板があり、敷地内に本陣 跡と刻まれた標柱 があった。 右側には、三菱東京証券の赤い看板が見え、その先は伝馬町交差点 |
 |
{左}梅屋本陣跡(ザザシテイ西館) である。 三菱東京証券のビルが川口本陣の跡で、歩道に、 「 川口本陣は百六十三坪(約540㎡)の敷地だった 」、とい う説明板があった。 伝馬町交差点の左に見える大きなビルは、ZAZACITY(ザザシテイ)西館である。 その前に、 梅屋本陣跡の説明板があり、「 梅屋本陣は、百八十坪(600㎡)の敷地だった。 国学者、歌人として有名な賀茂真淵(本名、 庄助)は、梅屋の婿養子だった。 」 、とある。 |
 |
{左}蕎麦屋 右に緩くカーブする国道257号線を歩く。 その先の、伝馬町 旅籠町交差点を過ぎると、旅籠町になるが、町並は少し雑然とした感じだった。 浜松宿には、九十四軒の旅籠があったので、江戸時代の旅籠が並ぶ姿と客引きは、さぞかし凄かったことだろう、と想像した。 昼には少し早かったが、塩町歩道橋近くの木挽庵というそば屋にはいり、千円なりの天もりそばを注文した。 汁は少し塩からい感じがしたが、蕎麦は更科系の細麺でこしもあり、おいしかった。 |
 |
{左}夢舞台東海道 浜松宿 道標 蕎麦屋を出て、二百メートル程歩くと、成子交差点で、国道257号は直進、県道62号は右折の表示がある。 交差点の左手前に、夢舞台東海道 浜松宿 の道標があり、舞阪宿まで10.9㎞と書かれていた。 東海道は、交差点を右折し、国道257号を渡る。 病院の一角には、成子坂泣き子 地蔵尊跡の標柱があり、道を挟んだ先には浜納豆の店があった。 県道62号(雄踏街道) を二百メートルほど進むと、菅原町交差点。 東海道は左折であるが、東伊場に |
 |
{左}賀茂神社 賀茂神社があるので、寄り道をする。 真っ直ぐ行くと、五百メートルほど先に、京都上賀茂神社の流れをくむ賀茂神社があった。 賀茂真淵は、賀茂神社の神官の子として生まれ、京都で荷田春満(かだのあずままろ)に師事して国学を学び、 浜松に帰郷して遠州国学の中心となり、神官、町人や地主層の支持を受けた。 その後、江戸に出て、八代将軍徳川吉宗の次男、田安宗武(たやすむねたけ)に仕えた。 |
 |
{左}子育地蔵 傍らの説明に、境内に県居翁の旧蹟があるとあったが、県居は賀茂真淵の号である。 もう少し先の丘の上には、天保十年(1839)に、浜松藩主、水野忠邦によって創建された県居(あがたい)神社があるが、寄らなかった。 菅原町交差点に戻ると、子育地蔵があり、脇に石仏群が祀られていた。 その先の菅原町の家並みが終える と、浜松宿は終わる。 途中から雨に降られ、蕎麦屋で四十分過ごすなど、計画より遅いペースである。 この後、舞阪宿を目指す。 |