舞阪宿から新居宿
 |
{左}新居から見た今切方面 浜名湖は、もとは淡水湖で、室町時代に、大地震と津波で砂浜が流されるまでは、陸続きであった。 当時は、海の通じる川が あり、その上に架かる橋を渡れば、舞阪から新居まで歩けていけたのである。 地震以降、東海道は、陸づたいに行くことがで きなくなり、舞阪から新居までは一里半(約6km)の距離を約二時間の舟便によった。 これを今切(いまぎり)の渡しと いう。 |
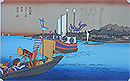 |
{左}広重の東海道新居宿 安藤広重の東海道新居宿の絵には、その様子が描かれている。 昭和七年に浜名橋が完成し、この渡しは廃止になったので、 この区間は電車に乗るか、弁天島経由で、橋を渡るかの方法をとらなければならない。 JRを利用した場合は、新居町駅で 降り、新居関所までは、約八百メートル、十分ほどの距離である。 |
 |
{左}弁天橋 舞阪宿の上雁木で、舞阪宿の探訪は終えたが、時間があったので、弁天島まで歩くことにした。 北雁木から北に向かうと、 弁天橋がある。 橋の上から浜名湖の水と大きな弁天神社の鳥居が見えた。 思ったより早く橋を渡り終えた。 国道と合流 する角に弁天神社があった。 弁天神社は、今切渡海安全のために宝永六年(1709)に建立された神社である。 舞阪は、 「 天女が舞い降りてきて、島の松の木で休んだ。 」 という伝承があるが、祭神は、市杵島姫 |
 |
{左}弁天神社 命(いちきしまひめのみこと)である。 境内には天女伝説で知られる子宝の松がある。 また、正岡子規が浜名湖弁天島を詠んだ、 「 天の川 浜名の橋の 十文字 」 という句碑もあった。 そこから先は温泉旅館が数軒続く。 それが終わると、中浜名 橋で、渡ると新弁天というところになるが、ここにも温泉旅館が数軒ある。 次の西浜名橋を渡ると新居である。 この橋が一 番長く、500m程である。 残りは250m位だろう。 |
 |
{左}浜名橋の舟溜まり 舞阪宿〜新居宿は、約6kmであるが、特に歩かないでもよいなあ!!、というのが実感である。 新居町駅前には、 山頭火の 「 浜名街道 水まんなかの道がまっすぐ 」 と、いう句碑が建っている。 駅前の道を歩いて行くと、宿場駐車場の先 に、浜名川に架かる浜名橋があり、その左側に、多くの小さな舟が係留されていた。 橋には、新居宿の浮世絵がレリーフにな って、幾つか描かれていた。 両脇には、御土産物屋や飲食店が並んでいた。 |
 |
{左}特別史跡・新居関 今切の渡しの渡し場の創設された当初は、浜名湖の今切口に近い、現在、大元屋敷と呼ばれるところにあったが、地震や津波な どの災害で、移転が強いられ、他に移転したがここも駄目で、現在の場所に移った、という。 道の右側に、特別史跡・新居関 跡の案内があった。 当時の建物が残っているのである。 右手にある受付で、四百円を払って入館(9時〜4時30分、 |
 |
{左}江戸時代の渡舟場 月休)したが、その先の旅籠を含めた料金である。 新居関所と資料館だけなら三百円。 門をくぐると左側に堀のようなもの が見えるが、江戸時代の渡舟場を再現したものである。 江戸時代には、関所のすぐ東が浜名湖で、関所の構内に渡船場があっ たので、舞阪宿の渡船場で舟に乗ると、着いたのは新居関所で、新居関所が江戸方の入口だったのである。 明治以降の埋め立 てにより、渡船場などが無くなったが、平成十四年、古絵図などに基づき、護岸石垣、渡船場、面番所へ の通路などを復元した ものである。 新居関所は、正式には今切関所といい、 |
 |
{左}面番所 慶長五年(1600)に設置され、幕府が管理したが、元禄十五年(1702)、三河国吉田藩に管理が移された。 面番所、書院、下改勝 手、足軽勝手の建物は、嘉永七年(1854)の大地震で大破、翌安政弐年に建替えられた。 手形を改める面番所では、番頭を筆頭 に、給人、下改などの役人が勤めていた、当時の様子を人形で再現している。 |
 |
{左}新居関の吟味風景 新居の関は、箱根の関所と同じように、 入り鉄砲に出女 の取り締まりが厳しかった所で、女人はこの関所を通るのを嫌がった。 船囲い場跡内に、女改長屋があり、関所勤務の足軽の母親が住み、関所を通る女性を調べていた、という。 資料館には、長崎勤番の大名の家来が、長崎の女を秘かに郷里に連れ帰ろうとして、関係者の多くに、 重罪が執行された事件が、紹介されていた。 関所手形に、女、鉄砲の他、乱心、囚人、首、死骸というのもあり、 |
 |
{左}船囲い場跡 船の出入りに出船手形、入船手形があることも知った。 関所を出て、街道に戻る。 関所の手前を左に入った空き地に、船囲い場跡石柱が建っていた。 ここは、舞阪宿からの渡船用の船をつないだところで、常時百二十艘が配置されたが、 大名通行などで足りなくなると、寄せ船制度で、近郷から集められた、とあり、船でも、助郷のような制度があったのである。 街道に戻り、少し歩くと、関所の反対側に、江戸時代、享保四年から元文四年までの二十一年間無人島の鳥島で生き、生還した新居出身の船乗りの石碑があった。 |
 |
{左}旧旅籠 紀伊国屋
この辺りは、番所を囲む竹やらいがあったというから、関所を出入りする大御門を出たあたりだろう。 新居宿は、面番所でお調べを受けた後、大御門から出ると、西に向かった並んでいた。 宿場の人口は三千四百七十四人、家数七百九十七軒で、本陣は三軒あったが、脇本陣はなく、旅籠は二十六軒だった。 街道の左側に、旅籠の一軒であった紀伊国屋の建物がある。 この建物は、明治七年(1874)の大火で燃失、二階建てに建替えられ、一部増築もされたが、 |
 |
{左}飯田武兵衛本陣 江戸後期の旅籠建築様式が、随所に残されている。 江戸時代には、この家の前後左右に、旅籠が林立していたが、その中でも大きかった 、と、説明板にあった。 道を少し歩くと、T字路に突き当たり、泉町交差点で、正面の屋根の上に、浜名湖競艇の道案内が乗る家は飯田武兵衛本陣の跡である。 小浜、桑名、岸和田など、七十を数える大名が利用し、明治天皇も明治元年の巡幸、還巡幸など、合わせて、四回利用している。 |
 |
{左}成子交差点 建物は当時のものではなく、家の前に、それを示す石碑と案内板があるだけである。 東海道は、ここで左折するが、武兵衛本陣の左隣は、伊勢屋という旅籠で、その隣に、疋田八郎兵衛本陣があった。 疋田八郎兵衛は、庄屋や年寄役を務め、本陣には、吉田藩の他、御三家など、百二十の大名が利用した。 門構えと玄関のある建坪百九十三坪の屋敷だったが、この場所は空き地になり、それを示す石碑が建っていた。 また、八郎兵衛本陣の隣に幕末の絵図では、医者高須弥久が住んでいた。 |
 |
{左}寄馬跡 なお、もう一軒の疋田弥五郎本陣は、道が突き当たる手前右側にある疋田医院のところにあった。 その先には、寄馬跡と書か れた石碑がある。 宿場には公用の荷物や公用の旅人のため、人馬を提供する義務があり、東海道の場合、人足百人、馬百疋、 と決められ、それだけの数の人馬を用意していた。 しかし、それでは不足する場合は、助郷制度により、近隣の村々から集め られたが、とり寄せた人馬のたまり場が寄馬である。 |
 |
{左}諏訪神社 その先の少し入ったところに、諏訪神社があった。 諏訪神社は、遠州新居の手筒花火として有名で、古くから東海道の奇祭と して知られていた、という。 江戸時代享保年間頃(今から約二百八十年前)、新居関所を管理していた、三河の吉田藩から伝 えられた、と言われる。 吉田藩の花火は見たことが、新居の花火も、機会があれば見てみたい、と思った。 照明の脇に |
 |
{左}仲町発展会 仲町発展会と記されていた。 この先、白須賀宿から二川宿まで行くので、昼飯を買おうと 右側にある手作りパンの店に入た が、きつねずしなども売っていたので、パンとすしを買い、自動販売機でお茶を購入した。 その先の左側にあるのが、池田 神社である。 小牧長久手の戦いで、戦死した池田信輝の首を、徳川方の武将、長田伝八郎が、首実検ののち、ここに首塚を 築いたもので、享保二十年(1735)に池田神社となった。 右にカーブし、その先で更に左にカーブ |
 |
{左}棒鼻跡石標 し、その先で、国道1号線に合流する。 この左カーブの手前に、棒鼻跡の石標がある。 棒鼻とは駕籠の棒先の意味だが、 大名行列が宿場に入るとき、先頭(棒先)を整えたので、そう呼ぶようになった、といわれる。 ここは、新居宿の西の入口 にあたり、一度に多くの人が通行できないように、土塁が突き出て、枡形をなしていた。 今は土塁は崩されて跡形もなく、 道も増やされているので、枡形といわれても少しピンとこなかった。 ここで、新居宿は終わりである。 |