岡崎宿から池鯉鮒宿
 |
{左}カクキュー八丁味噌 名鉄岡崎公園駅で降り、前回終えた愛環の高架下の 岡崎城下二十七曲り 八帖村 の標石から、東海道の旅を再開した。 旧八帖村は、岡崎城から八丁(約1000m)の距離にあることから、名付けられた。 真っ直ぐの道が東海道で、八帖往還道である。 八丁蔵通りの表示があり、八丁味噌の郷である。 右折をすると、創業が正保年間のカクキュー八丁味噌(早川家)がある(資料館と味噌蔵を見学可) 八丁味噌は、明暦元年(1655)に、朝鮮通信使が岡崎に宿泊 |
 |
{左}まるや八丁味噌 した時、使節より伝えられたと、いわれる。 そのまま直進すると、左側に、永禄年間創業のまるや八丁味噌(大田家)がある。 両側には、古い家並が続いていた。 突き当たりの丁字路には、昭和六十一年に建てられた、左江戸、右西京、と刻まれた道標が 立っている。 東海道は、ここを右折して進むと、国道1号線を左折すると、矢作川に出た。 江戸時代の慶長六年(1601)に、東 海道の矢作川に架けられた橋は、ここから百メートル程下流で、長さ七十五間 |
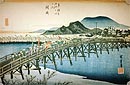 |
{左}広重の東海道五十三次 岡崎宿 (約136m)の土橋だった。 橋ができたことにより、これまで矢作川の川岸にあった宿場は存在価値をなくし、矢作宿は廃止に なった。 慶長十二年八月の大水により、橋は流失、八帖村の家屋も流される被害を受け、被害者達は、伝馬町の北側に移り、榎 町(祐金町)の人達は南側に住み替えて、現在の伝馬町になった、という。 寛永十一年(1634)、二百八間(約378m)の板橋が完成 した。 安藤広重は、岡崎宿の絵に、矢作川に架かる立派な木の橋が描いて |
 |
{左}矢作橋 いるが、その後、洪水などによる流失で、九回も架け替えが行われた。 幕末から明治十一年(1878)に、十回目の新橋が完成す るまでの約二十三年間は橋がなく、渡船による通行で、明治元年の明治天皇東征の際は、舟橋を利用した、とある。 幕末の尊王 攘夷の動きを考え、幕府は、橋を再建するのをあえて遅らせたのだろうか? 現在の橋は、昭和二十六年に完成した、全長二百七 十六メートルの橋であるが、橋のかけ替え工事中であった。 橋を渡ると、 |
 |
{左}出会いの像の案内 国道を横断して橋の右側に出た。 ここには、矢矧橋のたもとに槍を持つ武士と子供の像があるはずだった。 日吉丸(豊臣秀吉 の幼名)と阿波蜂須賀小六(正勝・蜂須賀家の始祖)とが、この河岸で運命の出会いをした姿を像にした、出会いの像である。 吉川英治の太閤記では、 無一文の日吉丸は腹を痛め、川に繋がれた小船で寝ていると、たたき起こしたのが川を渡る船を捜して いた小六だった、とあり、橋は出てこない。 出会いの像は、 橋の工事で一時撤去したようで、橋が完成したら、また、この 場所に置く、と断りがあった。 |
 |
{左}弥五騰神社 この先で左折し、入った細い道が東海道で、旧矢作村である。 右手に親鸞聖人の旧跡、とある勝蓮寺があり、左側には、近江屋 本舗という菓子屋があった。 古い家はほとんどないが、雰囲気のある家並みである。 弥五騰神社という変った名前の神社があ った。 十五世紀中期、碧海荘の地頭代だった土岐氏の一族の矢作城跡のようである。 鳥居手前の右側には、南無日蓮大菩薩・ ・、と刻まれた、大きな石柱が建っていた。 少し先の右側に、往生要集を著 |
 |
{左}誓願寺十王堂 わした恵心僧都が長徳三年(997)に建立した、と伝えられる誓願寺がある。 街道に面して十王堂があるが、「 寿永三年(1135)三月 、矢作の兼高長者の娘、浄瑠璃姫は、源義経を慕うあまり、菅生(すごう)川に身を投げた。 長者は、姫の遺体を当寺に埋葬し、十王堂を再建し、義経と浄瑠璃姫を弔う木像を作り、義経より姫に贈 られた名笛、薄墨と姫の鏡を安置した。 堂内には、十王の極彩色の像と地獄と天国の姿が描かれている。 なお、浄瑠璃姫と義経の伝承から 生まれたのが浄瑠璃節(義太夫節の別名)である。 」 と、案内板にあった。 |
 |
{左}熊野神社 東海道は短く、安城街道入口交差点で、国道1号線に合流。 ここから、二キロ程は、これといったものもなく、ただ黙々と国道 を歩いた。 鹿乗橋を渡り、宇頭町を過ぎると、安城市に入った。 尾崎東信号交差点の三叉路で、右側の松並木のある道が、 東海道である。 この道は、歩道帯がなく、線が引かれているだけである。 しばらく歩くと、うっそうとした森が見えてきた。 熊野神社で、境内は大変広い。 この辺りは、昭和十九年に、土浦海軍航空隊分遣隊として、 |
 |
{左}予科練の碑 創設された第一岡崎海軍航空隊の跡地である。 劣勢挽回のため、搭乗員養成を目的として創設されたが、翌年、終戦により解散 した。 予科練は、土浦だけだと思っていたが、戦況が急で慌てて岡崎に追加した、 という訳だが、戦争に負けたお陰で若い人 の命を落とさないですんだ。 鳥居の脇に、予科練の碑があった。 戦争は愚かなものだ、と今更ながら思う。 跡地は、戦後の 食糧難時代に開墾されて、農地になっていた。 |
 |
{左}一里塚跡の小さな石碑と目明しの松 鳥居の前を通り過ぎたところに、一里塚跡の小さな石碑と目明しの松があった。 その脇の案内板は、一里塚の説明かと思った が、鎌倉街道の説明で、 「 鎌倉幕府は、建久三年(1192)、鎌倉と京都の間に鎌倉街道を定め、六十三ヶ所の宿場を設置。 西三河は、知立市八橋の根曲がりの松から、安城市の不乗森(のらすのもり)神社を出て、証文山の東を通り、熊野神社に至 り、その後、西別所を、山崎町、岡崎市新堀町を経て、大和町桑子(旧西矢作)へ |
 |
{左} 宇頭茶屋説教所 通じていた。 」 と、あった。 少し歩くと、宇頭茶屋交差点になった。 旧宇頭村は、立場茶屋があったところである。 大 きな松がある妙教寺、内外神明社を過ぎると、宇頭茶屋説教所のバス停があり、右手に入ると、寺のような建物があった。 住職 がいる様子はない。 少し歩いた先は、江戸時代の大浜村で、ここにも茶屋があったようで、天保十四年(1842)には、宇頭茶屋と 大浜茶屋で、宿争いが起きている。 |
 |
{左}永安寺 雲龍の松 その先の右側の永安寺境内の右側に、枝を左右に大きく伸ばしている立派な松があった。 幹が上に伸びず、地を這うように伸びて、その形が雲を得て、まさに天に昇ろうとする龍を思わせることから、雲龍の松という名で呼ばれてきた。 樹高四メートル五 十センチ、枝張り東西十七メートル、南北二十四メートル、樹齢は三百年以上の老木で、県の天然記念物である。 なお、この寺には、大浜茶屋の庄屋で、村民の窮乏を見かねて、助郷の免除を願い出て、刑死され |
 |
{左}明治用水記念碑 た柴田助太夫の霊が祀られている。 浜屋バス停を過ぎると、右手に松の木が見えてきた。 明治川神社交差点を越えた右側に、明治用水の記念碑が幾つかあり、その中の一つに、明治十三年(1880)四月の新用水成業式(竣工式)に出席した松方正義が揮毫した、 「 疎通千里,利澤万世 」 と、刻まれた石碑もあった。 明治用水は、江戸時代の末期、碧海郡和泉村(安城市和泉町)の豪農、 都築弥厚が、碧海(へきかい)台地に、矢作川の水を引き、開墾を行う計画 |
 |
{左}明治川神社 で、始まった。 幕府の許可は 得られたが、弥厚が病死。 その後、岡本や伊豫田等が遺志を継いで、新たな計画を立てたが、 一部の農民の反対もあり、苦労の上、明治十三年に完成した。 道の左側に、明治川神社の石柱と鳥居があったので、入っていった。 明治川神社は、用水完成後設立が企画され、明治十七年に創建されたという神社で、明治用水の開発に功績 |
 |
{左}安城の松並木 のあった都築弥厚、岡本兵松、伊豫田与八郎等を祀っている。 街道に戻り、また、歩き始めた。 道の両側に、松並木が現れ、やがて、両側が工場地帯となったが、松並木は続いている。 しかし、あるところまで行くと、なくなった。 ところが、また、現れ、その後は現れたり消えたりを繰り返した。 松並木があるところには歩道もあり、松並木が途切れると歩道も消えてしまう。 黙々と歩き続けると、知立市に入り、来迎寺町の交差点に出た。 明治川神社から三キロ |
 |
{左}八橋無量寿寺への道標 弱だった。 交差点の右角の道とガードレールの間に、正面に、八橋業平作観音従是四丁半北 有 、脇に、八橋無量寺 と、刻 まれた古い道標があった。 これは、在原業平ゆかりの八橋無量寿寺への道標である。 折角なので、寄り道。 ここを右折し、 数分歩くと、無量寿寺に到着した。 無量寿寺は、臨済宗妙心寺派に属する寺で、奈良時代の慶雲元年(704)の創立といわれ、 弘仁十二年(821)にこの地に移され、無量寿寺となった。 その後、荒廃したのを文化九年 |
 |
{左}無量寿寺 (1812)、方巌売茶(ほうがん ばいさ)翁により再建され、杜若庭園もこの時完成した。 寺の本尊は、正観音像で、在原業平 の作と伝えられるものである。 本堂前の小高いところに、八橋古碑があった。 八橋古碑は、亀の台座の上に、碑柱が立つ亀甲 碑という、亀の形をした変わったもので、寛保二年(1741)の建立である。 碑文は、荻生徂徠の門人が、この地を訪れ、八橋と在 原業平の故事について、漢文でまとめたものであると、傍らの案内板にあった。 隣に、 |
 |
{左}伝説羽田玄喜二児の墓 「 かきつばた 我に発句の おもひあり (芭蕉) 麦穂なみ よるうるおいの里 (知足) 」という松尾芭蕉と下郷知足の 連句碑があった。 碑を建てたのは、知足の子孫、下郷学海で、安永六年(1777)の建立である。 芭蕉は、のざらし紀行の旅の 帰途、貞享三年(1685)四月、鳴海の俳人、下郷知足の家に泊り、歌会を開いた時の作いわれる。 寺の裏にまわると、 伝説羽田 玄喜二児の墓 と、書かれた二つの並んだ墓があった。 二児の水死を悲しみ、当寺で尼に |
 |
{左}無量寿寺 八橋 なった母親が 建てた墓で、村人の力で、入り江に八つの橋を架けたことから、この村は八橋と名付けられた、と伝えられる。 無量寿寺は、カキツバタで有名であるが、八橋を有名にしたのは、なんといっても、伊勢物語の第八話の東下りである。 ある男 (業平と想定されている)が都から道に迷いつつ、この地にたどり着いた。 川が幾筋も流れ、 水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を 八つにわたせるによりてなむ八橋といひける。 燕子花(かきつばた)が、水辺に美しく咲い |
 |
{左}業平井戸 ていたので、連れの者と かきつばた という五文字を句の上において歌を詠もう、ということになった。 その男は、 「 唐 衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思う 」 という歌を詠んだ。 業平が、茶を飲んだと いう井戸が残っていた。 また、花崗岩で作られた宝しょう印塔の杜若姫供養塔があった。 杜若姫は、小野中将篁(たかむら) の娘と伝えられ、在原業平が、東下りの時、在原業平を慕って来て、八橋の逢妻川で追いついたが、 |
 |
{左}淨教寺鐘楼門 業平の心を得ることができず、悲しんで、池に身を投げて果てた、と いう、悲しい話が伝えられている。 先程の道を戻り、 左側の淨教寺の角を右折する。 淨教寺の鐘楼門は、宝暦(1757)の建立であるが、延享元年(1744)に鋳造された鐘は、第2次大戦 時に供出したので、新しいものである。 その先の交差点を右折すると、道巾が狭い道になった。 鎌倉街道といわれる道で 道幅は車がすれ違うのは大変な狭い道である。 少し歩くと、左側の小高いところに、在原寺が |
 |
{左}在原寺本堂 見える。 寺に入る坂の途中に、 「 萩刈って 松籟ばかり 在原寺 経四楼 」 と、刻まれた常夜燈が建って いた。 在原寺は臨済宗妙心寺派の寺で、在原業平立像が祀られている。 寛平年間(889〜897)、在原塚を守る人の御堂として 創建された、と伝えられ、一時途絶えたが、文化六年(1809)に、方巌売茶によって、再建された。 本堂左側奥には、義玄句碑が あり、「 いつも聞く 家ははや寝て 遠砧(とうきぬた) 」 と、いう句が刻まれて |
 |
{左}種田山頭火句碑 いた。 市教育委員会の案内板によると、「 兼子義玄は、尾張藩士 の子として生まれたが、嘉永五年(1822)、在原寺に入寺、仏門に仕えるかたわら、 俳諧をたしなんだ。 義玄の俳風を慕って、 多くの門人が集まった。 」 と、ある。 種田山頭火の句碑には、 「 むかし男ありけりという松が青く はこべ花さく旅のある日のすなほにも 枯草にかすかな風がある旅で 業平塚にて 山頭 火 」 という句が刻まれているが、昭和十四年(1939)、山頭火 |
 |
{左}鎌倉街道の根上りの松 が当地を訪れた時、詠まれた句である。 寺を出て、街道を西に向かうと、左の小山に、鎌倉街道の根上りの松と呼ばれる黒松が あった。 安藤広重の東海道名所図会に描かれている松とも言われ、根の部分にあった土が、年月を経て流出し、根が上ったよう に見えることから、その名が付いた。 その先の名鉄三河線の踏み切りを渡ると、右側に小高い塚があるが、業平の菩堤を弔うた め築かれた業平塚である。 在原寺縁起に、「 寛平年間(889〜897)、業平の骨を |
 |
{左}業平塚の業平供養塔 分骨し、八橋川辺りの地に塚を築いた。 」 、と伝えられるもので、十メートルほどの高さだったが、隣に工場が出来ているた め、見晴らしはいいというものではなかった。 塚の上にある業平供養塔は、鎌倉末期頃、業平をしのんで建立されたもので、 塔身に、金剛界四仏と梵語で刻まれた、関西式といわれる宝篋印塔である。 傍らには、数百年もの年月を経た松があったが、伊 勢湾台風で枯死したので、今はない。 |
 |
{左}八橋伝説地碑 江戸時代、東海道を旅する人に、在原業平の古跡は人気があったようで、わざわざ遠回りして、この鎌倉街道を歩いたようである 。 塚の下に、八橋伝説地碑があり、この先に流れる逢妻川が、当時、蜘蛛の手のようになっていたようで、くもでが、歌の枕詞 になるくらい、有名だった、 と、書かれていた。 謡曲の杜若 の東下りの段には、 「 ささがにの蜘蛛手にかかる八橋や。 澤邊に匂う杜若。 在原の中将のはるばる来ぬと詠ぜしも。 今身の上に知られた |
 |
{左}来迎寺一里塚 り 」 とあり、 十六夜日記には、「 ささがにの蜘蛛手あやふき八橋を夕ぐれかけてわたりぬるかな 」 と、ある。 現在 の景色では、蜘蛛手にかかる川筋はぴんとこないが、狭間(はざま) のようなところだったのだろう。 来た道を戻り、無量寿寺 道標のある交差点を左折して、東海道に戻った。 少し歩くと、道の左側に来迎寺の一里塚があった。 左側だけか、と思った が、右の駐車場に入ると、民家の間にもう一つの一里塚があった。 少し歩くと、明治用水緑道 |
 |
{左}弘厚の夢の碑 の入口で、ここにも無量寿寺への道標が建っていた。 片方に、 従是五丁北 八橋業平作・・・ と、刻まれ、もう片方には、無 量寿寺 と、書かれている。 明治用水緑道は、明治用水を暗渠にした際、その上に造られた道で、整備された散歩道になってい る。 この道を行くと、ところどころに置かれた看板に、明治用水の歴史が解説されている。 公園の石碑に弘厚の夢と書かれて いたが、明治用水建設のきっかけを作った人である。 江戸時代の西三河と知多半島は、 |
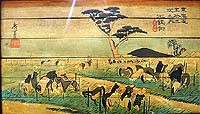 |
{左}広重の東海道五十三次池鯉鮒宿 河川のない荒地で、農民は、水の確保に苦労していたのである。 明治用水は、明治十二年(1879)に、工事を始め、明治十四年に 、西井筋が完成し、その後も工事が続いた。 戦後に、愛知用水が作られたのも、こうした先人の努力によることが大きい。 衣 浦有料道路を通りすぎると、松並木に入った。 安藤広重は、池鯉鮒宿を、 首夏馬市 と 題し、東野で行われた馬市の様子を描いている。 おびただしい馬のいななきが聞こえたことだろうから、この一帯のにぎやかだったことは想像できよう。 |
 |
{左}知立の松並木 松並木西の地名を引馬野と呼ぶのは、江戸時代には、ここで馬市が開かれていたことに由来する。 この松並木は、 知立の松並木と呼ばれ、慶長九年(1604)の幕府の五街道の制定により、一里塚と松並木の整備が義務付けられたが、今でも、 道巾六メートル、五百メートル程の区間に 百七十本ほどの松が残っている。 工場が立ち並び、自動車も通る環境の中で、健気に 頑張っていた。 年輪を重ねた松の枝は曲がり、二つとして同じものはなかった。 |
 |
{左}道祖神 俳人、麦人が、和田英作を当地に訪れた際に詠んだ句が、馬市句碑になっていた。 「 かきつばた 名に八ッ橋の なつかしく 蝶つばめ馬市 たてしあととめて 」 知立の松並木の枝ぶりに感心しながら歩くと、道の左側に、道祖神を見つけた。 道を歩いて行くと、馬市之跡碑があった。 市教育委員会の資料に、「 この松並木の特徴は側道を持つことだが、これは馬市の馬をつなぐためのものと推定される。 また、この付近には四百頭から |
 |
{左}知立の松並木 万葉歌碑 五百頭の馬が繋がれ、馬の値段を決めるところを談合松といった。 」 と、ある。 万葉歌碑には、大宝弐年(702)、持統天皇が三河行幸の際、詠まれた歌 「 引馬野爾 仁保布榛原 入乱 衣爾保波勢 多鼻能 知師爾 長忌寸 奥麻呂 」 ( ひきまのに にほふはりはら いりみだれ ころもにほはせ たびの しるしに ながのいみき おくまろ) が、刻まれていた。 傍らの説明板には、 この歌から天皇が駿河の興津とともにここに立ち寄られたことは明らか 、というよう なことが書かれていた。 |
 |
{左}小さな石仏 松並木が途切れるところの大きな松の木の下に、小さな石仏が祀られていた。 出たところに、国道1号線があったが、横断歩道 はないので、地下連絡道を歩き、道の反対側に出ると、東海道が残っていた。 東海道は直進し、左側の小さな社の石仏の前を通り り過ぎると、変則四叉路で、左手の踏み切りの先に、市役所があるせいか、左折する車で込んでいた。 そのまま直進し、山町 交差点に出る。 ここで寄り道。 右折して北に向かい、国道1号の交差点を渡り、 |
 |
{左}慈眼寺 幟がひらめく慈眼寺の境内に入っていった。 慈眼寺は、知多地方の観音霊場の一つである。 知立は、池鯉鮒とも書き、江戸時 代は、池鯉鮒の方が多く使われたようである。 古来より、馬市や木綿市が開かれた土地で、中世は鎌倉街道の要衡として栄え、江戸時代には東海道の宿場として賑わったところ。 また、木綿の集散地でもあった。 馬が運搬に使われた関係から、馬市が栄えたといわれる。 馬市は、四月二十五日に始まり、五月五日に終わった。 当初 |
 |
{左}馬頭観世音菩薩及家畜市場碑 は、知立宿の東入口にあたる東野で行われていたが、明治に入り、この寺の境内に移ったのである。 昭和初期までに、馬が牛に代わ ったものの、鯖市も兼ねて賑わったが、昭和十八年を最後に、幕を閉じた。 境内には、馬頭観世音菩薩及家畜市場、と書かれた 大きな石柱が建っていた。 傍らの草むらにも、馬の碑 刈谷馬車合資会社、と刻まれた石碑が残っている。 馬の碑は、街道で 亡くなった馬の供養碑で、刈谷馬車合資会社は、明治に入り各地に誕生した馬車を営業する会社の一つである。 しかし、馬車は、車の登場により、やがて 、終わりを |
 |
{左}池鯉鮒宿 問屋跡 告げた。 山町交差点まで戻り、東海道を西に向かう。 山町交差点を過ぎると、古い家が数軒あったが、江戸時代といえるもの ではなさそう。 明治四十一年(1908)に、建てられた常夜灯が古いという程度で、古いもの残っていない。 いよいよ、宿場の中 心に入る。 中町交差点は六差路なので、分かりにくいが、やや右に入る細い道が東海道である。 右側の銀座タワービルの駐車 場の前に、池鯉鮒宿問屋場之跡の石碑があった。 気を付けないと見つからない。 |
 |
{左}池鯉鮒宿 本陣跡 左側に、知立セントピアホテル、右手はコンサートホールがあり、宿場付近は、すっかり開発の波に飲まれてしまった感じである 。 脇本陣の表示はなくなっていて、その場所は分からなかった。 本陣は、この通りにあると思ったが、国道419号の知立駅 北口の交差点近くの道の右側にある貯水槽の脇に、本陣跡の石碑があった。 本陣は、峯家(杉屋本陣)だったが、没落したので、 寛文二年(1662)に、永田家(永田本陣)に代わった。 敷地面積は三千坪、建坪三百 |
 |
{左}大あんまき 坪と広大なものだったが、明治八年(1875)に取り壊された、と、傍らの案内板に書かれていた。 本陣は旧街道に面していたのだ が、土地が処分され、貯水槽のところだけが、かろうじて残ったのだろうと、推測できた。 街道に戻ると、その先の三叉路に、 知立名物、あんまきの元祖の小松屋がある。 大あんまきとは、どらやきの生地に餡を巻き込んたものだが、大きいので1つ食べ ると満腹する。 この先、道は鉤型に曲がっていて、小松屋を右折すると、左側に知立 |
 |
{左}知立城跡 城跡がある。 池鯉鮒には、代々、知立神社の神官を務めた氷見氏が築いた城があり、桶狭間の戦いで城が炎上した後、新たに御殿が 建てられたところである。 元禄の地震で、御殿が倒壊するまでは、将軍や藩主の休息所として使われたが、その後、壊されてし まった。 現在は児童公園になり、城址を示す石柱が一本建っているだけである。 歩いて行くと、了運寺につきあたったので、 ここを左に折れ、西町に入った。 西町を抜けると、右に入ったところに知立神 |
 |
{左}知立神社 社があり、街道の入口には常夜燈などが残っていた。 知立神社は池鯉鮒大明神といい、日本武尊ゆかりの神社である。 日本武尊東 征の折、当地において、皇祖の神々に平定の祈願を行い、無事、その務めを果したことにより、建国の祖神を祀ったのが神社の始 まりである。 参道にかかる太鼓橋(石橋)は、享保十七年の建設である。 境内右側の多宝塔は、嘉祥三年(850)の創建と伝えら れ、永正六年(1509)に再建されたもので、国の重要文化財に指定されている。 |
 |
{左}芭蕉句碑 寛政五年に建立されたという、芭蕉句碑は、少し分かりづらいところにある。 「 ふだんたつ 池鯉鮒の宿の 木綿市 芭蕉翁 」 江戸で有名になっていた知立木綿を題材に詠んだもので、芭蕉没後百年忌に、当地の有志が建立したものである。 五月二日〜三 日に行われる知立まつりといわれる神社の例祭では、偶数年に絢爛豪華な五台の山車が繰り出す。 また、外苑にある花しょうぶ は、明治神宮から |
 |
{左}総持寺 いただいた約六十品種の花しょうぶで、六月には多くの人で賑わう。 東海道に戻ると、その先に、総持寺がある。 元和弐年 (1616)に創建された玉泉坊が前身で、貞亨三年(1686)に総持寺に改称した。 明治五年(1572)、神仏混淆禁止令により、廃寺と なったが、大正十三年に、天台寺門宗として、この地に再興された。 明治以前の総持寺は、東海道の道筋、知立神社の手前の 右側にあったが、その跡には、樹齢二百年余の大銀杏が、今も、元気に葉を茂らせて |
 |
{左}逢妻橋 いる。 寺を出て少し歩くと、川があり、左に橋が見えてくる。 川の手前で左にカーブして、逢妻橋に出る。 逢妻川は、伊勢 物語の八橋に登場する逢妻男川が逢妻女川に合流した後の名前である。 逢妻川を渡ると、池鯉鮒宿は終わる。 岡崎宿〜池鯉鮒 宿は、十五キロであるが、途中に、カキツバタの無量寿寺や在原業平の旧跡が残るので、一日半を費やした。 |