桑名宿から四日市宿
 |
{左}神戸岡神社 今日は、名鉄桑名駅から、桑名宿を探訪して、四日市宿まで歩く。 桑名宿で時間をかけたので、桑名から四日市宿までは、十三 キロ程であるが、あんまりのんびりはしていられない。 桑名宿のはずれの矢田の火の見櫓の先で、街道は左折し、南下する。 少し歩くと、右側に神戸岡神社という小さな神社がある。 最初は、街道の反対側にあったが、明治二十九年、神社統合令によ り、立坂神社に合祀されたが、昭和三十年代に再度この地に移された。 |
 |
{左}了順寺 その先は、昔の大福村。 火の見櫓から七百メートル位歩くと、立派な構えの浄土真宗本願寺派の了順寺という寺院がある。 山 門は桑名城の遺物と伝えられる。 その先で見つけた江崎松原跡の案内板には、 「 七里の渡しから大福までの東海道は、両側に 家が建ち並んでいたが、江場から安永にかけての百九十二間 (約345m)は、両側とも家がなく、松並木になっていた。 眺望が よく、西には鈴鹿山脈が遠望され、東は伊勢湾が見られた。 」、 とあり、 |
 |
{左}城南神社 松並木は、昭和三十四年の伊勢湾台風頃までは残っていたようであるが、松の木は一本もなく、その上、両脇には家が建ち並んで いて、想像するのは困難だった。 了順寺から七百メートル位歩くと、鳥居の前に大神宮の一の鳥居下賜と書かれた石碑がある神 社がある。 城南神社で、伊勢神宮に天照大神と豊受大御神が鎮座する前、この地に仮座したことから、式年遷宮後の鳥居と建物 の一部が下賜されるという。 伊勢神宮の一の鳥居は、桑名宿の七里の渡し |
 |
{左}安永(やすなが)集落 の鳥居になり、その後、この神社の鳥居になるのである。 国道258号線に出たら、地下道を通って向こう側へ渡り、 そのま ま真直ぐ進む。 江戸時代の安永は、東海道の桑名宿の入口にある立場だった。 道は少し上りになり、ややカーブしているが、 右側に古い家が残っている。 江戸時代の安永は、町屋川(員弁川)の舟運の舟積場だったところである。 左側の藤棚のある料理 旅館の玉善は、江戸時代には茶屋を営み、街道名物の安永餅を売っていた、という。 |
 |
{左}伊勢両宮常夜燈 左手に国道が見えるが、小道を直進。 左側の楠は、樹齢二百年の老木で、注連縄(しめなわ)が結ばれていた。 右側の石積の上 の常夜燈は、桑名の根来市蔵という石工が彫った伊勢両宮常夜燈で、東海道の灯標として伊勢神宮の祈願を込め、桑名、岐阜の材 木商により、文化元年(1818)に寄進されたものである。 その前に、明治二十六年に建立された石造里程標が建っていて、正面に、 従町屋川中央北 桑名郡 、左面に、 距三重県県庁舎拾一里口町余 、 |
 |
{左}町屋川 と刻まれている。 そのまま進むと、川が見えるところで、行き止まり。 左手に橋が見える。 十返舎一九は、 「 旅人を 茶屋の暖簾に 招かせて のぼりくだりを まち屋川かな 」 、と詠んでいる。 案内板には、 「 寛永十二年(1635)にここから対岸に橋が架かった。 川の中州を利用し、大小 二つの板橋だったり、一つの板橋だったりした。 中央に馬がすれ違える |
 |
{左}町屋川からの展望 ように広くなっていた。 昭和十二年に国道1号線の橋が架かり、その橋はなくなった。 」 、 とあった。 ここには、橋がないので、左手に見える国道1号線の町屋橋を渡る。 桑名市はここまでである。 橋の上は風が強く、耳がちぎれるくらい寒く感じた。 右側に遠い先に、鈴鹿の山々が見えた。 左側は川越発電所と思うが、大きな煙突から煙がたなびいていた。 川を渡ると、三重郡朝日町縄尾である。 東海道は、橋を渡り終えたところで、右に曲がり、坂を下 |
 |
{左}山口誓子句碑がある店(振り返って写す) り、すぐに左折して、細い道に入る。 ここから近鉄伊勢朝日駅まで、約八百五十メートル。 道はやや上りであるが、江戸時代には、だらだら坂と呼ばれたようである。 道の両側は、民家で埋め尽くされていて、ほとんどが新しい家だが、一部古い家がある。 道の右側に、十一面観世音菩薩の石柱が建っていて、その先の右側には、真光寺がある。 そのまま行くと、左側のタバコの看板のある店前に、山口誓子の句碑があった。 その先の左側、黒い倉のような建 |
 |
{左}樹齢三百年余の榎 物前に、縄尾(なお)の一里塚があったことを示す石柱が建っていた。 その先の右側には東海道の道標がある。 富士の光、清鷹の看板を上げた安達本家という造り酒屋の前を通り過ぎると、東芝の工場が右にあり、左側に近鉄伊勢朝日駅がある。 ここから、朝日町のはずれの朝明川までは八百メートルほどの距離である。 踏み切りを渡ると、左側に宿駅四百年記念に建てたと思われる旧東海道の石碑がある。 十メートル先の榎(エノキ)は、樹齢三百年余で、東海道の並木の一本だった、とあった。 松の方は戦時中の松根油の採取のため切られて、残っ |
 |
{左}連子格子の家 ていなかった。 その先の右側に、連子格子が素晴らしい家があった。 少し歩くと旧小向村で、右側に、東海道の道標と御厨小向神社の石柱が建っていた。 その先の左側角に、橘守部旧蹟の表示があるが、ただの畑である。 橘守部は、この地の庄屋の家に生まれたが、父親が一揆加担の容疑で、家は破産し、ここを追われている。 その後、独学で国学を学び、香川景樹、平田篤胤、伴信友とともに、天保の国学四大家の一人に数えられた人物である。 |
 |
{左}浄泉坊 本居宣長を痛烈に批判し、古事記よりも日本書紀を重んじ、神話の伝説的な部分と史実の区分の必要性を説いた。 その先の右側 にある寺院は浄泉坊で、東海道を通る大名は、駕籠を降りて、黙礼をした、と伝えられる寺院である。 浄土真宗本願寺派である が、徳川家ゆかりのある奥方の菩提寺になっていたことがあり、山門や瓦に三葉葵の紋がついている。 その先は交差点で、左右 の道が最近造られたもののようである。 交差点を越えると、石垣の上に白い壁 |
 |
{左}三叉路 で覆われた西光寺という寺があるが、この寺も古い。 右側の細い道の角に、JR関西線朝日駅入口の表示板があり、百メートル奥に無人駅がある。 駅前を過ぎると、右側の柳屋という雑貨屋の先で、道が三叉路になっている。 東海道は左折し、すぐに右へカーブする。 その先は一本道である。 しばらく民家が続くが、なくなったところから、桜並木になる。 正面に伊勢湾岸道路が見えてきて、そのガートをくぐると、朝明川(あさけがわ)にでた。 朝明川は、壬申 |
 |
{左}多賀神社常夜燈 の乱の際、大海人皇子が伊勢神宮に遥拝し、戦勝を祈願した遼太川である、と伝えられる川である。 朝明川の堤にあると思った、弘化三年(1846)に建てられた常夜燈は、ここにはなかった。 街道脇から高速道路の手前にある道路の西方三十メートルほどのところに、昭和六年に移されていたのである。 なお、この常夜燈には、 多賀神社常夜燈 、 五穀成就 、 と刻まれている。 橋を渡ると、四日市市松寺に入る。 道の右側にある狭い道の角に、御厨神明社の大きな石柱が建っていた。 左側に、タカハシ酒造という造り酒屋があった。 左の石碑前の |
 |
{左}宝性寺 うす汚れた案内には、伊勢松寺の立場はこのあたりにあった、と書かれていた。 蒔田に入ると、右手に御厨神明神社があり、同じ境内に宝性寺があった。 宝性寺は、天平十二年(740)、聖武天皇の勅願で創建された、と伝えられる由緒ある寺だが、永禄十一年(1568)の伊勢長島の一揆で燃失、その後建てられたものも燃失した。 現在の建物は、文化十一年(1814)の建設と、鬼瓦の銘から推定できる、とあった。 本堂は、間向拝付き三間四方の入母 |
 |
{左}一里塚橋 屋造りの本瓦葺きである。 獅子の彫刻があったが、素晴らしいものだった。 境内に、御厨神明神社があった。 伊勢神宮の御厨の地に建てられたので、その名があるようで、以来、蒔田村の氏神として信仰されてきた、という。 三峡鉄道の高架下にあるJR関西本線の踏切を渡ると、百五十メートルほどで、やや変則の四差路があり、左にカーブした道を左折する。 その先の三峡鉄道と近鉄の高架をくぐると、小さな一里塚橋があるが、昔は庚申橋といっていた。 |
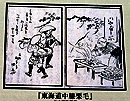 |
{左}東海道中膝栗毛 冨田(とみだ) その橋を渡ると、右側に、冨田一里塚跡の碑がある。 東海道の開設により、大名行列や伊勢参りなど、多くの旅人が行き来し、冨田付近はたいへんな賑わいを見せた。 立場になっていた冨田は、多く茶屋があったが、茶屋の名物は焼き蛤であった。 十返舎一九の東海道中膝栗毛では、喜多八が騒動を起こしている。 「 富田の立場にいたりけるに ここはことに焼はまぐりのめいぶつ、 両側に茶屋軒を並べ往来を呼びたつる声にひかれて茶屋に立ち寄り 」 とあり、弥次郎兵衛と喜多八の二人が焼き蛤でめしを食ったのはいいが、焼き蛤が喜多八 |
 |
{左}屋根神様 のへその下に落ちやけどするはめになり、 「 膏薬は まだ入れねども はまぐりの やけどにつけて よむたはれうた 」 と、いう狂歌が落ちになっている。 右側の連子格子の家の屋根に、陶器の神様が祀られていたが、家を守る守護神である。 こ のあたり一帯は、古代には海であったが、次第に陸地化した土地で、美味しい蛤がとれたのも、この土壌のおかげだろう。 桑名 の名物の蛤を土産にと |
 |
{左}八幡神社 願う声が高まり、誕生したのが、蛤を溜まり醤油で煮て作った佃煮で、 「 桑名の殿様 しぐれで 茶々漬 」 と、民謡にも唄わ れるほどの人気ぶりだった。 東海道名所図会にも、 「 初冬の頃美味なるゆえの時雨蛤の名あり、溜まりにて製す 」 、 と あるが、時雨蛤という風情ある名前は、芭蕉門下の各務至考の考案らしい。 残念なのは海が遠くなり、全然見えないこと。 ここが蛤の産地であることは想像できない。 道をすすむと、左側に八幡神社があった。 |
 |
{左}八幡神社 力石 冨田六郷氏神記に、 「 改安弐年(1279)に冨田地頭佐原豊前守政盛により東富田に勧請 された。 」 、と記されている神社で 、祭神は応神天皇である。 明治四十二年に神社統合令で、鳥出神社に合祀されたが、昭和四十年、現在地に社殿を建て、再建さ れたものである。 境内には、力比べに使われたという、およそ百キログラムの横長の丸い石(力石)が置かれていた。 江戸時代 には、八幡神社が富田の西端で、八幡の森が茂み、昼でも暗かったと、伝え |
 |
{左}富田山長興寺 られるが、今は近鉄の御蔭で、ここから冨田駅にかけての方が家が多い。 道をそのまま進むと寺に突き当たる。 突き当たりの寺は富田山長興寺で、十六羅漢堂がある。 東海道は、手前の三叉路のクリーニング屋の角を右に曲がり、仲町通りを歩く。 その先の右側に、富田地区市民センターがある。 その前に、右 富田一色、東洋紡績、川越村、と書かれた道標が建っていた。 これは大正六年十月に造られたもの。 近くに、明治天皇御駐れんの石碑が建っ |
 |
{左}明治天皇御駐れん跡碑 ていて、 「 明治天皇は、明治元年(1868)九月二十日、京都を発ち、二十五日、富田茶屋町の広瀬五郎兵衛方に御少憩になり、富田の焼き蛤を賞味になられた。 同年十二月十九日、京都に戻られる途中も、小休止された。 更に、明治二年に、神器を奉じて、東京に遷都されたときと明治十三年陸軍大演習で、行幸されたときも、寄られている。 明治天皇が休憩された屋敷は、東海道に沿った、現在の富田小学校から富田地区市民センターにかけてあった。 」 |
 |
{左}薬師寺 と、説明板にあった。 十四川に架かる十四橋に、十四川堤の桜並木は、両岸千二百メートルにわたって、ソメイヨシノが約八百本植えられていて、日本の桜の会より、全国表彰を受けた、という。 橋を渡ると、南富田に入る。 弘法大師が彫ったという秘仏の薬師如来を祀る薬師寺がある。 少し歩くと、旧茂福村で、突き当った三叉路に、新設用水道碑という大きな石碑が |
 |
{左}新設用水道碑と力石 あり、脇に力石が置いてあった。 今度は、大石が一つと小さな石が数個である。 案内板には、 「 明治時代中期、二つの寺の御堂を再建するため、土台石の奉納があった。 その際、地固めに集まった人達の間で、休憩時に奉納された石を持ち上げ、力競べを行わせた。 茂福地区では、その後も、大正の終りまで力競べが続いた。 」 と、あった。 東海道は三叉路を左折し、その先ですぐに右折する。 しばらく歩くと、右側に、茂福 (もちぶく)神社の石柱が |
 |
{左}羽津常夜燈 あるが、神社は、この奥(西)に三百メートル程行かなければならない。 そのまま進むと、産業道路の八田三丁目交差点にでる。 こ のあたりは、自動車販売店や工場が多い。 やや雑然とした家並みを少し歩くと、右側に、羽津の常夜燈といわれた燈籠があった 。 少し上ると、米洗川(よないがわ)があり、橋を渡ると羽津町になる。 しばらく歩くと、真央法願上座と書かれた石柱があ り、その脇に、小さなお堂の薬師堂があった。 |
 |
{左}大きな松の木 少し歩くと、一本だけぼつんと立つ大きな松の木がある。 斜めに傾いた枝が妙に良い感じである。 しばらく歩くと、志氏神社 の鳥居にきた。 志氏神社は、延喜式に記載がある古い神社である。 鳥居は、享保十年(1725)に建てられたものであるが、社殿 は、四世紀末に築造されたといわれる前方後円墳の前に建てられている。 境内の丹比屋主真人の歌碑は、聖武天皇に随行し、志 氏神社に詣でた時に、妻の無事を祈って詠んだ歌といわれる、万葉集の歌である。 |
 |
{左}志氏(しで)神社の二つの常夜燈 「 後れにし 人を偲はく 四泥の崎 木綿(ゆう)取り垂(し)でて さきくとぞ思ふ 」 鳥居の脇には、五穀成就と刻まれた常夜燈と八幡宮御神前と刻まれた常夜燈が建っていた。 境内にある狛犬は、神様から留守を 守るようにと、言いつけられたにかかわらず、遊びに出かけたため、左右の足を折られた、という言い伝えが残る。 古代には、 このあたり一帯が海で、四泥の崎と呼ばれていた泥地だった。 その土を使って焼かれたのが、四日市特産の万古焼 |
 |
{左}光明寺 で、桑名の豪商が、 元文年間(1736−41)に、窯を築いて焼いたのが始まり、といわれる。 製品に万古または万古不易の印を押したので、万古焼きと呼ばれるようになった。 その先には八十宮御遺跡という石碑がある、光明寺という大きな寺があった。 八十宮(やそのみや)は、吉子内親王(よしこないしんのう)の幼称で、異母兄に東山天皇、同母兄に有栖川宮職仁親王がいる。 生後一ヵ月で、時の将軍、徳川家継と婚約したが、夫となる家継も、わずか六歳だった。 |
 |
{左}くわな 四日市道道標 その二年後に、家継が死去したため、史上初の武家への皇女降嫁、関東下向には至らなかった。 その後、出家し、法号を浄琳院宮(じょうりんいんのみや)と称され、四十五歳で亡くなったとある。 光明寺を過ぎると、道は左へカーブ、すぐに右カーブする。 しばらく歩き続けると、国道1号線に合流し、東海道はここで終った。 国道を少し歩くと、金場町の交差点で、ここには小さな道標があった。 表面は、右くわな 左四日市道 、右面には、右四日市、大矢知道、 |
 |
{左}左に入る道(東海道) 左面に、大正十二年一月三日、陰刻に、羽津四区除雪紀・・、と刻まれている。 七百メートルほど、国道を歩くと、左に入る道 がある。 これが東海道で、この先百メートルほど、道が残っている。 その先の左側にあるのは、多度神社で、明治四十二年に 海蔵神社に合祀されたが、大正九年に再建されたものである。 そのまま歩くと、海蔵川に突き当たり、東海道は途切れてしま う。 江戸時代には、川に土橋が架かっていた。 元禄三年(1690)の東海道分間之図 |
 |
{左}三ツ谷一里塚碑 には、海蔵川に突き出た辺りに、一里塚が記されている。 昭和二十年に川を拡張した際、一里塚だったところは、川の中に入ってしまった。 現在土手際にある三ツ谷一里塚跡の石碑は、最近になって建てられたもの。 東海道分間之図には、海蔵川をかいぞ川と書いてあったが、国道に架かる橋には、かいぞうばしと刻まれていた。 国道にかかる海蔵橋を |
 |
{左}嶋小餅屋
渡り終えたら、すぐ左折すると東海道に入れる。 といっても、古い家がある訳でもなく、民家と商店が続くだけであ る。 川原町の交差点で、大きな道を横断し、少し歩くと前方に三滝橋が見えてくるが、手前の小さな橋の脇に、嶋小のだんこの 看板を架けた嶋小餅屋があった。 三滝橋の手前の民家のような造りの家には、創業元禄 文蔵餅 三滝屋という看板があった。 三滝橋を渡ると、四日市宿に入る。 四日市は、かっては浜辺の美しいところで、諸国の |
 |
{左}広重の東海道五十三次四日市宿 物産が集散する港町として栄えたところである。 江戸時代の前に、数多くの市場が開かれ、やがて、毎月四日に立つようになっ た。 そこから四日市の名がついた、と言われる。 広重の四日市宿の浮世絵は、川に突き出た縄手道の上に、突然強風が吹き、 吹き飛ばされた笠を追う男と、板橋を歩いて平然と立ち去る男を描いている。 浮世絵にある三重川は、三滝川のことで、海蔵橋 から約七百メートルほどの距離だった。 |
 |
{左}三滝橋 四日市宿は、三滝橋を渡ったところから諏訪神社の手前までの六町二十間(約700m)の短い宿場町であるが、宿内人口は六千八百 九十人 、家数千五百六十一軒 、本陣が二軒、旅籠が百十一軒もあった。 これは、伊勢参詣に使われる伊勢街道の分岐点にあっ たことで、陸海交通の要地で、商業の盛んな土地だったことによる。 江戸時代の寛永年間に刊行された、 東海道名所図会には、 「 当駅海陸都会の地にして商人多く、宿中繁花にして、旅舎に招婦見えて |
 |
{左}天文十九年創業の笹井屋 いと賑はし 」 、と書かれている。 三滝橋を渡ると、右側に、天文十九年(1550)創業という、老舗の笹井屋という菓子屋がある 。 名物のなが餅を売る店である。 津三十六万石藤堂家の始祖、藤堂高虎が、足軽時代から、 吾れ武運の長き餅を食うは幸先よ し と、好んで食べたという菓子で、長き餅の名の通り、細長い餅の中に、餡を入れて焼いた素朴な味で、程よい甘いが残る。 飽 食の時代の今日では、さほど美味いと思えないが、当時は、最高のお菓子であった |
 |
{左}黒川農薬店(黒川本陣跡) のに違いない。 道の左右には、普通の家やビルが建っていて、当時の建物は皆無である。 右側の福生医院が問屋跡で、近藤建 材店が帯や本陣跡、その先にある黒川農薬店が、黒川本陣跡である。 表示もないので、自分で確認するしかない。 そのまま歩 くと、交差点にでるので、交差点を越えて、正面にぶつだん屋と書かれた看板のあるビル前に出る。 道はここで右にカーブする が、カーブする右側に、江戸道の道標がある。 |
 |
{左}江戸道道標 すぐ江戸道、すぐ京いせ道、京いせ道・ゑどみち、文化庚午冬十二月建、書かれた道標である。 文化七年に造られ、この先の江 戸の辻に建っていたものを、昭和二十八年に複製し、当地に置いた、とあり、物は個人蔵とのこと。 東海道は、江戸時代には、 ここから諏訪神社の前に向かって、斜めに横断していたが、区画整理で様相を一変し、それを辿ることはできない。 この道標 が、このあたりが宿場の中心地だったことを暗示している感じがした。 道案内に従って、道標のところで右に曲がり、国道1 号線に出たら左折、最初の信号で国道を渡り、正面の |
 |
{左}諏訪神社 アーケードのスワマエ表参道に入った。 道標のあったところが中部(旧南町)で、諏訪神社が諏訪栄町(旧新田町)で 、この区画(整理された地域 ) に、四日市場と呼ばれた市場があったが、今はその痕跡すら残っていない。 表参道商店街入口 右側に、諏訪神社がある。 建仁弐年(1202)、信州諏訪の諏訪大社に勧請し、分祀した神社で、当地の産土社である。大四日市祭 の名で行われる諏訪神社の祭礼が、江戸時代の東海道名所図会に、 「 祭式の楽車(だんじり) |
 |
{左}鵜ノ森神社 ねりものあり、近隣群集して賑しき神事也 、 」 と、紹介されている。 近鉄四日市駅の 西側の鵜ノ森公園は、室町時代に、浜田城があったところ。 浜田城は、文明二年(1470)に、田原孫太郎景信の三男、田原 (赤堀)美作守忠秀が築城し、藤綱、元綱など、四代続いたが、織田信長の部将、滝川一益に攻略されて落城した。 なお、 景信は、俵藤太秀郷の子孫とされ、隣の鵜ノ森神社には、俵藤太秀郷が祀られている。 これで、四日市宿は終わりである。 |