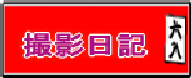

2009年12月25日
今年も終り

今年の経済はどん底で、企業の業績がひどいため、それが国や地方の財政に影響を少しづつ与え始めている。 トヨタ
自動車がある豊田市さえ、住民サービスに変化をきたし始めたと聞いた。 トヨタが儲けた時、徴収した税金は
プールされていないのだろうか、と思う。 行政はいざという時に備える姿勢がないように見えるが・・・・
それはともかく、今年はあと少しで終りである。 9月に妻に病気が見つかり、入院して手術し、自宅で療養すること
になった。 命にかかわる手術とあって、落着きのない日々を送ったが、退院して1月余、身体が自由ににならないので、
家事は小生の仕事になったが、家族全員で正月が迎えられるのが一番の幸せと実感している今日この頃である。
そのようなこともあり、今年の秋は京都に日帰りで
出かけただけだった。 そのした私を見た家内は、名古屋駅
の電飾を見に行ってきてという。
そうした声に後押しされて見にいったが、LSDの照明による四季を表現した電飾はなかなか良かった。

2009年11月20日
紅葉の光明寺

JR東海の秋のキャンペーンポスターに光明寺があった。 これまで京都に行っても、京都市内か宇治市や大津市であった。
JR東海でも京都か奈良が多いような気がする。 光明寺てどこにあるの?という感じ・・・・
京都を歩こう るるぶ を開くと、洛西 大原野のページにあった。 手つかずの自然に恵まれた山寺を風情を味わう、
とあり、観光から取り残されたところのようである。 そこには大原野神社や勝持寺、十輪寺などが紹介されているが、
光明寺は長岡八幡宮や乙訓寺と共に、ひと足のばそうと書かれた欄外に紹介されていた。
訪れたびっくり、多くの観光客、そして、なにより、驚いたのは見事な紅葉である。 人が多すぎて、よいアングルから
狙いなかったので、次回は早朝の人のいない時に訪れてみたい。

2009年11月20日
紅葉の野宮神社

今年の京都の紅葉は良いようだと聞いたので、日帰りで出かけた。 これまで二尊院には訪れていないので、これを主体
に嵯峨野を廻ることにする。 その為、早朝に名古屋を出て、京都駅で嵯峨野線に乗り換えて、嵯峨嵐山駅には
8時過ぎには着いた。 まだ早いので嵯峨釈迦堂と呼ばれる清涼寺へ行った。 寺務所の前にある庭には楓の木が数本あっ
たが、これはと思える景色ではなかった。 定刻に、二尊院に入り、境内をゆっくり見てまわることができた。 その後、
縁結びの神で人気のある野宮神社へ行った。 社殿の前の黄色から橙に色を変えようとする木と社殿の柵の朱色を入れて
写してみた。 人が次から次にくるので、それを避けて撮るのは忍耐とタイミングがいるが・・・・
なお、二尊院で撮った写真の一枚は、
Gallery−Autumn
の中に掲載しています。

2009年9月20日
ジュゴンへの餌やり
 友人と二泊三日で鳥羽、伊勢を旅行することになり、最初に訪れたのが鳥羽である。 鳥羽の見るところを検索すると、
御木本真珠島や鳥羽湾巡りと鳥羽水族館が出てくる。 どれも以前に行ったところであるが、神奈川に住む友人はすべてが
始めての経験という。 当日は時間の制約で、鳥羽湾巡りと鳥羽水族館で終わった。 遊覧船による鳥羽湾巡りはこれまで
数回行ったいたので、始めてイルカ島に寄った。 鳥羽水族館は久し振りなので、丹念に見てまわった。 最近の水族館
は大型水槽はごく普通になっている。 また、イルカショーは人が乗って水中を泳ぐというのもあり、水族館間の競争が
激しい。
かってラッコの餌をやるのが人気で開館当時多くの人を集めたが、それは過去の話。 最近の目玉は思ったら、ジュゴン
に餌をあげることのようである。 ジュゴンは草食動物のようで、海草を食べるようであるが、水に潜った飼育員が
あげていたのは人参だった。 ジュゴンはのんびりしているので、亀に時々横取りされる様は観客は笑いながら見ていた。
友人と二泊三日で鳥羽、伊勢を旅行することになり、最初に訪れたのが鳥羽である。 鳥羽の見るところを検索すると、
御木本真珠島や鳥羽湾巡りと鳥羽水族館が出てくる。 どれも以前に行ったところであるが、神奈川に住む友人はすべてが
始めての経験という。 当日は時間の制約で、鳥羽湾巡りと鳥羽水族館で終わった。 遊覧船による鳥羽湾巡りはこれまで
数回行ったいたので、始めてイルカ島に寄った。 鳥羽水族館は久し振りなので、丹念に見てまわった。 最近の水族館
は大型水槽はごく普通になっている。 また、イルカショーは人が乗って水中を泳ぐというのもあり、水族館間の競争が
激しい。
かってラッコの餌をやるのが人気で開館当時多くの人を集めたが、それは過去の話。 最近の目玉は思ったら、ジュゴン
に餌をあげることのようである。 ジュゴンは草食動物のようで、海草を食べるようであるが、水に潜った飼育員が
あげていたのは人参だった。 ジュゴンはのんびりしているので、亀に時々横取りされる様は観客は笑いながら見ていた。

2009年8月6日
しらびそ高原
 しらびそ高原は、飯田市上村にある交通が辺鄙なところである。 江戸時代、上村には秋葉街道が通り、街道には静岡県に
ある秋葉山へ訪れる旅人が歩いていた。 そのルートが国道152号となっているのだが、地蔵峠の付近やq青崩峠付近は今も
開通の見込みがない。 そうした上村に興味を持ったのは、急な七曲がり坂に民家がある長野県の観光ポスターに、日本の
チロルとあるのを見たことによる。 しかし、道は狭いようで、行っても駐車できるところもないと困る。 そうした時、
ある旅行会社からしらびそ高原ハイクの案内を受けたので、下見を兼ねて申込をした。 例年ならこの時期は快晴が続くと
予想して申し込んだが、長梅雨の影響で中央アルプスが展望できるしらびそ峠はガスがかかり一寸先も見えない状態
だった。 その後、御池山ハイキングコースを歩いたが、ずーっと霧雨で、頂上の1905mの御池山からは南アルプスの
光岳や大沢岳が展望できるはずだったが、百メートル先の尾根がやっという状態だった。 合羽で汗をかいた後、ハイラン
ドしらびそで風呂に入り、帰宅の途についた。
しらびそ高原は、飯田市上村にある交通が辺鄙なところである。 江戸時代、上村には秋葉街道が通り、街道には静岡県に
ある秋葉山へ訪れる旅人が歩いていた。 そのルートが国道152号となっているのだが、地蔵峠の付近やq青崩峠付近は今も
開通の見込みがない。 そうした上村に興味を持ったのは、急な七曲がり坂に民家がある長野県の観光ポスターに、日本の
チロルとあるのを見たことによる。 しかし、道は狭いようで、行っても駐車できるところもないと困る。 そうした時、
ある旅行会社からしらびそ高原ハイクの案内を受けたので、下見を兼ねて申込をした。 例年ならこの時期は快晴が続くと
予想して申し込んだが、長梅雨の影響で中央アルプスが展望できるしらびそ峠はガスがかかり一寸先も見えない状態
だった。 その後、御池山ハイキングコースを歩いたが、ずーっと霧雨で、頂上の1905mの御池山からは南アルプスの
光岳や大沢岳が展望できるはずだったが、百メートル先の尾根がやっという状態だった。 合羽で汗をかいた後、ハイラン
ドしらびそで風呂に入り、帰宅の途についた。
訪問しようと思っている日本のチロルはバスではいけない
狭い急勾配であることが確認できたのは収穫だった。

2009年6月15日
梅宮大社

前日同窓会があり、その後二次会に参加し、ホテルに泊まった。 ホテルにあった京都いいとこマップという小冊誌を
見ていると初夏の花咲くさんぽ道というページが目に付いた。 その中に写真入りで紹介されていたのが、梅宮大社で
ある。 これまで訪れたこともない神社なので、案内に従い、宿泊した四条大宮から市バスでいった。 梅宮大社の
歴史は古く、延喜式では名神大社に列し、仁明天皇の外戚の氏神として二十二社にも列している、とある。 また、古くから
造酒の神として有名であるとあり、それを証明するように、酒造会社の酒樽が並んで置かれていた。 小冊誌に紹介のあった
梅宮神苑に入ると、道の両側に植えられているアジサイは見ごろで、池の周りには無数の花菖蒲が咲いていた。
池の向こうに見えるのは、芦のまろ屋とも呼ばれる茶室、池中亭で、池の傍らには、百人一首の大納言
源経信が詠んだ
「 夕されば 門田の稲葉 訪れて 芦のまろ屋に 秋風ぞ吹く 」 の歌碑があった。

2009年6月9日
奥山半僧坊

静岡県磐田市の見附宿で、東海道と別れて、浜名湖の北側を通り、本坂峠を越えて、愛知県の御油宿で東海道と合流する
のが姫街道である。 小生は数回に分けてこの街道を歩いたが、その途中で立ち寄ったのが、奥山半僧坊である。 奥山
半僧坊の道標を街道歩きでしばしば見たので、どういう寺だろうと
訪れた。 訪れると、臨済宗の方広寺という寺で、その寺院が大火で燃えたとき、開創の無文元選禅師(円明大師)に仕えた
半僧坊大権現を祀った半僧坊仮堂と開山円明大師の墓地が焼け残ったことから、火除けの神として、有名になった、とあ
った。 森閑とした境内には無数の羅漢像があった。 円明大師が中国の天台山で、石橋にお茶を献じられた時、羅漢が
姿を現した、という故事にちなむもので、宝暦年間から明和七年(1770)に作られたものである。 一体づつ表情が異なり、
面白かった。

2009年4月19日
白川郷の春

麻生内閣の景気対策の一環とした、3月末から土日曜日は高速道路をどこまで走っても千円という施策が始まったので、
これを利用して、これまで行ったことがなかった飛騨白川郷へ行った。 行きは順調で2時間程で着いたが、帰りは小生の
ような1000円組が多く、その為、渋滞して4時間以上かかった。
白川郷で合掌造りの家が多く残っているのは荻町集落である。 ここは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されて
いる。 集落はずれの荻町城跡の展望台から下を眺めると、集落が一望できた。 その後、集落をくまなく歩いた。
名古屋に比べて、春が遅く、集落のあっちこっちで満開の桜が咲き誇っていた。
右写真は、国の重要文化財に指定されている和田家とそこで見た桜である。

2009年3月15日
土肥から見た富士山

東京から伊豆の熱川温泉で集まるので来ないかの誘いがあり、1泊2日ならいけると返事する。 東京組は電車で来るとあ
ったが、新幹線で往復するのも芸がない。 これまで行けないでいた西海岸をドライブして、修善寺に出て、熱川に
入るというコースを計画した。 高速道路は早朝4時前にICから入ると、深夜割引で5割の値引きが受けられるので、当日
は自宅を3時半前に出た。 高速で走ると早く着きすぎるので、スピードを落として走り、富士川SCに寄り、コンビニで
食べ物を調達して、腹を満たし、沼津ICで降り、ナビの指定した通り走った。 すると土肥の町に出たので、車を停めて
歩いたが、富士山は見えない。 その代わり、土肥温泉は、江戸時代、幕府の金の鉱山があり、その鉱山の採掘現場からお湯が出たのが、起源であること
を知った。
土肥温泉を出ると、カーブが続く坂があり、上っていくと海が展望できるところがあり、そこからは雲ひとつない富士山を
見ることができた。

2009年3月8日
斎 宮

伊勢街道を歩いた時、三重県明和町の斎宮跡に立ち寄った。 斎宮とは、に伊勢神宮に天皇の名代として奉仕した斎王の宮
殿と斎宮寮という役所のあったところである。 天皇が即位するたびに、伊勢神宮に天皇の名代として奉仕する斎王が
未婚の皇女の中から選ばれた。 この制度は、平安時代から南北朝時代まで六百六十年間も続き、その間、記録では六十人
余の斎王がいた、とある。 中には恋人がいたのに、中を割かれ、泣きながら、都を下って行った姫君もいたという。
その後、斎宮跡は歴史の彼方に消えていたのであるが、戦後になり、跡地が保存され、最近発掘調査が行われるようになっ
た。 今のところ、斎宮跡は確認されていないようである。
そうしてロマンあるところに、菜の花が咲き乱れていた。

2009年1月12日
墨俣一夜城

太閤秀吉が、木下藤吉郎時代に木曽川の流れる敵地に一夜で城を築いた話は有名である。 吉川英治の太閤記では、東濃
の武将を調略して味方につけ、土豪の蜂須賀小六を使い、上流から資材を乗せた筏を下らせて、一気に砦を築き、敵の
反撃を食い止め、美濃攻略に糸口をつけた、とある。
愛知県に住んでいながら、墨俣は一度も訪れたことがなかったが、美濃路を歩く際、ここを通ることが分かり、立ち寄った。
行ってみると、立派なお城があるではないか?
この城は、竹下内閣のふるさと創生資金1億円を使って、当時の墨俣町は大垣城を模した天守と金のしゃちほこを造り、
墨俣一夜城歴史資料館として公開したものである。 道理でどこかで見た城と思った。
木下藤吉郎が築いた墨俣城は木造の砦で、この模擬天守とはまったく無関係であるが、資料館には木下藤吉郎の一夜城築城
の様子をはじめ、墨俣の歴史資料や風土を紹介しているので、資料館として割り切れば許されるだろう。

最新の日記帳に戻る

 今年の経済はどん底で、企業の業績がひどいため、それが国や地方の財政に影響を少しづつ与え始めている。 トヨタ
自動車がある豊田市さえ、住民サービスに変化をきたし始めたと聞いた。 トヨタが儲けた時、徴収した税金は
プールされていないのだろうか、と思う。 行政はいざという時に備える姿勢がないように見えるが・・・・
今年の経済はどん底で、企業の業績がひどいため、それが国や地方の財政に影響を少しづつ与え始めている。 トヨタ
自動車がある豊田市さえ、住民サービスに変化をきたし始めたと聞いた。 トヨタが儲けた時、徴収した税金は
プールされていないのだろうか、と思う。 行政はいざという時に備える姿勢がないように見えるが・・・・ JR東海の秋のキャンペーンポスターに光明寺があった。 これまで京都に行っても、京都市内か宇治市や大津市であった。
JR東海でも京都か奈良が多いような気がする。 光明寺てどこにあるの?という感じ・・・・
JR東海の秋のキャンペーンポスターに光明寺があった。 これまで京都に行っても、京都市内か宇治市や大津市であった。
JR東海でも京都か奈良が多いような気がする。 光明寺てどこにあるの?という感じ・・・・ 今年の京都の紅葉は良いようだと聞いたので、日帰りで出かけた。 これまで二尊院には訪れていないので、これを主体
に嵯峨野を廻ることにする。 その為、早朝に名古屋を出て、京都駅で嵯峨野線に乗り換えて、嵯峨嵐山駅には
8時過ぎには着いた。 まだ早いので嵯峨釈迦堂と呼ばれる清涼寺へ行った。 寺務所の前にある庭には楓の木が数本あっ
たが、これはと思える景色ではなかった。 定刻に、二尊院に入り、境内をゆっくり見てまわることができた。 その後、
縁結びの神で人気のある野宮神社へ行った。 社殿の前の黄色から橙に色を変えようとする木と社殿の柵の朱色を入れて
写してみた。 人が次から次にくるので、それを避けて撮るのは忍耐とタイミングがいるが・・・・
今年の京都の紅葉は良いようだと聞いたので、日帰りで出かけた。 これまで二尊院には訪れていないので、これを主体
に嵯峨野を廻ることにする。 その為、早朝に名古屋を出て、京都駅で嵯峨野線に乗り換えて、嵯峨嵐山駅には
8時過ぎには着いた。 まだ早いので嵯峨釈迦堂と呼ばれる清涼寺へ行った。 寺務所の前にある庭には楓の木が数本あっ
たが、これはと思える景色ではなかった。 定刻に、二尊院に入り、境内をゆっくり見てまわることができた。 その後、
縁結びの神で人気のある野宮神社へ行った。 社殿の前の黄色から橙に色を変えようとする木と社殿の柵の朱色を入れて
写してみた。 人が次から次にくるので、それを避けて撮るのは忍耐とタイミングがいるが・・・・ 友人と二泊三日で鳥羽、伊勢を旅行することになり、最初に訪れたのが鳥羽である。 鳥羽の見るところを検索すると、
御木本真珠島や鳥羽湾巡りと鳥羽水族館が出てくる。 どれも以前に行ったところであるが、神奈川に住む友人はすべてが
始めての経験という。 当日は時間の制約で、鳥羽湾巡りと鳥羽水族館で終わった。 遊覧船による鳥羽湾巡りはこれまで
数回行ったいたので、始めてイルカ島に寄った。 鳥羽水族館は久し振りなので、丹念に見てまわった。 最近の水族館
は大型水槽はごく普通になっている。 また、イルカショーは人が乗って水中を泳ぐというのもあり、水族館間の競争が
激しい。
かってラッコの餌をやるのが人気で開館当時多くの人を集めたが、それは過去の話。 最近の目玉は思ったら、ジュゴン
に餌をあげることのようである。 ジュゴンは草食動物のようで、海草を食べるようであるが、水に潜った飼育員が
あげていたのは人参だった。 ジュゴンはのんびりしているので、亀に時々横取りされる様は観客は笑いながら見ていた。
友人と二泊三日で鳥羽、伊勢を旅行することになり、最初に訪れたのが鳥羽である。 鳥羽の見るところを検索すると、
御木本真珠島や鳥羽湾巡りと鳥羽水族館が出てくる。 どれも以前に行ったところであるが、神奈川に住む友人はすべてが
始めての経験という。 当日は時間の制約で、鳥羽湾巡りと鳥羽水族館で終わった。 遊覧船による鳥羽湾巡りはこれまで
数回行ったいたので、始めてイルカ島に寄った。 鳥羽水族館は久し振りなので、丹念に見てまわった。 最近の水族館
は大型水槽はごく普通になっている。 また、イルカショーは人が乗って水中を泳ぐというのもあり、水族館間の競争が
激しい。
かってラッコの餌をやるのが人気で開館当時多くの人を集めたが、それは過去の話。 最近の目玉は思ったら、ジュゴン
に餌をあげることのようである。 ジュゴンは草食動物のようで、海草を食べるようであるが、水に潜った飼育員が
あげていたのは人参だった。 ジュゴンはのんびりしているので、亀に時々横取りされる様は観客は笑いながら見ていた。  しらびそ高原は、飯田市上村にある交通が辺鄙なところである。 江戸時代、上村には秋葉街道が通り、街道には静岡県に
ある秋葉山へ訪れる旅人が歩いていた。 そのルートが国道152号となっているのだが、地蔵峠の付近やq青崩峠付近は今も
開通の見込みがない。 そうした上村に興味を持ったのは、急な七曲がり坂に民家がある長野県の観光ポスターに、日本の
チロルとあるのを見たことによる。 しかし、道は狭いようで、行っても駐車できるところもないと困る。 そうした時、
ある旅行会社からしらびそ高原ハイクの案内を受けたので、下見を兼ねて申込をした。 例年ならこの時期は快晴が続くと
予想して申し込んだが、長梅雨の影響で中央アルプスが展望できるしらびそ峠はガスがかかり一寸先も見えない状態
だった。 その後、御池山ハイキングコースを歩いたが、ずーっと霧雨で、頂上の1905mの御池山からは南アルプスの
光岳や大沢岳が展望できるはずだったが、百メートル先の尾根がやっという状態だった。 合羽で汗をかいた後、ハイラン
ドしらびそで風呂に入り、帰宅の途についた。
しらびそ高原は、飯田市上村にある交通が辺鄙なところである。 江戸時代、上村には秋葉街道が通り、街道には静岡県に
ある秋葉山へ訪れる旅人が歩いていた。 そのルートが国道152号となっているのだが、地蔵峠の付近やq青崩峠付近は今も
開通の見込みがない。 そうした上村に興味を持ったのは、急な七曲がり坂に民家がある長野県の観光ポスターに、日本の
チロルとあるのを見たことによる。 しかし、道は狭いようで、行っても駐車できるところもないと困る。 そうした時、
ある旅行会社からしらびそ高原ハイクの案内を受けたので、下見を兼ねて申込をした。 例年ならこの時期は快晴が続くと
予想して申し込んだが、長梅雨の影響で中央アルプスが展望できるしらびそ峠はガスがかかり一寸先も見えない状態
だった。 その後、御池山ハイキングコースを歩いたが、ずーっと霧雨で、頂上の1905mの御池山からは南アルプスの
光岳や大沢岳が展望できるはずだったが、百メートル先の尾根がやっという状態だった。 合羽で汗をかいた後、ハイラン
ドしらびそで風呂に入り、帰宅の途についた。  前日同窓会があり、その後二次会に参加し、ホテルに泊まった。 ホテルにあった京都いいとこマップという小冊誌を
見ていると初夏の花咲くさんぽ道というページが目に付いた。 その中に写真入りで紹介されていたのが、梅宮大社で
ある。 これまで訪れたこともない神社なので、案内に従い、宿泊した四条大宮から市バスでいった。 梅宮大社の
歴史は古く、延喜式では名神大社に列し、仁明天皇の外戚の氏神として二十二社にも列している、とある。 また、古くから
造酒の神として有名であるとあり、それを証明するように、酒造会社の酒樽が並んで置かれていた。 小冊誌に紹介のあった
梅宮神苑に入ると、道の両側に植えられているアジサイは見ごろで、池の周りには無数の花菖蒲が咲いていた。
池の向こうに見えるのは、芦のまろ屋とも呼ばれる茶室、池中亭で、池の傍らには、百人一首の大納言
源経信が詠んだ
前日同窓会があり、その後二次会に参加し、ホテルに泊まった。 ホテルにあった京都いいとこマップという小冊誌を
見ていると初夏の花咲くさんぽ道というページが目に付いた。 その中に写真入りで紹介されていたのが、梅宮大社で
ある。 これまで訪れたこともない神社なので、案内に従い、宿泊した四条大宮から市バスでいった。 梅宮大社の
歴史は古く、延喜式では名神大社に列し、仁明天皇の外戚の氏神として二十二社にも列している、とある。 また、古くから
造酒の神として有名であるとあり、それを証明するように、酒造会社の酒樽が並んで置かれていた。 小冊誌に紹介のあった
梅宮神苑に入ると、道の両側に植えられているアジサイは見ごろで、池の周りには無数の花菖蒲が咲いていた。
池の向こうに見えるのは、芦のまろ屋とも呼ばれる茶室、池中亭で、池の傍らには、百人一首の大納言
源経信が詠んだ 静岡県磐田市の見附宿で、東海道と別れて、浜名湖の北側を通り、本坂峠を越えて、愛知県の御油宿で東海道と合流する
のが姫街道である。 小生は数回に分けてこの街道を歩いたが、その途中で立ち寄ったのが、奥山半僧坊である。 奥山
半僧坊の道標を街道歩きでしばしば見たので、どういう寺だろうと
訪れた。 訪れると、臨済宗の方広寺という寺で、その寺院が大火で燃えたとき、開創の無文元選禅師(円明大師)に仕えた
半僧坊大権現を祀った半僧坊仮堂と開山円明大師の墓地が焼け残ったことから、火除けの神として、有名になった、とあ
った。 森閑とした境内には無数の羅漢像があった。 円明大師が中国の天台山で、石橋にお茶を献じられた時、羅漢が
姿を現した、という故事にちなむもので、宝暦年間から明和七年(1770)に作られたものである。 一体づつ表情が異なり、
面白かった。
静岡県磐田市の見附宿で、東海道と別れて、浜名湖の北側を通り、本坂峠を越えて、愛知県の御油宿で東海道と合流する
のが姫街道である。 小生は数回に分けてこの街道を歩いたが、その途中で立ち寄ったのが、奥山半僧坊である。 奥山
半僧坊の道標を街道歩きでしばしば見たので、どういう寺だろうと
訪れた。 訪れると、臨済宗の方広寺という寺で、その寺院が大火で燃えたとき、開創の無文元選禅師(円明大師)に仕えた
半僧坊大権現を祀った半僧坊仮堂と開山円明大師の墓地が焼け残ったことから、火除けの神として、有名になった、とあ
った。 森閑とした境内には無数の羅漢像があった。 円明大師が中国の天台山で、石橋にお茶を献じられた時、羅漢が
姿を現した、という故事にちなむもので、宝暦年間から明和七年(1770)に作られたものである。 一体づつ表情が異なり、
面白かった。  麻生内閣の景気対策の一環とした、3月末から土日曜日は高速道路をどこまで走っても千円という施策が始まったので、
これを利用して、これまで行ったことがなかった飛騨白川郷へ行った。 行きは順調で2時間程で着いたが、帰りは小生の
ような1000円組が多く、その為、渋滞して4時間以上かかった。
麻生内閣の景気対策の一環とした、3月末から土日曜日は高速道路をどこまで走っても千円という施策が始まったので、
これを利用して、これまで行ったことがなかった飛騨白川郷へ行った。 行きは順調で2時間程で着いたが、帰りは小生の
ような1000円組が多く、その為、渋滞して4時間以上かかった。  東京から伊豆の熱川温泉で集まるので来ないかの誘いがあり、1泊2日ならいけると返事する。 東京組は電車で来るとあ
ったが、新幹線で往復するのも芸がない。 これまで行けないでいた西海岸をドライブして、修善寺に出て、熱川に
入るというコースを計画した。 高速道路は早朝4時前にICから入ると、深夜割引で5割の値引きが受けられるので、当日
は自宅を3時半前に出た。 高速で走ると早く着きすぎるので、スピードを落として走り、富士川SCに寄り、コンビニで
食べ物を調達して、腹を満たし、沼津ICで降り、ナビの指定した通り走った。 すると土肥の町に出たので、車を停めて
歩いたが、富士山は見えない。 その代わり、土肥温泉は、江戸時代、幕府の金の鉱山があり、その鉱山の採掘現場からお湯が出たのが、起源であること
を知った。
土肥温泉を出ると、カーブが続く坂があり、上っていくと海が展望できるところがあり、そこからは雲ひとつない富士山を
見ることができた。
東京から伊豆の熱川温泉で集まるので来ないかの誘いがあり、1泊2日ならいけると返事する。 東京組は電車で来るとあ
ったが、新幹線で往復するのも芸がない。 これまで行けないでいた西海岸をドライブして、修善寺に出て、熱川に
入るというコースを計画した。 高速道路は早朝4時前にICから入ると、深夜割引で5割の値引きが受けられるので、当日
は自宅を3時半前に出た。 高速で走ると早く着きすぎるので、スピードを落として走り、富士川SCに寄り、コンビニで
食べ物を調達して、腹を満たし、沼津ICで降り、ナビの指定した通り走った。 すると土肥の町に出たので、車を停めて
歩いたが、富士山は見えない。 その代わり、土肥温泉は、江戸時代、幕府の金の鉱山があり、その鉱山の採掘現場からお湯が出たのが、起源であること
を知った。
土肥温泉を出ると、カーブが続く坂があり、上っていくと海が展望できるところがあり、そこからは雲ひとつない富士山を
見ることができた。 伊勢街道を歩いた時、三重県明和町の斎宮跡に立ち寄った。 斎宮とは、に伊勢神宮に天皇の名代として奉仕した斎王の宮
殿と斎宮寮という役所のあったところである。 天皇が即位するたびに、伊勢神宮に天皇の名代として奉仕する斎王が
未婚の皇女の中から選ばれた。 この制度は、平安時代から南北朝時代まで六百六十年間も続き、その間、記録では六十人
余の斎王がいた、とある。 中には恋人がいたのに、中を割かれ、泣きながら、都を下って行った姫君もいたという。
伊勢街道を歩いた時、三重県明和町の斎宮跡に立ち寄った。 斎宮とは、に伊勢神宮に天皇の名代として奉仕した斎王の宮
殿と斎宮寮という役所のあったところである。 天皇が即位するたびに、伊勢神宮に天皇の名代として奉仕する斎王が
未婚の皇女の中から選ばれた。 この制度は、平安時代から南北朝時代まで六百六十年間も続き、その間、記録では六十人
余の斎王がいた、とある。 中には恋人がいたのに、中を割かれ、泣きながら、都を下って行った姫君もいたという。  太閤秀吉が、木下藤吉郎時代に木曽川の流れる敵地に一夜で城を築いた話は有名である。 吉川英治の太閤記では、東濃
の武将を調略して味方につけ、土豪の蜂須賀小六を使い、上流から資材を乗せた筏を下らせて、一気に砦を築き、敵の
反撃を食い止め、美濃攻略に糸口をつけた、とある。
太閤秀吉が、木下藤吉郎時代に木曽川の流れる敵地に一夜で城を築いた話は有名である。 吉川英治の太閤記では、東濃
の武将を調略して味方につけ、土豪の蜂須賀小六を使い、上流から資材を乗せた筏を下らせて、一気に砦を築き、敵の
反撃を食い止め、美濃攻略に糸口をつけた、とある。